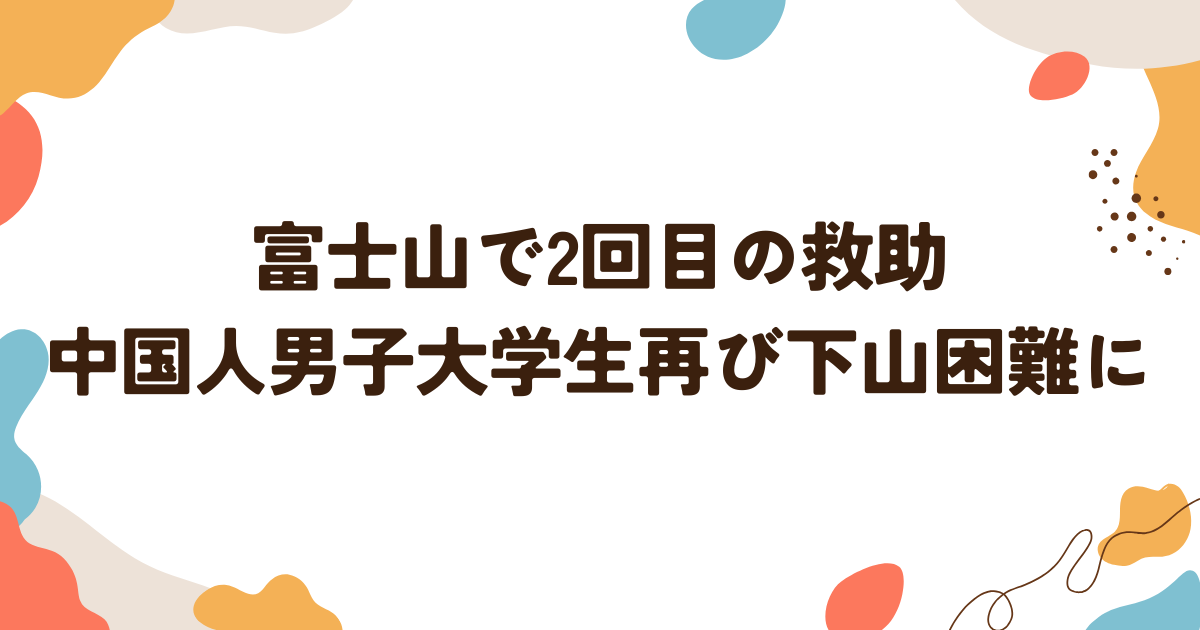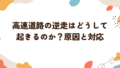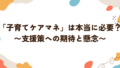2025年4月26日、富士山8合目付近で中国籍の男子大学生(27歳)が体調不良により下山困難となり、静岡県警の山岳救助隊によって救助されました。この男性は、4日前の22日にも富士山頂でアイゼン(登山用の滑り止め具)を紛失し、下山できなくなったため、山梨県の防災ヘリで救助されたばかりでした。今回の登山は、前回の救助時に置き忘れた携帯電話などを回収するためだったと報じられています。
このような事例は、登山者の装備や計画の不備が原因で、救助隊の出動が必要となるケースの一例です。特に富士山のような高山では、天候の急変や高山病のリスクが高く、十分な準備と計画が不可欠です。
山岳救助の流れと費用
公的機関による救助
山岳での遭難時には、警察の山岳警備隊や消防の山岳救助隊が捜索・救助を行います。
これらの公的機関による救助活動は、原則として費用が発生しません。これは、緊急を要する怪我や病気で救急車を利用した際の搬送費が税金で賄われるのと同様に、捜索や救助にかかった費用も税金で賄われるためです。
民間による救助
一方で、民間の山岳会や山小屋のスタッフが救助活動に協力する場合、その費用は遭難者に請求されることがあります。例えば、民間の山岳会に協力を依頼した場合、1日1人あたり2~3万円の費用が発生します。また、民間のヘリコプターを使用した場合、1日3時間の飛行で約150万円前後の費用がかかることもあります。
富士山での登山と救助
富士山は標高3,776メートルの日本最高峰であり、多くの登山者が訪れます。しかし、その標高ゆえに高山病のリスクが高く、また天候の急変も頻繁に起こります。そのため、十分な装備と計画が必要です。特に、登山計画書の提出や、GPSアプリの活用、事前の天候チェックなどが推奨されています。
救助費用の負担と議論
公的機関による救助活動は原則として無料ですが、その費用は税金で賄われています。
そのため、無謀な登山や装備の不備による救助要請が増えると、税金の負担が増加することになります。このような背景から、救助費用の一部を遭難者に負担させるべきだという意見もあります。
実際に、埼玉県では、全国で初めて自治体ヘリによる山岳救助を有料化する条例が施行され、約1時間の飛行における燃料費として5万5,000円を請求しています。
登山計画書の提出義務
登山者の安全確保に向けた取り組みは、各地で進められています。
たとえば長野県では、「長野県山岳遭難防止条例」に基づき、一定の山岳地域を対象に登山計画書の提出が義務付けられています。これにより、登山前の準備や安全管理が強く促され、遭難リスクの低減が図られています。
一方、富士山においては、山しており、一部の登山ルートでは登山計画書の提出が義務となっています。ただし、すべてのルートで義務化されているわけではなく、ルートによって対応が異なるため、登山前に各自治体の最新情報を確認することが重要です。
登山者への注意喚起を
登山を計画する際は、各自治体の公式情報を確認し、適切な準備と計画を行うことが求められます。特に、登山道の状況や天候、野生動物の情報などは、登山の安全性に直結するため、最新の情報を把握することが重要です。
安全な登山を楽しむためにも、自治体が提供する情報を積極的に活用し、自己責任のもとで行動することが求められます。