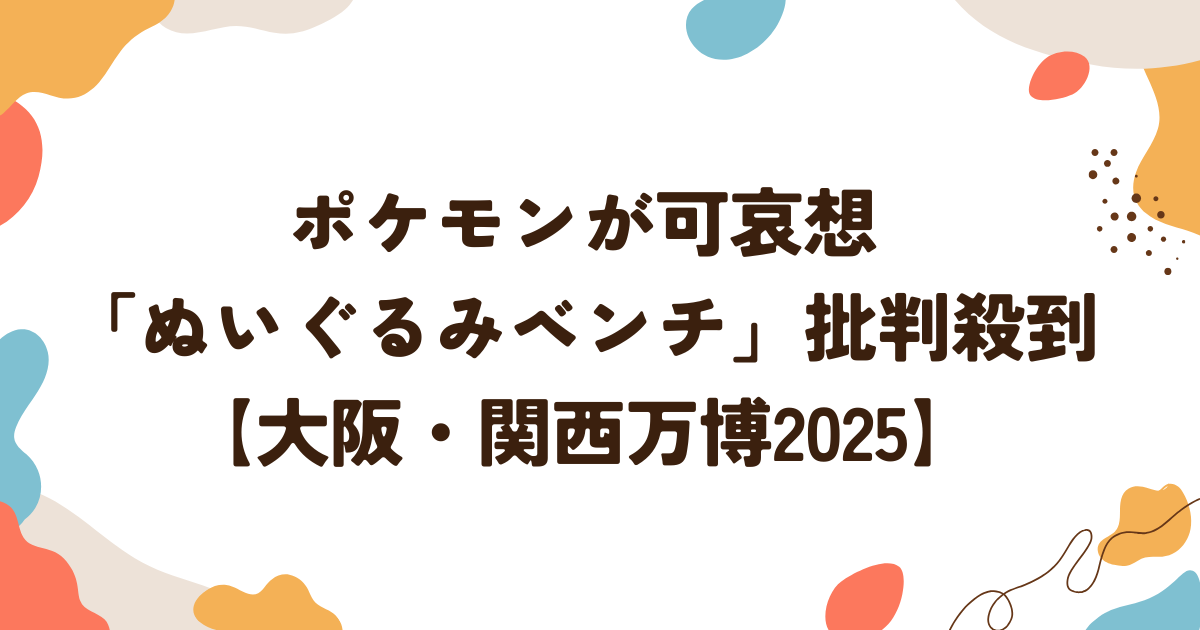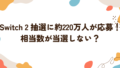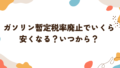2025年の大阪・関西万博で展示された「ぬいぐるみベンチ」が、SNS上で大きな議論を呼んでいます。
このベンチは、使用されなくなったぬいぐるみを透明なビニールに詰め込んで作られたもので、アップサイクルの一環として展示されました。
しかし、ポケモンファンの間で「悪趣味すぎる」と批判が殺到しました。任天堂はこの展示について「許諾したものではない」とコメントしています。
「ぬいぐるみベンチ」展示の背景
この「ぬいぐるみベンチ」は、株式会社ワイドレジャーが運営する体験ブース「遊んでい館?」に設置されました。同社は、ポケモンをはじめ遊ばれなくなったぬいぐるみに新たな価値を与えることを目的に、このベンチを制作しました。透明のビニールに詰め込まれたぬいぐるみたちは、再利用の象徴として展示されました。
「ぬいぐるみベンチ」ネット上の反響と批判
ネットの声(SNSの反応)
- 「これは悲しい気持ちになっちゃいますね…みんなぎゅうぎゅう詰めで可哀想…」
- 「ぬいぐるみ供養を神社でお金払ってやってもらってる自分は、これは座れない」
- 「可哀想すぎて心拍数上がるわ」
- 「これあまりにも悪趣味すぎません…? 自分の好きなキャラクターがこんな目に遭ってるの見たら泣いてしまいそう」
- 「万博に遊ばなくなったぬいでリサイクルして作りましたってベンチあったけど…デデンネさん…」
- 「ちょ!推しポケのハクリューぬいある!!?」
- 「ポチタとかジョージとかマイメロもいるな…」
- 「これって権利的にOKなの?」
- 「コレは任天堂怒っていいと思う。完全にブランドイメージに関わる案件でしょ」
- 「息が詰まりそうなぬいぐるみたち、見ていて辛い」
- 「アップサイクルの発想は分かるけど、これはやり方が間違ってる」
こうした声から見えてくるのは、「リサイクル・サステナブル」という意図は理解しつつも、「思い出の詰まったぬいぐるみをモノとして扱われたように感じた」ことへの強い違和感や悲しみです。また、著作権やブランドイメージへの懸念も多く見られました。
SDGsと感情の乖離
この展示は、持続可能な開発目標(SDGs)の一環として、アップサイクルを推進する目的で行われました。しかし、ぬいぐるみを大切にしてきた人々にとっては、思い出の詰まったぬいぐるみが詰め込まれた姿は、感情的に受け入れがたいものでした。SDGsの理念と、個人の感情との間に乖離が生じた例と言えるでしょう。
万博パビリオン、明暗分かれる評価
大阪・関西万博では、展示やパビリオンに対する評価が二極化しています。一部では「感動した」「美しい」と高評価を集める展示がある一方で、批判や疑問の声が集まっているブースも少なくありません。
たとえば、イタリア館は、ルネサンス芸術を現代的に再解釈した展示構成や、伝統素材と最新技術を融合させた建築デザインで来場者の関心を集めています。文化と創造性が調和した空間は、「本物のイタリアの空気を感じた」とSNSでも好評で、撮影スポットとしても人気を博しています。エジプト館も同様に、ピラミッドやファラオのモチーフを活かしたダイナミックな展示が称賛され、古代文明と未来のテクノロジーを結びつける演出が訪れる人々を魅了しています。
一方で、批判の声も根強く存在します。混雑対策の甘さも指摘されており、動線の分かりづらさや案内表示の不備も来場者のストレス要因となっています。
さらに、ネパール館では工事が一時中断される事態も報じられ、SNS上では「まだ完成していない」「予算や人員の管理はどうなっているのか」といった疑問が飛び交いました。このように、各国のパビリオンにおいて準備や管理体制の差が浮き彫りになっており、全体としての統一感や信頼性にも影響を与えつつあります。
炎上スポット巡りという視点
今回の「ぬいぐるみベンチ」のように、SNSで話題となった展示を巡る「炎上スポット巡り」という新たな観光の形も考えられます。賛否両論ある展示を実際に見て、自分自身の目で評価することは、万博の楽しみ方の一つかもしれません。
おわりに
「ぬいぐるみベンチ」の展示は、アップサイクルという理念のもとに行われましたが、感情的な反発を招く結果となりました。SDGsの推進においては、理念だけでなく、個人の感情や文化的背景にも配慮することが求められます。万博という大規模なイベントでは、多様な視点を持つ人々が集まるため、展示の意図と受け手の感情とのバランスを取ることが重要です。