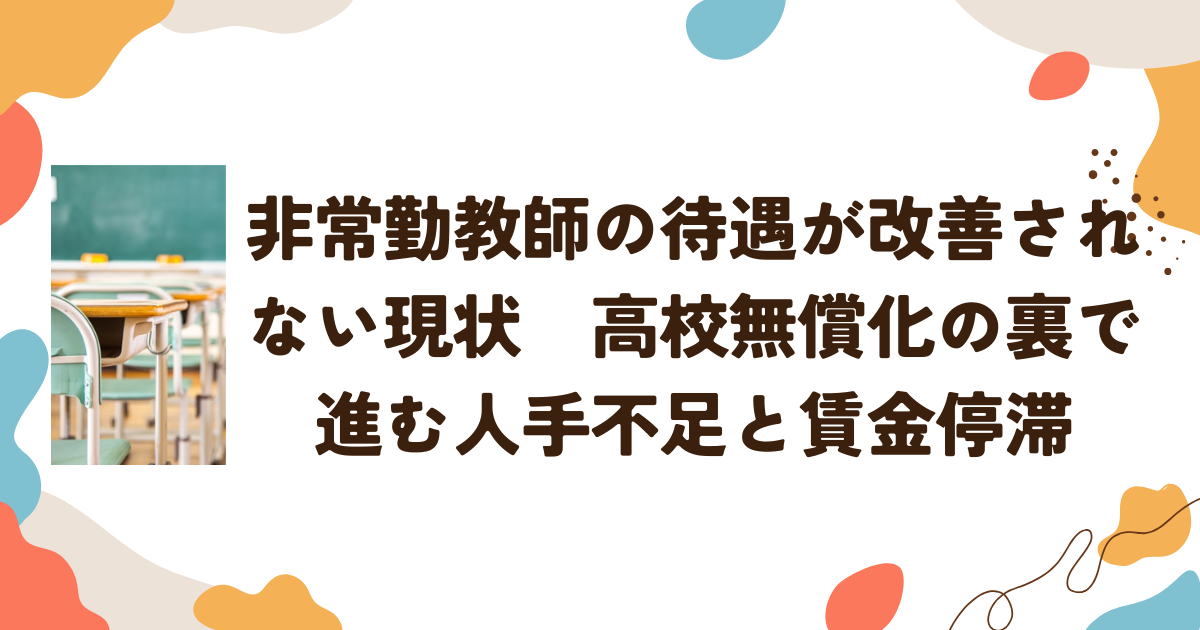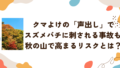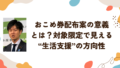非常勤教師の待遇改善が進まない現状が、教育現場で深刻な課題となっています。
高校無償化によって授業料の負担は軽くなったものの、その恩恵が教育を支える教員たちの給与や働く環境には十分に反映されていません。
特に私立高校では、授業料の値上げが相次ぐ一方で、非常勤講師の報酬は長年据え置かれ、生活が厳しいという声が相次いでいます。
こうした状況のなか、日大三島中学・高校の非常勤講師たちが待遇改善を求めてストライキに踏み切ると発表し、全国的な注目を集めています。
非常勤教師に依存する教育現場
文部科学省の統計によると、私立高校では非常勤や契約教員といった非正規雇用の割合が増加しています。
常勤教員の人件費を抑えるため、授業単位で雇用される非常勤教員に依存する学校が増えているのです。
しかし、非常勤教員は以下のような厳しい労働環境に置かれています。
- 年間契約・時給制が多く、夏休みなど授業がない期間は収入が途切れる
- 賞与・退職金・社会保険が適用外のケースも多い
- 担任業務や部活動指導などの負担を求められることもあるが、報酬は変わらない
こうした状況が続くことで、教育の現場では「人が集まらない」「優秀な教師が続けられない」という人手不足の悪循環が起きています。

“高校無償化”の裏で広がる矛盾
高校無償化制度――正式には「高等学校等就学支援金」は、国が授業料を補助する仕組みです。
しかしこの制度が拡充されるたびに、私立高校の授業料が上昇していることが問題となっています。
2026年度からは、支援金の上限が45.7万円に引き上げられ、所得制限も撤廃される予定です。
これにより「多くの私立高校が実質無償化される」とされますが、その一方で「上限額を基準に便乗値上げが進むのでは」と懸念されています。
学校側は「教育環境の充実」「設備投資のため」と説明しますが、授業料の値上げが教員の待遇改善に使われているかは不明です。
非常勤教員の現場では、「値上げしても給料は上がらない」という声が相次いでいます。
非常勤教師「生徒のために働いても生活が苦しい」
非常勤教員の多くは、情熱と使命感で教育に携わっています。
しかしその現実は厳しく、授業準備や採点に多くの時間を使っても、報酬は授業コマ数で決まっていて、時間外労働も多く、生活が成り立たないとの声もあります。
このように、教育現場を支える非常勤教員の努力が制度的に報われていないのです。
結果として、他職種への転職や離職が相次ぎ、教育の質を保つことすら難しくなりつつあります。
「待遇改善されない」非常勤講師の実態 ―三島中高の事例から
先にご案内した、日大三島ユニオンによるストライキ通告の報道では、私立学校における非常勤講師の「待遇改善されていない」問題が端的に浮き彫りになっています。
- 非常勤講師の給与が「授業1コマあたり」の金額で決まっており、年収200万円程度という報道があります。報道によれば20年以上ベースアップがなかったとされています。
- また、私立学校であっても「私学共済」等の社会保障制度(厚生年金など)への加入を、非常勤講師に対して学校法人側が条件付きで認めていないという指摘がなされています。
- さらに、部活動担当・授業待機時間を含むと「週5~6日出勤」「実質的にフルタイム勤務」に近い状態であるにもかかわらず、非正規という立場ゆえに待遇が正規教員と比較して劣るという声が上がっています。
- ユニオン側は「来年度から非常勤教職員の給与を15%引き上げること」を要求し、要求が受け入れられなければ11月25日に授業冒頭15分のストライキを行うと通告しています。
このケースは、教育現場における「非常勤だから仕方ない」「安定雇用でないから待遇も低めで」という常態化した構造を、非常勤講師自身が「このままでは教育を維持できない」として動き出した例とも言えます。
私立学校・非常勤講師の文脈であっても、公立校で報じられている「非正規教員の増加-待遇格差-人手不足」の構図と通底しており、教育現場全体の課題を象徴しているといっても過言ではありません。

高校無償化の“次の課題”は教員待遇の見直し
高校無償化は、確かに家庭の教育費負担を軽減する重要な政策です。
しかし、教育を担う側――つまり教員の待遇が悪化すれば、教育の質自体が崩れる危険があります。
今後、国と自治体には以下のような視点が求められます。
- 授業料値上げ分の使途を透明化すること
- 非正規教員の待遇改善や雇用安定化に補助を拡大すること
- 教育現場の人材流出を防ぐための長期的な人件費支援制度を構築すること
授業料の「無償化」だけでなく、教育を支える「労働の適正化」がなければ、本当の意味での教育改革は実現しません。
まとめ:教育の根幹を支える“人”への投資を
非常勤教員の待遇が改善されないままでは、どんな制度改革も持続的な効果を生みません。
「教育は人で支えられている」という原点に立ち返り、高校無償化の恩恵が教育現場の労働者にも届く仕組みが求められています。
授業料の値上げや制度の拡充が、本当に“生徒と教師の未来”につながる形に修正されることが、これからの課題です。