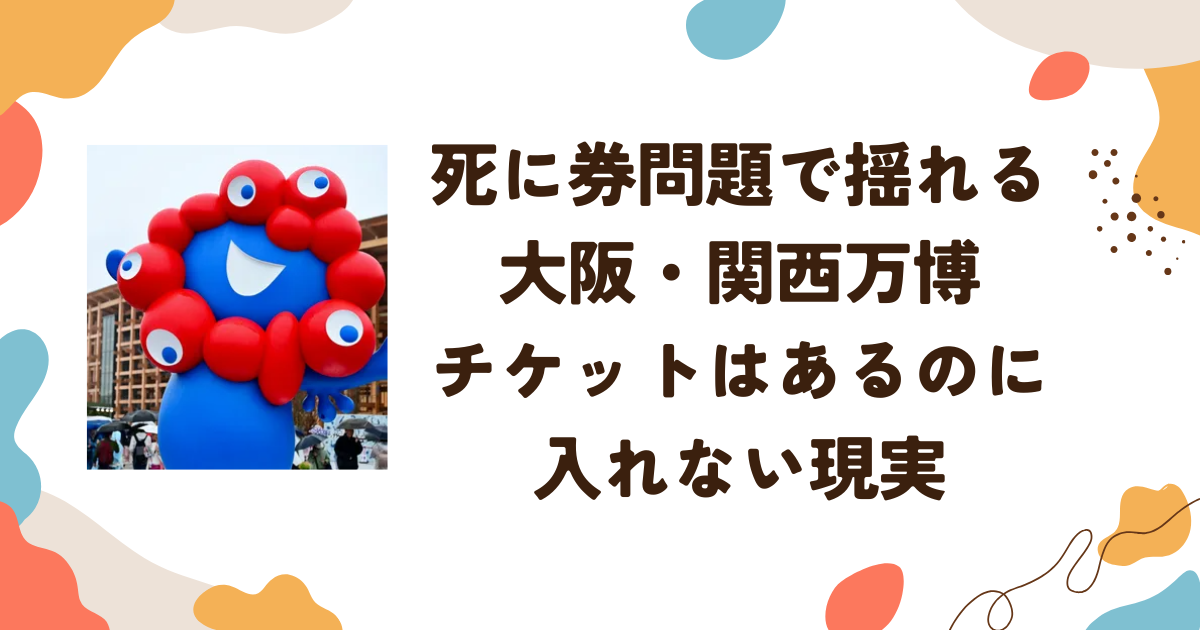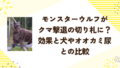大阪・関西万博で深刻化している「死に券」問題。チケットを買ったのに入場できないという声が相次ぎ、SNSでも批判や困惑が広がっています。
本記事では、死に券が生まれた背景と払い戻し問題、混雑の実態、そしてSNSで寄せられている声を整理します。
死に券とは?大阪関西万博で懸念されるチケット問題
大阪関西万博では「死に券」という言葉が話題になっています。死に券とは、本来は投票用語ですが、万博では「購入したものの使われないチケット」を指して使われています。多くの人が来場を見込んで買ったものの、混雑や予定変更で結局行けず、無駄になってしまうケースが懸念されています。
死に券が生まれる背景
万博チケットは事前購入制で、日付指定券や予約枠が埋まると柔軟な利用が難しくなります。さらに混雑予想やアクセスの不安、転売禁止の仕組みなどが重なり、「結局使わずに終わるのでは」という声が強まっています。
万博はいつまで?残り期間が少ない現実
大阪関西万博は 2025年4月13日から10月13日まで の開催で、残りの開催期間は限られています。「まだ行ける」と思っているうちに時間が過ぎ、結局行けずに死に券化してしまう可能性が高まっています。
なぜ死に券は発生したのか
死に券が発生した原因は大きく分けて以下の通りです。
- 入場には日時予約が必須で、人気の時間帯がすぐ満杯になる
- 通期パスや複数回入場可能なチケットが多く出回り、予約枠が不足
- 閉幕が迫り、予約希望者が殺到したことで予約が取りづらい
- 購入時に「予約しなければ使えない」ことが十分に伝わっていなかった
この仕組みにより、「お金を払ったのに使えない」という不満が爆発しているのです。
死に券の枚数はどれくらい?
報道では、100万枚以上の未使用チケットが存在するのではないかとの推測が出ています。ただし、これは販売総数と来場者数の差から導かれたもので、正確な死に券の数は公表されていません。
いずれにせよ「大量のチケットが宙に浮いている」状態であることは間違いなく、消費者の不信感を強めています。
払い戻しはなぜできないのか
死に券を抱えた人々の関心は「払い戻しはできるのか」という点に集まります。
しかし協会は、「原則として払戻しは行わない」と明言しています。規約にも同様の記載があり、自然災害や主催者都合による中止以外では返金対象にならないとされています。
これに対しSNSでは、
- 「予約取れないのに返金なしって消費者軽視すぎ」
- 「協会の責任じゃないと言うけど、制度設計に無理があったのでは?」
といった不満が噴出しています。

万博の混雑と当日券争奪戦
死に券問題が深刻化する一方で、実際の会場は連日大混雑。
- 当日券を求めて早朝から長蛇の列
- 人気パビリオンは数時間待ち
- 午後以降は予約が取れず、入場しても体験できないケースが多発
SNSでも、
- 「6時に並んで当日券ゲット…もう体力勝負」
- 「子どもを連れてきたけど、待ち時間が長すぎて何も見られなかった」
という声が目立ちます。
死に券と転売・譲渡の課題
公式規約では転売は禁止されていますが、譲渡は一定条件で可能です。しかし実際には、予約枠が埋まっているため譲渡しても無意味というケースが多発。
SNS上では、
- 「高額転売チケットを買っても予約取れないのでは詐欺同然」
- 「譲ってもらったけど結局入れなかった」
といった声も上がっています。
死に券をめぐるSNSの声
最後に、SNSで特に多い意見をまとめます。
- 「死に券になるなんて知らなかった。説明不足では?」
- 「返金なしは納得いかない。せめて代替措置を」
- 「万博の思い出が不満で終わるのは残念」
- 「最初から予約枠を調整しておけばこんなことにならなかった」
批判が大半ですが、中には「早めに予約して楽しめた」というポジティブな声もあり、来場計画の立て方次第で体験に大きな差が出ていることが分かります。
まとめ
死に券問題は、制度設計の不備と情報不足が招いたトラブルでした。
- チケット購入=入場確約ではない
- 払い戻しは原則不可
- 閉幕が近づくほど混雑と予約困難が増大
という現実を、もっと早い段階で共有していれば混乱は抑えられたかもしれません。
大阪・関西万博の教訓は、今後の大規模イベントにも活かされるべきでしょう。