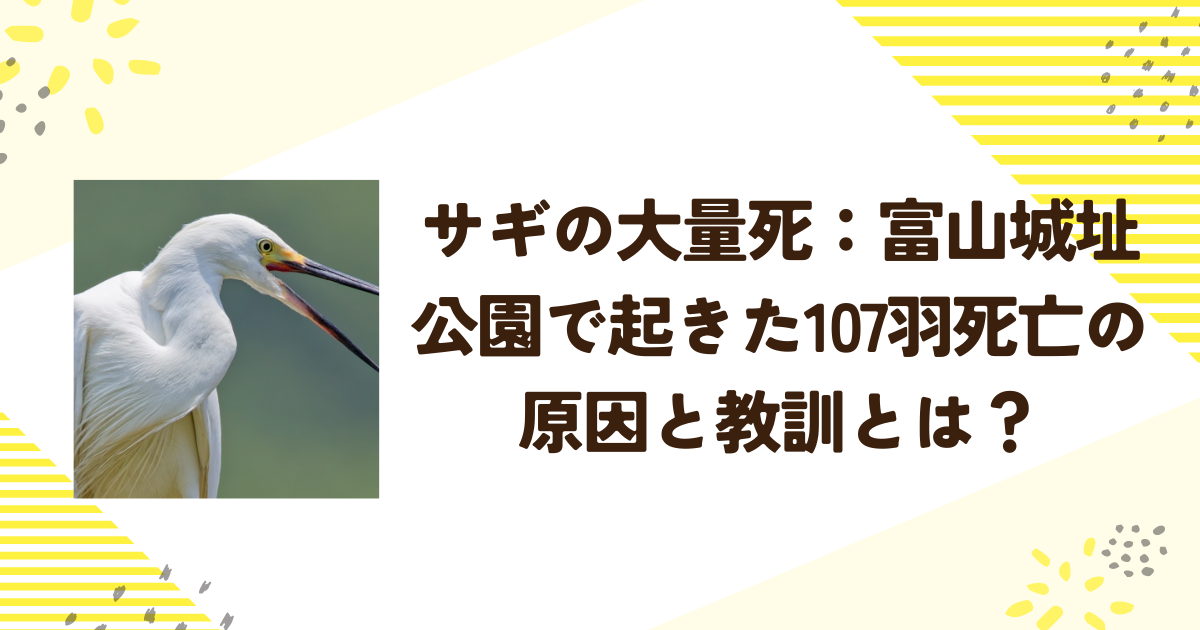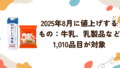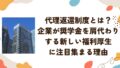サギの大量死から考える都市と野生動物の共存の課題
2025年夏、富山城址公園で107羽ものサギが相次いで死ぬという衝撃的な事態が発生しました。死骸が初めて確認されたのは6月末。その後1か月のうちに100羽以上が命を落とし、地元住民のみならず、全国的な注目を集めるニュースとなっています。
この記事では、サギの大量死の原因とされる「伐採時期の誤り」について詳しく解説しながら、サギの生態や繁殖行動、大量発生の背景、人と野生動物の共存の課題についてもわかりやすくお伝えします。
サギの大量死、原因は「繁殖期の伐採」だった
まず、今回の大量死の原因について富山市が公表した結論は明確です。
「繁殖期の真っ最中にサギが営巣していた松の木6本を伐採したことが原因」
富山城址公園では、数年前からサギが堀沿いの高木(主にマツやサクラ)をすみかにして繁殖していました。しかし、その鳴き声やフン害に対する市民からの苦情が続き、2025年6月下旬に松の木を伐採。ところがこの時点では、まだ巣立ちを終えていない幼鳥が多数いたことが判明しています。
巣を失った幼鳥たちは、自力でエサを取ることができず衰弱。結果として、7月末までに107羽が死亡しました。
市の記者会見では、「サギの生態に関する知識が不十分で、事前の専門機関への相談もなかった」と説明し、深く謝罪しています。

サギはなぜ公園に大量発生していたのか?
そもそも、なぜ富山城址公園にこれほど多くのサギが集まっていたのでしょうか? その背景には、都市部特有の「安全で快適な環境」が関係しています。
◆ 安全性の高さ
サギにとって、公園の高木は天敵(カラスや哺乳類)から身を守るうえで非常に有利な環境です。また、公園内は人の出入りがあっても直接的な脅威は少なく、安心して巣作りができる場となります。
◆ エサ場へのアクセス
サギは水辺を好む鳥で、堀や河川、水田などで魚・両生類・昆虫などを捕食します。富山城址公園は堀に囲まれており、自然の餌場が近くにあることも大きな要因でした。
◆ 集団営巣の習性
サギ類(特にアオサギやコサギなど)は集団で同じ木に巣をつくる習性があります。1本の大木に複数の巣が築かれることもあり、年を追うごとに群れの規模が大きくなることがあります。
こうした環境が整った結果、富山城址公園は「都市に現れた理想的なサギの繁殖地」となっていたのです。

サギの繁殖生態──知られていない重要な知識
今回の「サギの大量死」事件を深く理解するには、サギの繁殖行動と子育てのタイミングについての知識が欠かせません。
◆ 繁殖期:春〜夏(4月~8月)
多くのサギ類は春にペアをつくり、4〜5月に営巣を開始します。卵を産んでから孵化するまでに約3週間、さらに巣立ちまでは1か月以上かかります。
◆ 幼鳥の特徴
巣立ち直後のサギの幼鳥は、まだ十分な飛行能力や採餌能力を持っていません。親鳥が餌を運ぶのを待って成長していくため、巣を失うことは命に直結する重大なリスクとなります。
◆ 巣の放棄と混乱
伐採などで親鳥がストレスを受けたり、巣に近づく人が増えると、親が巣を放棄する「擬死行動」や巣立ち前の飛び立ちが起こることがあります。今回のように伐採で木ごと巣を失った場合、幼鳥はその場で餓死や脱水死を迎えるしかありません。
今回の問題は違法ではなかったのか?
野鳥は「鳥獣保護法」によって守られています。巣を破壊したり、生体を傷つけたりする行為には原則として規制があります。
しかし、今回の件では以下の理由で「違法性はない」と判断されています。
- サギの死は意図的ではなく、間接的な被害
- 市は鳥インフルエンザや毒物検査を実施し、安全性を確認
- 鳥獣保護管理法上、やむを得ず行った作業とみなされた
とはいえ、「知らなかったでは済まされない」ほどの重大な失態であったことは確かです。

富山市がとるべき再発防止策とは?
市は再発防止のため、以下のような対策を発表しています。
- サギの繁殖期を避けた伐採や整備作業
- 事前に専門機関へ相談
- 公園内で営巣を許容する区域の設定
- 市民への情報共有や自然教育の強化
さらに、野生動物と人が共存する都市空間のあり方として、「自然との共生」をテーマにした取り組みが求められています。
「サギの大量死」が私たちに教えてくれたこと
今回のサギ大量死は、単なる「動物のニュース」ではありません。
これは、人間の行動が自然にどれだけ影響を及ぼすかを示した象徴的な出来事です。そして、公園のような都市の中の自然空間では、人と動物の境界線が極めてあいまいであることも浮き彫りになりました。
適切な知識と判断があれば、サギの命は守られたかもしれません。自然に対する敬意と理解を深めることこそが、再発防止の第一歩となるのです。
命を守る都市づくりへ
- 富山城址公園で107羽のサギが死亡した原因は、繁殖期の松伐採。
- サギの生態(集団営巣、親による給餌)が理解されていなかった。
- 市は「判断ミス」と認め、今後の対応を見直す方針。
- サギの大量発生は「都市の自然環境」がもたらしたもの。
- 人と野生動物が共存できる都市管理が急務。
サギの命を無駄にしないためにも、今後は「生き物の目線」で都市を見直す視点が求められます。