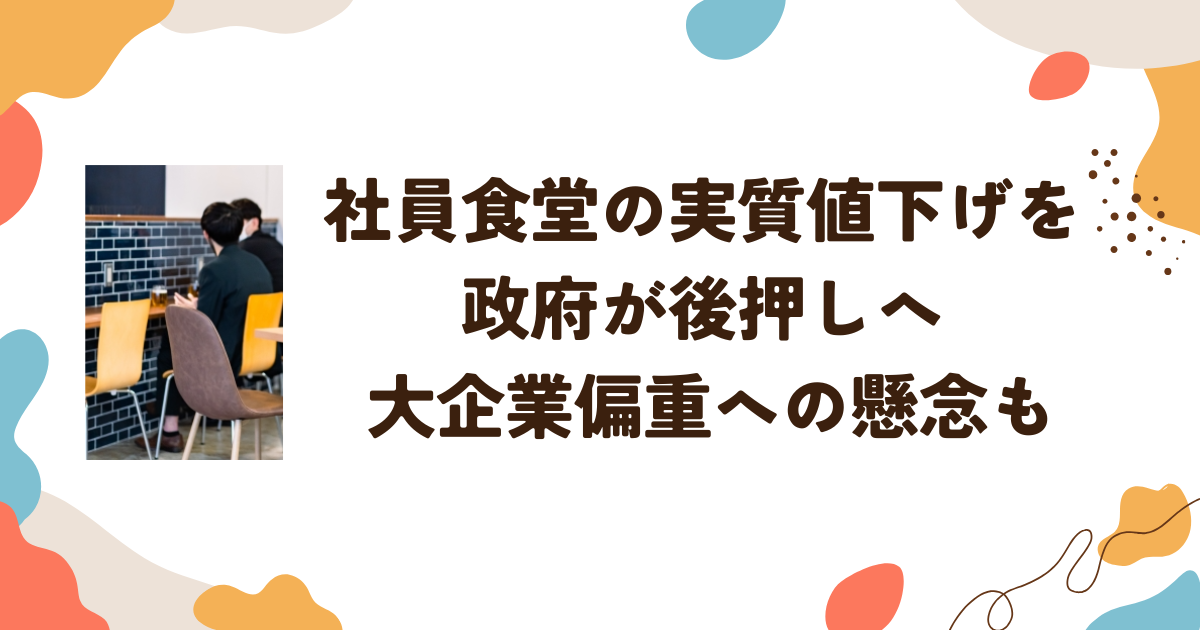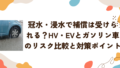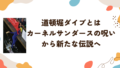政府は社員食堂や弁当支給など「職場での食事補助」に焦点を当てた税制改正を検討しています。2026年度の税制改正において、社員食堂の食事代の実質的な値下げにつながる支援策が盛り込まれる可能性が出てきました。
近年、食品価格の高騰が家計を直撃しています。スーパーで買い物をするたびに「前よりも値段が上がったな」と感じている人は少なくないでしょう。コメや小麦といった主食に加え、肉・魚・野菜など幅広い食品が値上がりし、さらに輸送費や人件費の上昇も重なって、飲食にかかる負担は増す一方です。
本記事では、現行制度の仕組みと課題、政府が検討する見直しの方向性、そしてその効果についてわかりやすく解説します。
現行制度の仕組み ― 社員食堂の補助と非課税枠
現在、日本では企業が従業員に食事を提供する際に税制上の特例があります。たとえば社員食堂での食事代や、会社が支給する弁当に補助が出る場合、その補助は原則的に「従業員の所得」と見なされます。しかし、一定の条件を満たせば課税対象から外れ、非課税で受けられる仕組みになっています。
条件は次の二つです。
- 従業員が食事代の半分以上を自己負担していること
- 企業の補助額が月額3,500円(税別)以下であること
この範囲内であれば、企業からの補助は所得税の課税対象になりません。つまり、従業員は税金を払わずに実質的に安く食事を利用できるのです。
なぜ見直しが必要なのか
この制度は実に40年以上も改正されていません。非課税となる補助の上限額は「月3,500円」。仮に社員食堂を月20日利用すると、1日あたりわずか175円しか非課税の範囲として認められていない計算になります。
しかし現代の物価水準を考えると、この金額はあまりにも低いといえます。社員食堂の定食が500円程度であったとしても、企業が補助できるのはそのうち175円にすぎず、それ以上を補助すると課税対象になってしまうのです。1984年当時の物価と比べれば、いかに実態と乖離しているかがわかるでしょう。
食品価格の高騰が続くなかで、従業員の昼食代の負担は重くなっています。特に都市部では外食価格も上昇し、500円ワンコインランチを見つけるのは困難になってきました。社員食堂は福利厚生として従業員を支える大切な仕組みですが、現行の税制では企業が十分に支援できないという課題が浮き彫りになっています。
政府の検討内容 ― 非課税上限額の引き上げ
こうした背景から、政府は2026年度の税制改正において「非課税となる食事補助の上限額」を引き上げる方向で検討を進めています。これが実現すれば、企業が社員食堂の食事代をより多く補助できるようになり、従業員は追加の税負担なしで恩恵を受けられることになります。
たとえば上限額が1日300円や400円に引き上げられれば、社員食堂での昼食が500円の場合、企業が半分以上を負担しつつ非課税の範囲で運営できる可能性が高まります。従業員にとっては「安く食べられる」メリットが増し、企業にとっても福利厚生の充実をアピールできるでしょう。
期待される効果
- 従業員の生活支援
食費は家計に占める割合が大きいため、社員食堂の値下げは実質的な賃上げと同じ効果を持ちます。特に若手社員や子育て世帯にとっては大きな助けになるでしょう。 - 健康促進への波及効果
社員食堂では栄養バランスを考えた食事が提供されるケースが多く、安価に利用できる環境が整えば健康的な食生活につながります。長期的には医療費の抑制にも寄与するかもしれません。 - 企業の人材確保や定着に寄与
福利厚生の充実は企業の魅力を高め、人材確保や定着につながります。特に人手不足が深刻な現在、社員食堂の整備と支援は企業戦略の一環としても重要です。 - 物価高対策の一助
政府が掲げる物価高対策の柱として、食費の負担を和らげる仕組みを整えることは国民生活の安定に直結します。直接的な値下げではなくても「実質値下げ」という効果が期待できます。

専門家の見解 ― 公平性への疑問も
一方で、この施策には懸念を示す識者もいます。エコノミストの門倉貴史氏は、ヤフーコメントで次のように指摘しています。
「このような社食支援策は、物価高で本当に困っている人たちの生活支援を優先するという政府の方針に合致しない。というのも社員食堂がある企業は従業員数が多く、平均年収の高い大企業に偏っているからだ。2020年の労働政策研究・研修機構の調査によると、従業員数30人未満の中小企業で社員食堂がある企業の割合は16.5%にすぎない。」
つまり、制度を見直しても恩恵を受けられるのは主に大企業の従業員に限られ、中小企業や非正規雇用の人々には届きにくいのではないか、という懸念です。こうした公平性の問題は、今後の議論において重要な論点となるでしょう。
残された課題
- 財政負担と公平性
税制優遇は国の税収減を意味します。どの程度の上限額引き上げが適切か、また社員食堂のない企業や中小企業との公平性をどう確保するかが議論の焦点になります。 - 中小企業への波及効果
社員食堂は大企業に多く、中小企業では弁当支給や食事手当が主流です。制度改正が中小企業の従業員にも実効性を持つ形で設計されるかどうかが重要です。 - 企業の実施意欲
補助額が引き上げられても、企業側にコスト負担が残るのは事実です。企業が積極的に利用するインセンティブを高めるためには、税制だけでなく補助金や助成制度と組み合わせる工夫も必要です。
まとめ
社員食堂の食事代補助に関する非課税枠は、1984年以来見直されていませんでした。しかし、物価高が続く現代において、当時の制度設計のままでは従業員の負担軽減には不十分です。政府が検討している非課税枠の引き上げは、実質的に「社員食堂の値下げ」を後押しするものであり、生活支援、健康促進、人材確保など多方面でプラスの効果が期待できます。
ただし、門倉氏が指摘するように、大企業中心の恩恵となり中小企業の従業員に届きにくい可能性は否めません。制度の実効性を高めるためには、社員食堂を持たない企業への配慮や別の支援策を組み合わせる必要があります。
約40年ぶりの見直しは時代の要請といえる一方で、公平性をどう担保するのか。物価高という逆風の中、働く人々が安心して日々の食事をとれるようにするために、今後の制度設計に注目が集まります。
社員食堂の値下げは「小さな政策」かもしれませんが、毎日の食事を支える大きな力になる可能性があります。物価高に苦しむいまだからこそ、身近な生活支援策が求められているのです。