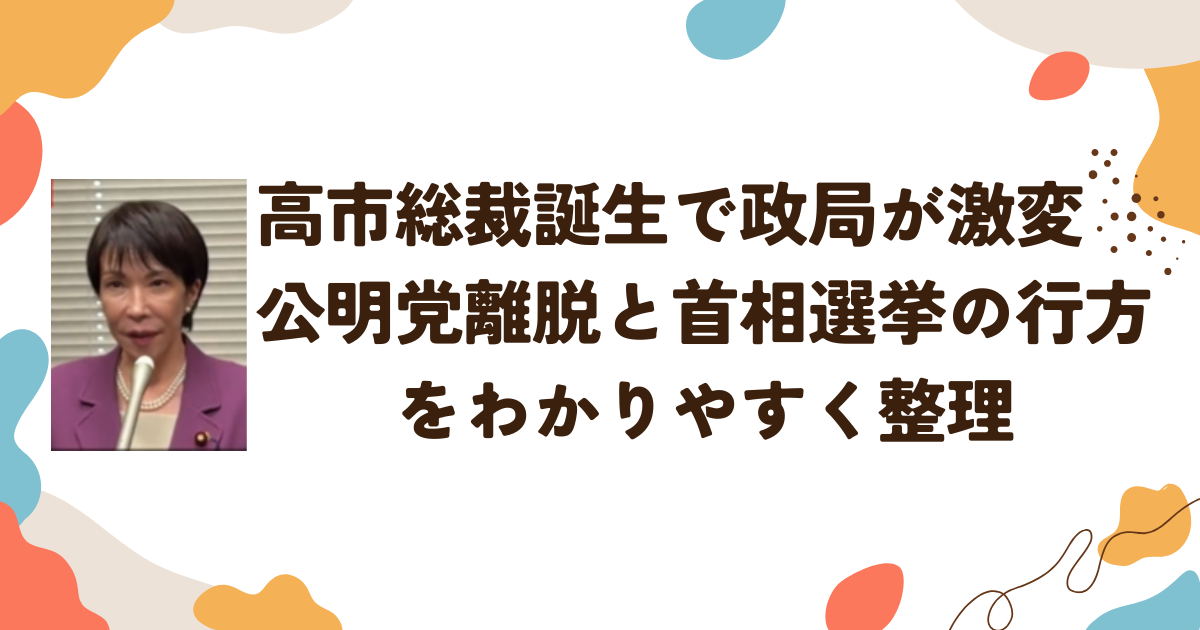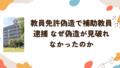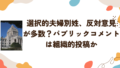2025年10月、自民党総裁に高市早苗氏が選出されたことを皮切りに、日本の政界は一気に緊迫した局面を迎えました。これまで長く続いてきた自民・公明の連立体制は崩れ、維新や国民民主党を軸にした新たな連携の可能性が浮上しています。さらに、従来であれば当然のように成立していた「自民党総裁=首相」という構図も揺らぎ、首相指名選挙そのものが注目を集めています。
この記事では、高市総裁誕生から現在までの流れ、公明離脱の背景、首相選挙のしくみ、維新や国民との連携の可能性、そして今後のシナリオをわかりやすく整理します。
高市早苗氏が自民党総裁に選出
自民党は総裁選を実施し、党内の支持を背景に高市早苗氏が新総裁に就任しました。通常であれば、与党第一党の総裁がそのまま内閣総理大臣に指名されるのが通例であり、報道でも「新首相誕生」と同義で扱われてきました。
しかし、この前提は今回崩れることになります。その理由は、公明党の動きに直結します。
公明党の連立離脱で何が変わったのか
高市氏が総裁に選ばれた直後、公明党は自民党との連立政権から離脱する方針を表明しました。背景には、政策面での溝や人事方針への不満、支持者向けの説明責任など、複合的な事情があるとされています。
この離脱によって大きく変わったのは、「衆議院での議席数」です。自民党は単独では過半数に届かず、従来のように“自動的に”首相を出せる立場ではなくなりました。過去30年近く、首相指名選挙は「儀式的」な側面が強く、実質的な争いになることはほとんどありませんでしたが、今回は事情が異なります。
なぜ「自民党総裁=首相」にならないのか?
かつては「自民党が第一党で、かつ公明党と連立して過半数を確保している」という前提が存在しました。このため、党総裁がそのまま国会での首班指名を勝ち取り、新内閣を組織する流れが安定して続いてきたのです。
しかし今回は以下の点が大きく影響しています:
- 公明党が連立から離脱
- 自民党単独では衆議院の過半数を確保できない
- 維新・国民・立憲・公明などが連携を模索
- 「自民総裁=自動的に首相」の条件が崩壊
その結果、高市総裁は“指名されれば首相”という立場ではあるものの、自力での当選が保証されている状況ではありません。

首相選挙(首班指名)とは?
日本では内閣総理大臣は国民の直接選挙ではなく、国会による「首班指名選挙」で選ばれます。正式名称は「内閣総理大臣指名選挙」で、憲法・国会法に基づいて以下の流れで行われます。
● 衆議院と参議院でそれぞれ投票
各議院で候補者名を書いて投票し、多数を得た人物を選出します。
● 衆議院の優越
衆参で異なる人物が選ばれた場合、憲法の規定により「衆議院の結論が優先」されます。
● 過半数が取れない場合は決選投票
1回目で過半数に届かないと、上位2名で再投票が行われます。
つまり――
「誰が首相になるか」は、議席と連携の組み合わせで決まる政治交渉の結果であり、「自民党総裁だから自動的になる」という保証はありません。
維新・国民・公明・立憲… 各党の動き
● 日本維新の会
自民との連携を視野に入れつつも、独自路線を強調。政策面では協力の余地を残しています。
● 国民民主党
玉木代表を軸に「首班候補」としての存在感が高まっており、数合わせ次第では“逆転指名”の可能性すら議論されています。
● 公明党
連立離脱後の立ち位置は流動的で、自民と距離を取りつつも、野党との協調も模索。
● 立憲民主党
最大野党として主導権を握る構えですが、首班候補をどうするかは情勢次第。
いずれの勢力も、「誰を首相に選ぶか」を軸に駆け引きを続けています。

首相指名の現実的シナリオ
現在想定される主な展開は次の3つです。
① 高市氏が他党の協力を得て当選
維新・国民・無所属などの一部議員の支援を取り付けて過半数確保を狙う形です。
② 野党系の候補が首相に指名される
国民民主や維新が立憲と組み、玉木氏などを首班に据える「非自民連立型」も現実味を帯びています。
③ いったん混迷し、条件付き支持や暫定合意に収束
政策合意や期限付きの協力を条件に、首班選出だけを先行させる可能性もあります。
国民生活や政策への影響
短期的には以下のようなリスクが指摘されています。
- 内閣発足の遅れによる政策停滞
- 補正予算や経済対策の審議遅延
- 為替・株式市場の不安定化
- 外交スケジュールの再調整
一方で、中期的には「与野党再編」「政策再整理」という形で新しい政治構図が見えてくる可能性もあります。
今後の焦点は「数」と「条件」
これから注目されるポイントは以下の通りです。
- 自民党が維新や国民をどこまで取り込めるか
- 公明党が完全に離れるのか、条件付きで接点を持つのか
- 野党側が首班候補を一本化できるか
- 首班指名選挙の日程調整と駆け引き
特に「首班指名前の政策カード提示」や「院内会派との水面下交渉」が焦点になります。
まとめ:政治の常識が大きく書き換わる局面
今回の政局は、これまで半ば当然視されてきた「自民党総裁=首相」という構図が通用しなくなったことを象徴しています。連立離脱によって議席数の前提が崩れ、各党の交渉力が一気に可視化されました。
首相指名選挙は、国会勢力の足し算・引き算だけでなく、政策・人事・選挙戦略まで絡む総合戦です。今後の展開によっては、自民以外から首相が誕生する可能性すら排除できません。
情勢は刻々と変化していますが、重要なのは「首相は誰が選ぶのか」「どの勢力とどの政策で組むのか」「国民生活にどんな影響が出るのか」という視点です。今後の報道や公式発言を確認しながら、引き続き冷静に動向を追う必要があります。