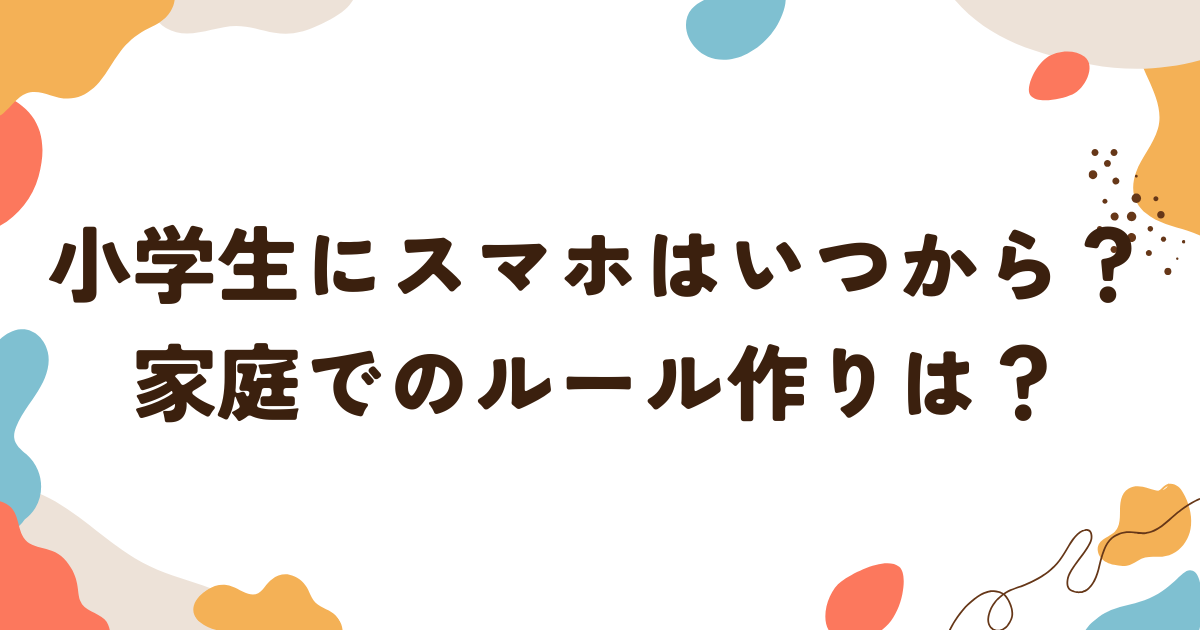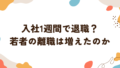「小学生にスマホはいつから持たせるべきか?」新学期が始まると、子どもから「スマホがほしい」と言われて悩む保護者の方も多いのではないでしょうか。特に小学校高学年にもなると、周囲の友達がスマートフォンを持ち始めることも増え、子ども自身も強く関心を示すようになります。
しかし、「本当に今、持たせて大丈夫?」「学力への影響は?」「使いすぎにならないかしら」といった不安もつきものです。
小学生にスマホ:所持率は年々増加中
NTTドコモモバイル社会研究所が2024年に実施した調査によると、小学4〜6年生の52%が「自分専用のスマートフォンを持っている」と回答しています。これは調査開始以来初めて半数を超えた結果で、スマホの低年齢化が確実に進んでいることを示しています。
スマホを持ち始める年齢の平均は10.4歳。ちょうど小学校高学年にあたる時期であり、多くの家庭で「持たせるかどうか」の判断が求められる時期ともいえます。
主な携帯電話会社のキッズ携帯
| サービス名 | おすすめ年齢 | 月額料金 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| Rakuten Mobile | 小学生 | 968円〜 | 12歳まで月額最大440円割引で528円 13歳以上は858円 |
| LINEMO | 小学生 | 990円〜 | データ容量無制限でLINEし放題 |
| SoftBank | 園児〜 | キッズ基本プラン 539円〜 | 子供向け機種・機能が豊富 |
| docomo | 園児〜 | キッズケータイプラン 550円〜 | 知育アプリ「dキッズ」利用可能 |
| au | 園児〜 | ジュニアケータイプラン550円〜 | 防犯ブザー安心ナビなどの見守り機能充実 |
スマホ所持によるメリットとデメリット
メリット:
- 緊急時の連絡手段になる
- 子どもの居場所が確認できる
- 学校の連絡アプリや学習アプリに対応できる
- デジタルリテラシーを早くから育てられる
デメリット:
- 使いすぎによる学力低下のリスク
- 視力や睡眠への悪影響
- SNSトラブルやネット依存の可能性
- 課金や詐欺などへの接触リスク
特に気になるのが、スマホの利用時間と学力との関係です。仙台市教育委員会と東北大学の研究では、「スマホの利用が1時間を超えると、学習時間に関係なく成績が下がる」という結果が出ています。つまり、使い方や時間管理がとても重要だということです。

海外ではどうしている?各国のスマホ対策
日本では、スマホ所持について各家庭に判断が任されている傾向がありますが、諸外国ではより明確なルールや規制がある国もあります。
フランス:
2018年から15歳未満の生徒に対し、学校内でのスマホ使用を原則禁止する法律を施行。授業中だけでなく休み時間にも使用不可とされています。
イギリス:
学校ごとにポリシーを設ける形式が多く、一部の学校ではスマホの持ち込みそのものを禁止しているところもあります。
韓国:
子どものスマホ使用時間を制限するアプリの導入を国が推進しており、特に深夜の利用制限が強化されています。
このように、海外では子どものスマホ使用に対して、家庭だけでなく社会全体で制限・サポートを行っている例が少なくありません。
小学生にスマホ:家庭でできるルール作りのコツ
スマホの利便性を活かしながら、使いすぎを防ぐには、家庭内でルールを設けることが非常に大切です。以下に、ルール作りのポイントをいくつかご紹介します。
1. スマホを持たせる「目的」を明確にする
まず、「なぜスマホを持たせるのか?」を親子で話し合いましょう。連絡手段なのか、学習用なのか、それとも娯楽のためか。目的がはっきりしていると、自然と使い方も限定されてきます。
2. 利用時間を設定する
東北大の研究でも「1日1時間以内」が理想とされています。家庭でも「○時〜○時まで」「夕食後は使わない」など、具体的な時間制限を設けましょう。
3. 寝室には持ち込まない
夜間のスマホ利用は睡眠に悪影響を及ぼします。寝る前にはスマホをリビングなどに置くルールを作りましょう。
4. アプリやサイトの制限をかける
子どもが不用意にトラブルに巻き込まれないよう、フィルタリングやペアレンタルコントロールを活用しましょう。アプリのダウンロードには保護者の承認が必要になる設定も有効です。
5. 親子で定期的に「使い方」を見直す
スマホの利用状況について、月に一度など定期的に振り返る時間を持ちましょう。「最近使いすぎていないか」「困っていることはないか」など、子どもの声に耳を傾けることが大切です。
小学生にスマホ「持たせない」選択肢
すべての子どもに、同じ時期にスマホが必要なわけではありません。通学距離や家庭環境、子どもの性格や生活習慣によって、最適なタイミングは異なります。周囲の家庭と比べすぎず、子どもの成長段階に合わせた判断ができると良いですね。
また、スマートフォンを持たせずに、代わりに「キッズ携帯」や「GPS付き見守り端末」などを利用するという選択肢もあります。必要最低限の機能だけを持たせることで、安全性と依存防止のバランスが取れる場合もあります。
まとめ:スマホを通して「親子の信頼関係」も育てよう
スマートフォンは、今や生活に欠かせないツールとなっていますが、小学生にとってはまだ扱いが難しい面もあります。持たせるかどうかは、単に「友達が持っているから」ではなく、「我が家ではどのように使わせたいか」を基準に考えることが大切です。
家庭でルールを設け、親子でスマホについて話し合うことは、単なる制限ではなく、子どもとの信頼関係を築くきっかけにもなります。「使わせる」ではなく「一緒に使い方を考える」。そんな姿勢で向き合っていけたらいいですね。