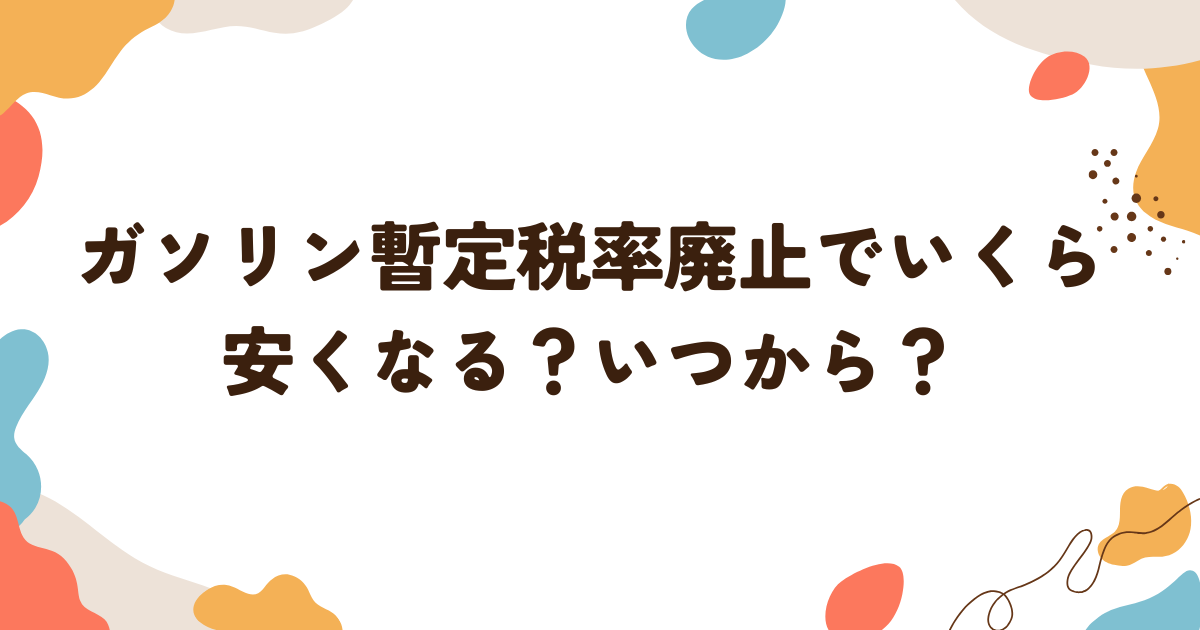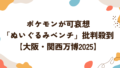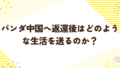2025年4月24日、自民党・公明党・日本維新の会の3党による協議が行われ、ガソリン税の「暫定税率」廃止に向けた議論が進展しました。
これまで時期を明言してこなかった自民党は、年末の税制改正議論で結論を出せば「最も早ければ2026年4月以降」に廃止が可能と説明しました。ただし、維新の会は今夏の廃止を目指しており、3党の間で意見の隔たりが残っています。協議は今後も継続される予定です。
ガソリン暫定税率とは?
ガソリン税は、揮発油税(国税)と地方揮発油税(地方税)から構成されており、通常の課税額(本則)は1リットルあたり28.7円(揮発油税24.3円、地方揮発油税4.4円)です。
これに加えて、1974年に道路整備の財源不足を補うために導入された「暫定税率」が1リットルあたり25.1円上乗せされ、合計で53.8円の税金が課されています。この暫定税率は本来一時的な措置でしたが、延長が繰り返され、現在も「当分の間税率」として存続しています。
ガソリン価格に含まれる税金の内訳
この図は、ガソリン1リットルあたりの価格構成を示しています。例えば、ガソリン価格が1リットルあたり186.5円の場合、以下のような内訳になります。
- ガソリン税(本則税率):28.7円 (揮発油税(国税):24.3円 + 地方揮発油税(地方税):4.4円)
- ガソリン税(暫定税率):25.1円
- 石油石炭税:2.04円
- 地球温暖化対策税:0.76円
- 消費税(10%):約17円
- 本体価格:約112.95円
これらを合計すると、税金部分だけで約73.6円となり、ガソリン価格の約40%を占めています。このように、ガソリン価格の大部分が税金で構成されていることがわかります。
また、石油石炭税と地球温暖化対策税を合わせて、石油税として2.8円が課税されています。これらの税金に対しても消費税が課せられており、いわゆる「二重課税」と指摘されることもあります。
給油時の金額と内訳(40L)
ガソリン価格が1リットルあたり186.5円で、40リットル給油した場合の金額と内訳は以下の通りです。
- 給油総額:7,460円
- 本体価格合計(税抜き部分):4,518円
- 税金合計(消費税含む):2,942円 (内、暫定税率1,004円)
暫定税率(25.1円/L)が廃止された場合、
給油総額(暫定税率廃止後):6,456円 (1,004円安くなる)
暫定税率廃止でガソリン価格はどう変わる?
暫定税率が廃止されると、ガソリン税は1リットルあたり28.7円となり、現在より25.1円の減税となります。例えば、40リットルを満タン給油する場合、減税後は今までに比べて約1,004円安くなります。
また、ガソリンには石油石炭税(1リットルあたり2.8円)と消費税(10%)も課されており、これらを含めると、現在のガソリン価格の約40%が税金となっています。暫定税率の廃止により、これらの税負担も軽減されることが期待されます。
家計や企業への影響
暫定税率の廃止は、家計や企業にとって大きなメリットがあります。特に、日常的に車を使用する家庭や運送業界では、燃料費の削減が期待されます。例えば、年間で約10万円のガソリン代を支払っている家庭では、数千円から1万円程度の節約効果が見込まれます。
また、ガソリン価格の低下は輸送コストの削減につながり、商品価格への転嫁が抑えられることで、物価全体の上昇を和らげる効果も期待されています。これにより、消費者の購買意欲が高まり、地域経済や景気の回復を後押しする可能性があります。
暫定税率廃止に伴う課題
一方で、暫定税率の廃止にはいくつかの課題も存在します。まず、税収の減少が挙げられます。年間約1.5兆円の税収減が見込まれており、地方自治体の財政にも影響を与える可能性があります。これに対して、維新の会は税収の上振れや予算の組み替えによる補填などの措置で対応可能と主張しています。
また、ガソリンスタンドなどの在庫分に対して税額分を還付する手続きが発生する可能性があり、行政手続きの効率化が求められます。さらに、ガソリン税の引き下げがCO2排出量の増加につながることを懸念する声もあり、環境政策との整合性が問われています。
国民の声と今後の展望
ガソリン暫定税率の廃止に対して、一般の人々からはさまざまな意見が寄せられています。
「ガソリン価格の変動は運輸業に大きな影響を与えるため、政府は現場を見て真剣に対応すべきだ」という声や、「ガソリン価格が高騰するたびに話題になる『暫定税率』について、政府が廃止を検討しているのは良いことだが、将来的な維持管理の負担を誰が、どのように担っていくのか、単なる『減税』だけでなく、その先の仕組みづくりまで含めた議論が求められる」といった意見があります。
今後、政府と関係者は、税収の減少や環境政策との整合性などの課題に対処しつつ、具体的な実施時期や方法について協議を進めていく必要があります。国民生活や経済活動に与える影響を慎重に考慮し、持続可能な税制