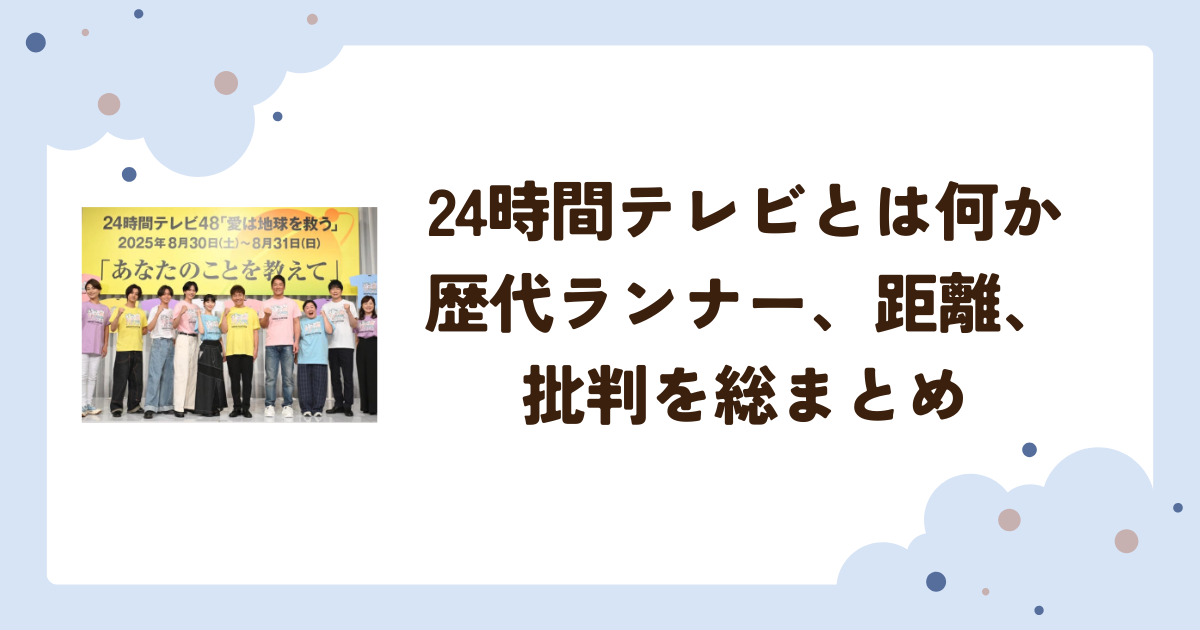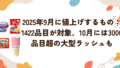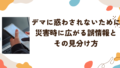「24時間テレビ 愛は地球を救う」は、日本テレビ系列で1978年に放送が始まったチャリティー番組です。毎年8月下旬の週末に全国で放送され、視聴者の募金をもとに福祉・環境保護・災害復興などに役立てられてきました。番組を象徴する企画として「チャリティーマラソン」があり、著名人が長距離を走破する姿を通じて、視聴者に「勇気」や「挑戦」のメッセージを届けてきました。
一方で、長年続くこの番組には批判や疑問の声も少なくありません。本記事では、番組の概要やランナーの歴史、マラソン距離の特徴、放送時期の理由、さらには批判点まで、幅広く整理してご紹介します。
24時間テレビとは——番組の成り立ちと趣旨
日本テレビ系で毎年8月下旬の土曜〜日曜に生放送される長時間特番「24時間テレビ 愛は地球を救う」は、1978年にスタートしたチャリティー番組です。
番組自体は日本テレビの制作ですが、イベント全体は日本テレビ系列局(NNN/NNS)に沖縄テレビを加えた計31社で共同開催されます。
目的は、福祉の実情や支援の必要性を広く伝え、寄せられた寄付金を「福祉」「環境保護活動」「災害復興」の分野へ役立てることです。寄付金は、福祉車両(訪問入浴車・スロープ付き車など)の贈呈、障害者スポーツ支援、難病患者支援、災害被災地支援等に充当され、その使途内訳はチャリティー委員会の公式サイトで公開されています。
日本テレビ:24時間テレビ公式サイト
公益社団法人24時間テレビチャリティー委員会
なぜ「夏」に放送されるのか?
① 日本テレビの開局記念と時期のご縁
「24時間テレビ 愛は地球を救う」は、1978年に日本テレビ開局25周年の記念特番としてスタートしました。日本テレビは8月28日に開局しており、それに近いタイミングでの放送が自然な流れだったと言われています。
② “夏休みの終わり”はチャリティー行動の好機
夏休み終了間近の時期は、子どもたちや親子が番組を見ながら募金しやすいという背景もあります。特に「夏休みの宿題の追い込みを避けつつ」「夜更かししても影響が少ない」などの条件が整いやすいため、8月中旬〜下旬に放送するのが理にかなっているという見方もあります。
③ イベントが少ない時期の目玉化
7月の花火大会など夏の目玉イベントがひと段落した時期である8月下旬は、大きな話題になるイベントが少なめ。そのため、テレビ番組としてこの時期に大規模チャリティ特番を打ち出すことで、注目を集めやすいという狙いもあったと考えられます。
チャリティーマラソン(ランナー企画)の位置づけ
番組の象徴的企画が「チャリティーマラソン(/駅伝・トライアスロン等で実施)」です。1992年に間寛平さんが100kmマラソンに挑戦して以降、社会的関心の高いタレントやアスリートらが走者を務めてきました。基本は「番組の進行と連動してゴールをフィナーレに重ねる演出」を軸に、単独走、複数人の駅伝形式、周回コースを用いた募金連動型など、時代や状況に応じてスタイルを変えてきたのが特徴です。2018年は“スイム→バイク→ラン”のトライアスロン形式で合計161.95kmという例外的な年でもありました。
距離設定の特徴
チャリティーマラソンの距離は、おおむね 100km前後 が基準とされてきました。
1992年に間寛平さんが挑戦した100kmマラソンをきっかけに、この「100km」という数字が番組企画の象徴的な目安になったのです。
ただし、走者の年齢や体力、さらに番組のテーマ性や演出意図によって、実際の距離は毎年異なります。
例えば、2010年のはるな愛さんは85km、2011年の徳光和夫さんは63.2kmと短めの設定になった一方、2009年のイモトアヤコさんは126.585kmという長距離に挑戦しました。さらに特例として、2018年のみやぞんさんは「水泳・自転車・ラン」を組み合わせたトライアスロン形式で合計161.95kmを走破。2020年は新型コロナ禍の特例として周回コースを複数人で走り、合計236kmを達成するなど、通常の100km枠を超える年もありました。
また、近年は企画性を重視し、2023年は「おじさん」に語呂合わせした102.3km、2024年は81.97kmと、独自の距離設定が話題を集めています。このように、100kmを基準にしながらも毎年の走者や社会状況に合わせて柔軟に変化する点が、24時間テレビのマラソン企画の大きな特徴です。
歴代ランナー一覧(主要年・形式・距離のポイント)
1990年代
- 1992年 間 寛平(初の100kmマラソンとして定着の起点)
- 1993年〜1998年 毎年タレントが単独で挑戦(100km前後)
- 1999年 にしきのあきら ほか(1990年代終盤にかけても単独走が基本)
2000年代
- 2009年 イモトアヤコ(126.585km)——長距離挑戦の代表例。
2010年代
- 2010年 はるな愛(85km)。
- 2011年 徳光和夫(63.2km)。
- 2012年 佐々木健介・北斗晶ファミリー(リレー/合計120km)。
- 2013年 大島美幸(森三中)(88km)。
- 2014年 城島 茂(TOKIO)(101km)。
- 2015年 DAIGO(100km)。
- 2016年 林家たい平(100.5km)。
- 2017年 ブルゾンちえみ(90km)※走者は当日発表。
- 2018年 みやぞん(トライアスロン形式:計161.95km)。
- 2019年 水卜麻美/いとうあさこ/近藤春菜/よしこ(4人駅伝・148.78km)。
2020年代
- 2020年 高橋尚子ら6人(周回・募金連動型/合計236km)。
- 2021年 岸優太・水谷隼ら10組(駅伝/合計100km)。
- 2022年 兼近大樹(EXIT)(100km)。
- 2023年 ヒロミ(102.3km)。
- 2024年 やす子(81.97km)。
- 2025年 横山 裕(SUPER EIGHT)(第48回ランナー/詳細距離は放送時発表)。
企画の変遷と見どころ
1)単独走の時代から「多様な形式」へ
1990年代〜2010年代前半は“100km前後の単独走”が定番でしたが、2012年には家族リレー、2019年には4人の駅伝、2020年は周回+募金連動という複数人・周回スタイルへと拡張。2021年はトップアスリートが多数参加する100km駅伝、2022年には単独走へ再回帰、2023年は語呂合わせの距離設定と、演出の幅が広がりました。
2)2018年の特例:トライアスロン
みやぞんさんが挑んだ“水泳→自転車→ラン”の合計161.95kmは、番組史でも特異点。酷暑の中での挑戦・完走は、近年の象徴的エピソードとして語り継がれています。
3)「番組フィナーレにゴール」を重視する演出
チャリティーマラソンはスポーツ競技の記録性よりも、番組全体の物語的クライマックスとしての機能が強く、フィナーレ直前のゴールを想定した進行が通例です。視聴者の関心を引きつけつつ、寄付や社会課題への関心喚起へつなげるという広報・啓発の役割も担っています。
2024年のトピック:やす子の81.97km
2024年はやす子さんがランナーに就任。スタジアムのトラック周回(約30km)と公道区間を組み合わせ、計81.97kmを走破しました。距離設定は100km標準からは短めで、年齢・体力や演出設計に応じた調整が行われた年でした。
2025年の注目:横山 裕(SUPER EIGHT)
第48回(2025年)は、横山 裕さん(SUPER EIGHT)がランナーに決定。放送は8月30日(土)〜31日(日)で、走行距離や詳細コースは例年通り番組の演出に合わせて発表される見込みです。
24時間テレビの寄付金はどこへ?
直近の使途報告では、福祉車両(リフト付きバス、スロープ付き自動車、訪問入浴車、電動車いす等)の贈呈、障害者スポーツ支援、子ども食堂支援、環境保護、災害復興など、項目ごとの支出額が公開されています。チャリティー委員会のサイトでは、年度別の支援実績や支出内訳が確認できます。
批判と疑問の声
長い歴史の中で、24時間テレビには数々の批判も寄せられてきました。代表的なものを整理します。
1. 「感動ポルノ」との批判
障がい者や難病患者の挑戦を感動的に描く一方で、「障がいを感動の材料として利用している」という指摘があります。NHKの「バリバラ」が対抗的に「感動を疑え」と特集を組んだことも話題となりました。
2. 高額な出演料
チャリティーを掲げつつ、出演者には数百万円〜数千万円規模のギャラが支払われると報じられており、「偽善ではないか」との批判が絶えません。
3. 募金の透明性
集められた募金がどのように使われているのか不透明だとの懸念が繰り返し指摘されてきました。さらに系列局幹部による寄付金着服事件は、番組への信頼を大きく揺るがせました。
4. マンネリ化・視聴率偏重
毎年同じような構成に「新鮮味がない」という声があります。感動演出やマラソンに依存する構成が、番組の存在意義を疑問視させています。
5. マラソンの安全面
酷暑の中での長距離マラソンは出演者に過度な負担を強いるのではないかという懸念もあります。特に高齢者ランナーの場合は、安全性に強い批判が出ました。
6. 募金・視聴率の低迷
テレビ離れの影響や批判の広がりによって、募金額や視聴率がかつてほど伸びなくなっている現状もあります。
おわりに
24時間テレビは、日本の夏を象徴する恒例イベントとして定着しています。歴代ランナーの挑戦や、視聴者の善意による募金活動は、多くの人々に希望や感動を与えてきました。その一方で、出演料や演出方法、募金の透明性といった課題も浮き彫りになり、番組のあり方自体が問われ続けています。
今後は「本当の意味でのチャリティー」として、透明性や多様性をどう確保していくのかが大きな課題です。愛と勇気を伝える番組としての伝統を守りながらも、社会からの批判に誠実に向き合うことで、さらに意義ある存在へと進化していくことが期待されています。