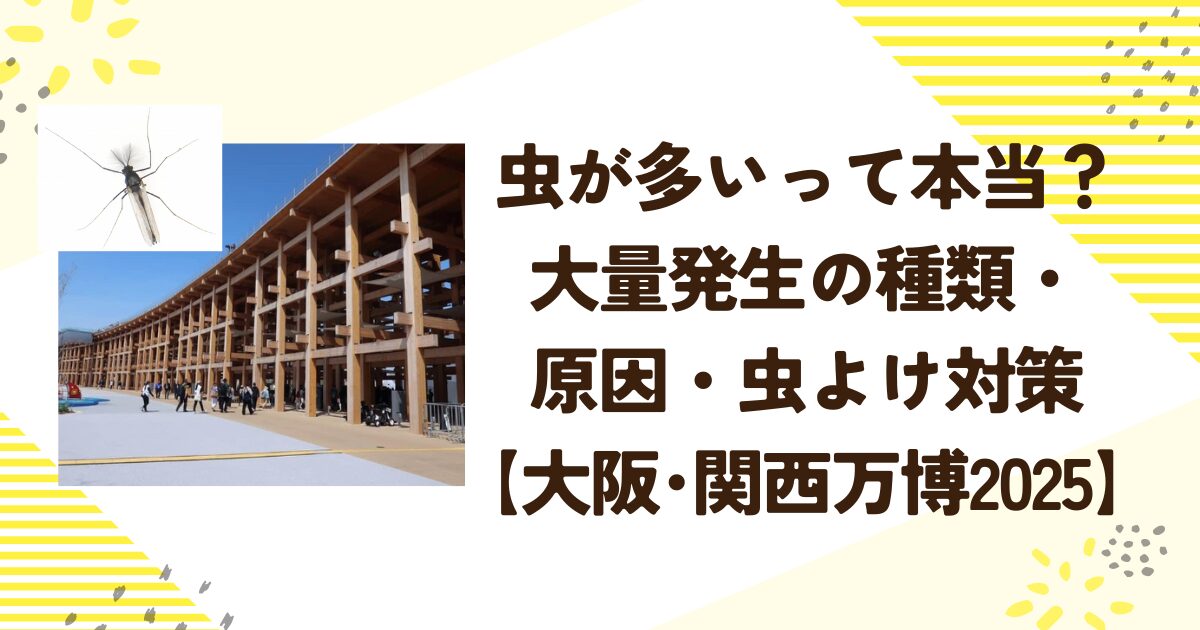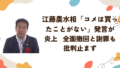2025年春に開幕した大阪・関西万博ですが、SNSでは「虫が多すぎる」「黒い虫が柱や展示物にびっしり付いていて不快」といった投稿が広がっています。特に大屋根リングやウォータープラザ周辺で虫が大量に発生しているという報告が相次いでおり、「これから暑くなってさらに虫が増えるのでは?」と不安に思う来場者も少なくありません。
本記事では、実際に万博会場で発生している虫の種類、なぜ虫が多いのかという原因、万博協会による虫対策、そして来場者ができる虫よけ対策のポイントまで、詳しくまとめました。
万博会場で虫が多いのはなぜ?大量発生の原因とは
湿気・水たまり・照明が「ユスリカ」の好条件
万博会場で特に問題視されている虫は、「ユスリカ」という蚊に似た昆虫です。見た目は小さく細長く、蚊のように見えますが、人を刺したり血を吸ったりすることはありません。しかし、大量発生することで見た目の不快感を与えたり、死骸がアレルギーの原因となることもあり、対策が急がれています。
ユスリカは、次のような環境で発生しやすいとされています:
- 水たまりや湿地の近く(卵がふ化しやすい)
- 照明が多い場所(光に集まりやすい)
- 気温が高く、風通しが悪い環境
大阪万博の会場である「夢洲(ゆめしま)」は、もともと埋立地で、海に囲まれた湿気の多い地域です。ウォータープラザの噴水周辺や、大型構造物である大屋根リングの柱・天井には、昼夜問わず多くのユスリカが集まっている様子が確認されています。
特に夜間は照明の光に引き寄せられて虫が密集しやすく、SNSでも「柱が真っ黒になるほど虫がついていた」との投稿も。
ユスリカとはどんな虫?
大量発生しているのは「ユスリカ」という種類の虫で、特に「シオユスリカ」という河口などの汽水域に生息するタイプが確認されています。日本全国の河口や潮だまりでよく見られる種類です。
見た目は蚊にそっくりですが、刺したり病気を媒介することはありません。赤虫(釣り餌や観賞魚のエサ)として知られるのがこのユスリカの幼虫です。幼虫は水中で水底の汚泥や藻類などの有機物を食べて成長します。
また、ユスリカの生中は口や消化器が退化しており、食事はしません。生殖のために成虫になり、交尾や産卵を行うのみです。わずか1日~2日程度しか生きないため、交尾や産卵を済ませるとすぐに死んでしまいます。
万博会場では水が滞留しやすく天敵の魚も少ないことから、ふ化と大量発生を招いていると専門家は指摘しています。シオユスリカは真夏以外にも断続的に発生すると考えられます。さらに、夏になり気温が上がると別の種類のユスリカも発生する可能性もあります。
蚊の種類は世界で3500種類以上、日本では約100種類の蚊がいます。その中でも、吸血するのは20種類で、代表的なものは「ヒトスジシマカ(ヤブカ)」「アカイエカ」「チカイエカ」です。
万博会場で発生しているのは吸血しない「ユスリカ」ですが、死骸が粉じん化して空中を舞うことや、飲食物への混入、アレルギーの誘発といった二次被害の懸念もあるため、今後の気温上昇に伴いさらに虫の種類が増える可能性も含め、引き続き慎重な対応と継続的な虫対策が求められます。

万博協会も認めた虫の大量発生と対策状況
会場全体に広がるユスリカ問題
2025年5月20日の記者会見で、日本国際博覧会協会の高科淳副事務総長は、「会場に虫がいることは認識している」「主にウォータープラザ、大屋根リング、パビリオン周辺に多く発生している」と明らかにしました。
当初は明確な対策が講じられていなかったものの、開幕後に多くの来場者からの不満が寄せられたことで、以下のような虫よけ対策が実施されています。
協会が実施している主な虫対策
| 対策方法 | 内容 |
|---|---|
| 発泡剤の散布 | 卵がふ化するのを防ぐため、雨後の水たまりや植栽に薬剤(発泡剤)を散布 |
| 殺虫剤の配布 | 店舗やパビリオン内に虫が侵入しないよう、殺虫剤を配置・定期的に散布 |
| 殺虫ライトの設置 | 光に集まる虫の習性を利用し、ライトで誘引・捕獲 |
| 専門業者への相談 | 今後さらに対策を強化するため、害虫駆除の専門業者と連携を図る方針を発表 |
万博協会は、「来場者の不快感を最小限にするため、あらゆる手段を講じる」とし、今後も継続して対応していく姿勢を見せています。
万博会場で見かける虫の種類は?
多く見られるのはユスリカですが、それ以外にも以下のような虫の種類が会場では目撃されています。
- ユスリカ:主犯格。人は刺さないが大量発生しやすい。
- ガガンボ:大きな蚊のように見えるが無害。
- 蛾や羽虫類:夜間の照明に集まりやすい。
- ハエの仲間:飲食エリアなどで出没することも。
- 蚊(本物):夏場には人を刺す蚊も増加の恐れあり。
来場者ができる虫よけ対策【現地での実践法】
万博を快適に楽しむための「虫対策5選」
虫の多い万博会場でも、事前に対策をしておけばストレスを減らすことができます。以下は、実際に会場を訪れる際におすすめの虫よけ対策グッズ&ポイントです。
- 虫よけスプレーは必携!
- ディート配合のものや、天然由来成分のスプレーも選択可。
- こまめに塗り直すのが効果的。
- 長袖・長ズボンで肌の露出を減らす
- 蚊などに刺されにくくなる。
- 薄手のUVカット素材なら夏でも快適。
- 明るすぎない服を着る
- 虫は黒や青など濃い色に引き寄せられやすい傾向がある。
- 携帯型虫よけアイテムの活用
- ウェアラブル虫よけや、電池式の虫除けリングなども便利。
- 飲食時は特に注意
- 食べかすや甘い匂いが虫を引き寄せる原因に。
- 食べ終わったらすぐに片付けよう。
夏本番は虫がさらに増える?今後への注意点
ユスリカを含む虫は、気温が上昇するとさらに活動が活発になる傾向があります。梅雨や夏の猛暑に向けて、虫の数が増加する可能性は十分にあり得るとされています。大阪府の環境衛生課も、「水が滞留している場所ではユスリカの繁殖が加速する恐れがある」と注意を呼びかけています。
また、今後の対応次第では、別の虫(蚊やハエなど)も含めて広範囲な対策が必要になるかもしれません。
まとめ|虫が多い万博でも、対策すれば楽しめる!
大阪・関西万博では、夢洲という湿気の多い土地柄と気温の上昇、照明設備などが重なり、虫が多い状況が続いています。特に大屋根リングやウォータープラザ付近では、ユスリカが大量発生していることが報告されています。
とはいえ、主催者側の対策も本格化してきており、来場者自身がしっかりと虫よけ対策を行えば、万博を快適に楽しむことは十分に可能です。