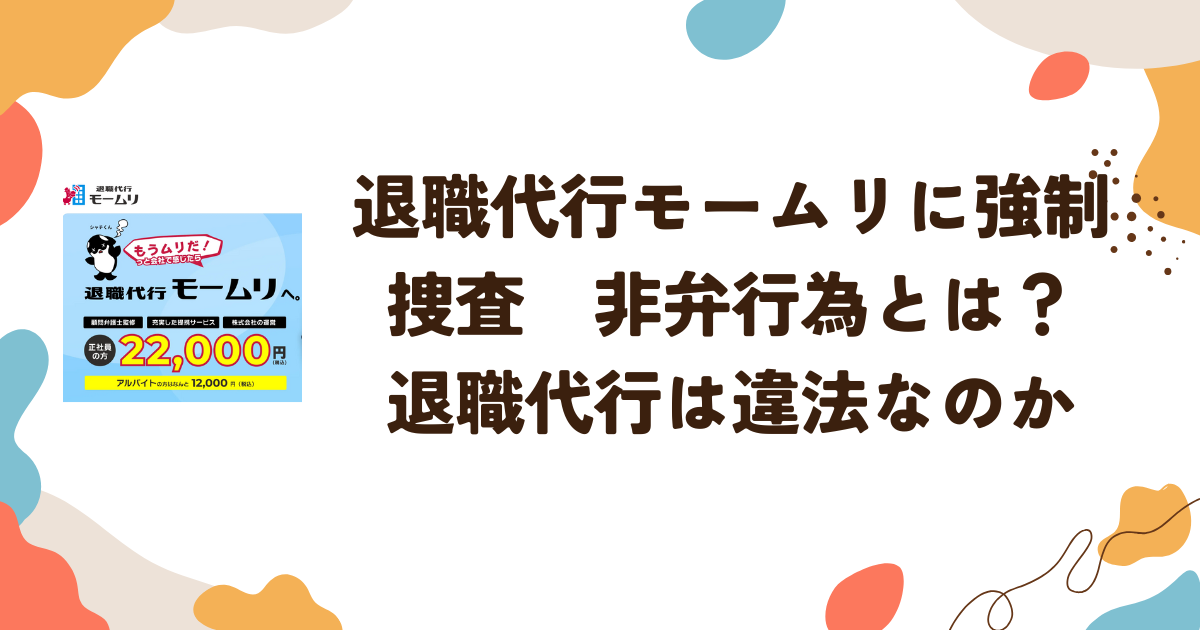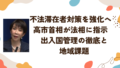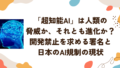2025年10月22日、退職代行サービス「モームリ」を運営する株式会社アルバトロス(東京都品川区)が、弁護士法違反(非弁行為)の疑いで警視庁の強制捜査を受けました。
複数の報道によると、同社は退職希望者と企業の間に入り、弁護士に違法に業務をあっせんし紹介料を受け取った疑いが持たれています。
退職代行「モームリ」に強制捜査 東京弁護士会も声明を発表
同日、東京弁護士会はこの件に関する声明を発表しました。モームリという固有名詞には触れていませんが、「退職代行サービスをめぐる非弁行為の可能性」について以前から警鐘を鳴らしており、今後の動向を注視するとしています。
声明の中では、過去に発信したブログ記事「退職代行サービスと弁護士法違反」を再度紹介し、非弁行為の定義や注意点をあらためて説明しました。
退職代行とは?近年急増する「第三者に任せる退職」
退職代行とは、本人の代わりに退職の意思を会社へ伝えるサービスのことです。
利用者が直接上司や人事に「辞めたい」と言わずに済むため、精神的な負担を軽減できるとして人気が広がりました。
背景には、パワハラや長時間労働などによって「退職を切り出せない」労働環境の問題があります。特に若年層や女性の利用が増えており、SNS上でも「使ってよかった」「人生が変わった」といった口コミが拡散しています。
退職代行サービスには大きく分けて2種類があります。
- 弁護士が運営する退職代行サービス
→ 法律の専門家が対応するため、金銭請求などの交渉が可能。 - 民間企業が運営する退職代行サービス
→ 弁護士資格を持たないため、法律相談や交渉行為はできません。
問題となるのは、後者の「民間業者」が法的な交渉行為に踏み込むケースです。これが「非弁行為」にあたる可能性があります。
非弁行為とは?どこから違法になるのか
「非弁行為」とは、弁護士資格を持たない者が、他人の法律問題を業として扱う行為を指します。弁護士法第72条で明確に禁止されており、違反した場合は刑事罰の対象になります。
退職代行サービスで非弁行為に該当するのは、例えば次のようなケースです。
- 未払い残業代の支払いを会社に求めるなど、法律的な交渉を行う
- 労働契約の解約条件について法的助言を行う
- 弁護士ではないにもかかわらず、「法的に問題ない」などの判断を伝える
東京弁護士会のブログでは、実際に「退職代行業者が残業代の支払いを交渉した結果、支払いが行われた」ケースを例に挙げています。こうした行為は本人の権利を守るどころか、誤った計算や不利な条件での合意につながるリスクもあると指摘しています。
「モームリ」報道を受け、他の業者も声明
今回の報道を受け、他の退職代行サービスも次々に声明を発表しました。
「ガーディアン」を運営するTRK(東京都新宿区)は、「当社は法令に基づいた完全合法の退職代行サービスを提供している」とプレスリリースを発表。
また、「EXIT(イグジット)」を運営するEXIT社の新野俊幸社長も、「弊社は退職代行のパイオニアとして弁護士法を順守している」とX(旧Twitter)で投稿しました。
このように、「非弁行為ではないこと」を強調する動きが相次いでいます。
退職代行サービスの信頼性が揺らぐ中で、合法的な運営をアピールすることが重要になっているのです。
退職代行の落とし穴 「即日退職」や「代行交渉」に注意
退職代行の広告では、「即日退職できます」「すべて丸投げOK」といったキャッチコピーをよく見かけます。
しかし、これらの表現には法的な限界がある点に注意が必要です。
- 労働契約の内容や就業規則によっては、即日退職が不可能な場合もある
- 有給休暇の扱い、退職金、未払い賃金などは法律知識が必要
- 弁護士資格がない業者が法的交渉を行うと違法になる可能性
また、「弁護士監修」と書かれたサービスでも、実際に弁護士が個別の案件に関与していなければ、監修だけでは法的な交渉はできません。利用者側もサービス内容をよく確認することが大切です。
まとめ:退職代行は違法ではないが、使い方には注意を
退職代行サービス自体は違法ではありません。
しかし、弁護士資格を持たない業者が法律交渉を行えば、「非弁行為」となり違法です。
利用する際は、以下の点に注意してください。
- 弁護士が運営・監修しているかを確認する
- 「残業代請求」など交渉を代行しないかチェックする
- 口コミや運営会社の実態を調べる
- 料金体系が明確かどうかを確認する
退職代行は、精神的負担を減らし、スムーズに退職できる便利な手段です。
しかしその裏には、法的リスクやトラブルの可能性も潜んでいます。
信頼できる業者を見極め、慎重に利用することが大切です。