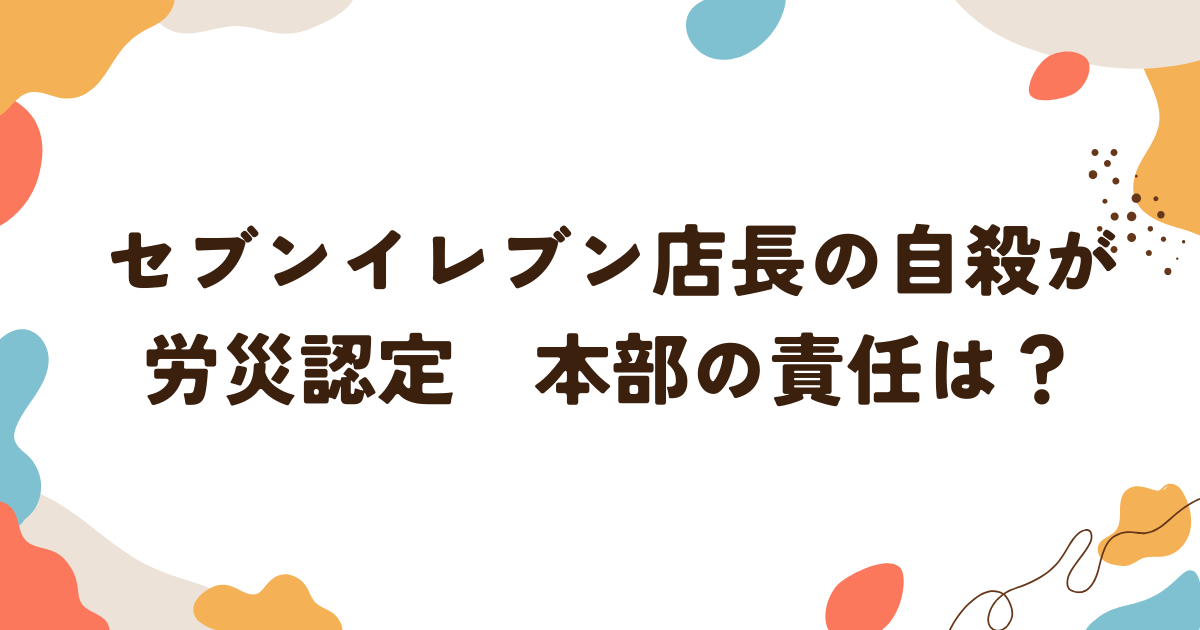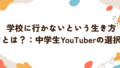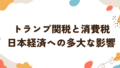2022年、大分県内のセブンイレブン店長を務めていた38歳の男性が、自ら命を絶つという痛ましい出来事がありました。労働基準監督署は、6カ月間一日も休みのない連続勤務が原因で発症した重度のうつ病により、自殺に至ったと認定。労災と判断しました。
この事例は、コンビニ業界における過酷な労働環境と、フランチャイズ契約の構造的な問題を浮き彫りにしています。
コンビニ店長の過重労働が招いた悲劇
セブンイレブンの店長の業務は、単なるマネジメントにとどまらず、シフト管理や在庫・売上の管理、人員不足への対応など、さまざまな仕事をこなさなければなりません。特に人手が足りない店舗では、店長が自ら長時間働かざるを得ないこともあります。そのため、過重労働が常態化しているケースも少なくありません。
今回のケースでは、店長が6カ月間一度も休むことなく働き続け、最終的に自殺に追い込まれたとされています。これにより、労働環境の異常さが問題視されています。
過労死・過労自殺の労災認定はなぜ難しい?
日本では、過労死や過労自殺が労災として認定されるまでに高いハードルがあります。労働の過重性や精神的負担を遺族が証明しなければならず、企業側が非協力的な場合、申請が難航することもあります。
過去にも、東京都内のコンビニ店長が月120時間を超える時間外労働を半年続けた末に自殺し、東京高裁が労災と認定した事例があります。今回の大分県のケースも、それに続くものといえるでしょう。
フランチャイズ本部の責任と社会的課題
セブン-イレブン本部は、労働環境に関する問題について「フランチャイズ個店の運営に関わる内容であり、本部として回答する立場にない」との立場を示しています。
しかし、実際には本部からの指導や運営マニュアル、売上ノルマの圧力などを考えると、完全に無関係とはいえません。本部が加盟店に与える影響は大きいため、その点を考慮すべきでしょう。
労働環境の改善には、本部と加盟店の明確な責任分担と、労務管理体制の見直しが必要です。

東大阪のセブンイレブン元オーナー訴訟
また、東大阪市の「セブンイレブン東大阪南上小阪店」の元オーナーである松本実敏さんが、本部との契約解除をめぐって訴訟を起こしていた件も注目されています。
この訴訟では、松本氏が契約解除は不当であると主張しました。しかし、2023年に全面敗訴となり、店舗の明け渡しと損害賠償の支払いを命じられました。このケースも、フランチャイズ経営者と本部との力関係や契約上の問題点を浮き彫りにしています。
フランチャイズ経営の構造的課題と今後の改善策
今回のような事例が繰り返されないためには、以下のような改善策が必要です。
- 店長を含む労働者の健康管理の徹底
- 労働時間の適正な管理と記録の義務化
- 労災認定制度の見直しと申請手続きの簡素化
- フランチャイズ本部と加盟店の責任と権限の明確化
- 適正な人員配置やサポート体制の強化
まとめ:業界全体での労働環境改善を
コンビニ店長の自殺が労災と認定された今回の事例は、個別の問題ではなく、業界全体が抱える構造的な課題を象徴しています。フランチャイズ契約のもとで働く店長たちは、経営者としての責任と労働者としての負担を同時に背負っており、適切な保護が必要です。
今後、コンビニ業界全体が労働者の命と健康を守る体制へと転換することが求められています。