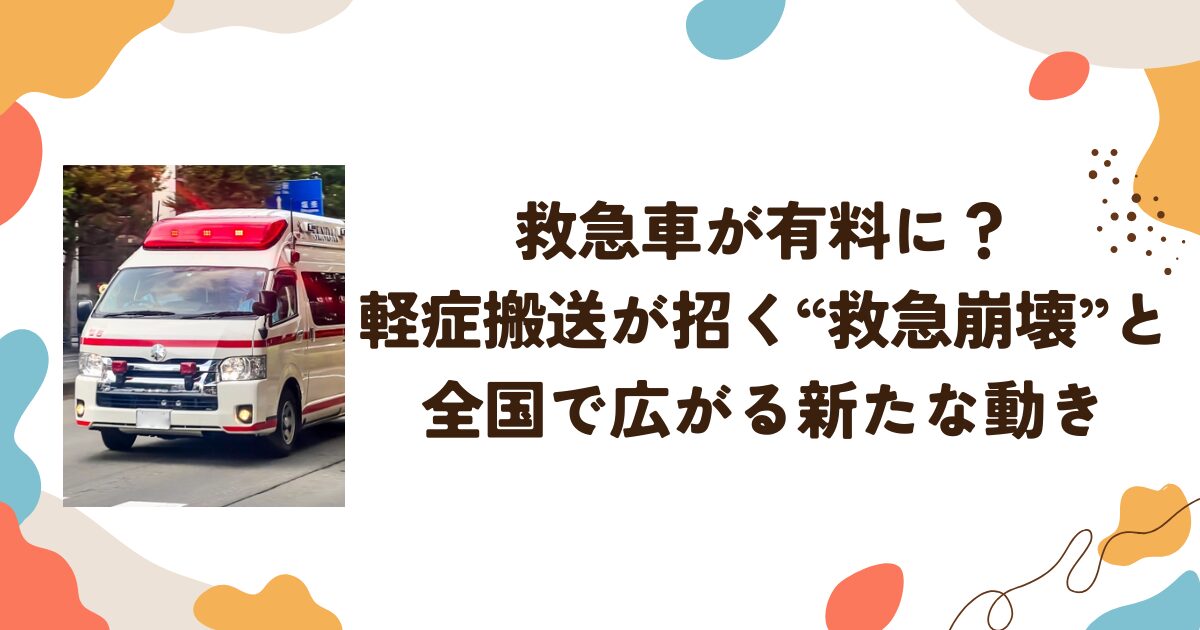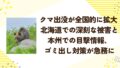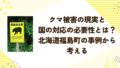今、日本各地で「軽症なのに救急車を呼ぶ人が多すぎる」ことにより、救急搬送の現場が逼迫し、“救急車が有料になる時代”が現実味を帯びてきています。
この記事では、救急車の有料化が議論される背景や、すでに始まっている地方自治体での取り組み、そして海外との比較を通じて、これから私たちが何を意識すべきかをわかりやすく解説します。
救急車有料化の背景:「軽症搬送」が全体の約半数
2022年度の総務省の統計によると、全国で723万件を超える救急出動がありました。そのうち、47.3%が軽症者。つまり、救急車で搬送されたにもかかわらず、外来診療だけで済んだ人たちです。
これはつまり、本来救急車を必要とする重篤な患者が搬送されにくくなる原因を、半数近くが作っていることになります。

救急車の出動コストは1回7万円以上?
日本では救急車の利用は無料ですが、それは税金でまかなわれているからにすぎません。
過去の東京都の発表では、救急車1回の出動に約4万5000円(2002年)かかっていました。現在では燃料費や人件費の上昇もあり、7万円〜8万円のコストがかかっているとも言われています。
この費用を考えると、軽症で救急車を使うことがいかに大きな社会的損失であるかがわかります。
「タクシー代わり」に119番?実際に起きた事例
・夜中に50回も119番通報した高齢女性
・「眠くなったから電話はもういいわ」と自分で通話を終了
信じがたい話ですが、これは東京消防庁に実際に記録された事例です。このように、話し相手が欲しい・通報が癖になっているといった、緊急性とは無関係な119番通報も、救急の現場を混乱させています。
三重県松阪市では「軽症搬送7700円徴収」がスタート
こうした事態に対応すべく、2024年6月、三重県松阪市が全国初の有料化制度を導入しました。
- 軽症と判断された救急搬送者に7700円の選定療養費を請求
- 厚労省の医療制度と同様、「紹介状なしの大病院受診」と同じ料金体系
この取り組みの効果は顕著で、導入直後の出動件数は大幅に減少。**「なんとなく不安だから」「病院が混んでそうだから」**といった理由で救急車を呼ぶ行動に、ブレーキがかかった形です。
同様の取り組みは、茨城県の一部医療機関でも2024年12月から始まる予定で、今後全国に広がる可能性もあります。

海外では救急車は“有料”が当たり前
日本ではまだ「救急車は無料」が常識ですが、海外では救急車が有料なのが当たり前です。
| 国・地域 | 費用の目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| アメリカ | 10万円〜20万円超 | 保険が効かないと高額に |
| ドイツ | 5万〜10万円程度 | 自治体によって異なる |
| フランス | 民間救急3万〜4万円 | 緊急度で公費か自費が分かれる |
つまり、日本のように無料で救急車が来てくれる国は非常に珍しく、世界的に見ても極めて優遇された制度であることがわかります。
有料化には賛否も──「命の選別にならないか」という声
もちろん、救急車の有料化には慎重な検討も必要です。
メリット
- 軽症者の無用な利用を防げる
- 本当に必要な人にリソースを集中できる
- 税負担の抑制につながる
デメリット
- 経済的な理由で救急車を呼べなくなる恐れ
- 高齢者や独居者が「我慢」して重症化する可能性
- 判断基準が曖昧だとトラブルの原因に
そのため、所得による免除・減額制度の整備や、高齢者向けの相談窓口の拡充など、制度設計が極めて重要になります。
「#7119」「#8000」も活用を──通報の前にできること
救急車を呼ぶべきか迷ったら、#7119(大人)や #8000(子ども)に電話してみましょう。
- 医師や看護師による24時間相談
- 緊急性の有無を専門的に判断
- 不要な救急要請を防ぐ第一歩
多くの人がこの番号を知らずに通報してしまっている現実があります。まずは情報を知り、冷静に判断することが、社会全体の安心・安全につながります。
救急車は「無料で使える権利」ではなく「命を守る最後の砦」
日本の救急医療は、世界でも類を見ないほど恵まれた仕組みです。しかしその“無料”の仕組みが、軽症搬送の増加によって崩壊の危機に直面しています。
今後、救急車が有料になる動きは、確実に広がっていくと考えられます。
それを避けるためにも、私たち一人ひとりが「救急車の正しい使い方」を学び、必要なときに必要な人のためにリソースを残す──そんな意識が求められているのです。