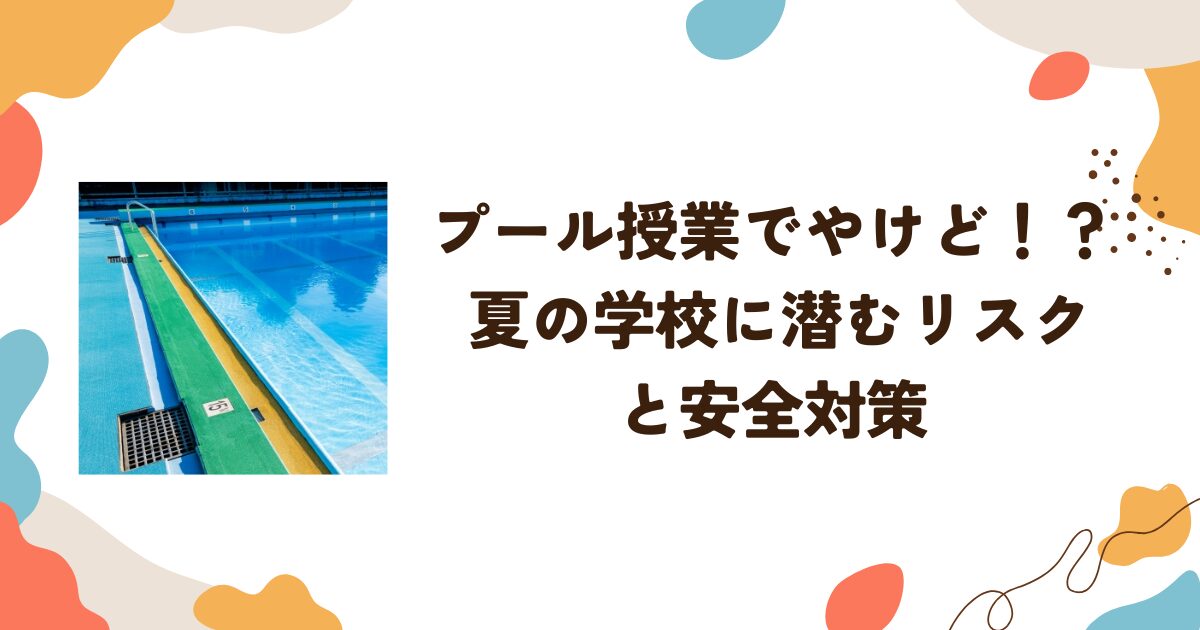夏の恒例ともいえる学校のプール授業。しかし2025年の今年、その“当たり前”に大きな変化が起きています。
「プールの授業で児童がやけど」「見学中に熱中症」――信じられないようなニュースが全国で相次いでいるのです。
一方で、安全と学びを両立させる新たな試みとして、民間スイミングスクールへの授業委託も本格的に始まっています。
本記事では、プール授業をめぐる問題と対応策について、わかりやすく解説します。
プール授業でやけど!? 滋賀の小学校で児童62人が受傷
2025年7月9日、滋賀県守山市の市立河西小学校で行われたプールの授業後、6年生の児童62人が尻に赤みの症状を示し、病院を受診しました。
守山市教育委員会によると、プール授業終了後の着替えの際、まず5人の児童が尻に赤みがあることに気づき、教員が他の児童の状態を確認したところ、男子38人・女子24人、合計62人に同様の症状が見られたとのことです。
この日のプール授業には、6年生129人が参加。授業は午前10時30分から正午ごろまで行われており、児童たちはプールに入る順番を待つ際に、プールサイドに座っていたとされます。
学校側は、暑さ対策としてプールサイドにマットを敷いたり、水を撒いたりする対応を取っていたとしていますが、学校が計測した当時の気温は35.9℃に達していました。
児童の症状はいずれも軽傷とされ、守山市教育委員会は今後、授業前の十分な散水や温度管理の徹底など、再発防止策を講じる方針を明らかにしています。
北九州では手に湿疹・しびれ…マットの圧迫が原因?
さらに6月には、福岡県北九州市の高蔵小学校で、水泳授業中に児童25人が手の湿疹やしびれを訴え、救急搬送されるという事態も発生しました。
原因は、プールサイドのプラスチック製マットに手をつくことによる圧迫痕であると結論づけられました。
市教委や医師の検証によって、アレルギーや水質の異常ではないことが確認されています。
この2つの事例から明らかなのは、炎天下のプールでは“水の中”だけでなく、“周囲環境”も重大なリスクを孕んでいるということです。

プールでも熱中症になる! 環境省も注意喚起
一般的に「プール=涼しい」「水に入っている=大丈夫」と思われがちですが、それは大きな誤解です。
環境省が公開している『熱中症環境保健マニュアル2022』では、屋外プールでも熱中症の危険があると明記されています。
特にコンクリートに囲まれた学校のプールは照り返しが強く、さらに日陰が少ないという構造的問題も。肌の露出が多く、直射日光を遮るものがない状態で、体温は想像以上に上昇します。
加えて、授業中は安全面から水分補給が制限されているケースも多く、脱水症状を起こすリスクも高まっています。
「暑さ指数」って何? 原則運動禁止レベルが続出中
日本スポーツ協会が熱中症予防のために示している運動基準では、
- 気温35℃以上
- 暑さ指数(WBGT)31℃以上
この条件を満たすと、運動は原則中止とされています。
この「暑さ指数(WBGT)」とは、気温・湿度・輻射熱(地面からの熱など)を総合的に反映した指標で、単純な気温以上に人間の熱ストレスを的確に示すとされています。
7月に入り、連日この「危険レベル」の暑さ指数を記録しており、プール授業が中止になる学校も急増しています。
なぜプール授業が大切なのか? 命を守る「水泳学習」の意義
「そんなに暑いなら、もうプール授業はやめた方がいいのでは?」
そんな声もあるかもしれませんが、プール授業には決して無視できない役割があります。
それは、“いざというときに命を守る力”を養う授業であるということです。
日本は自然災害が多く、水辺の事故も毎年発生しています。泳げることは、遊びではなく**“自己防衛の手段”**でもあるのです。
そのため文部科学省も、学校教育における水泳学習を重要視しています。

解決策として注目される「民間委託」のプール授業
こうした課題を乗り越えるべく、今注目されているのが水泳授業の「民間委託」です。
いくつかの自治体ではすでに、スイミングスクールなど民間施設と連携し、以下のような形で水泳授業を実施しています。
- 温水プールを使用:屋内施設のため、天候に左右されず、熱中症ややけどのリスクが低い
- 民間インストラクターによる指導:泳力別で効率的に指導ができる
- 担任は安全確認に集中:監視や体調管理など、教員が本来の役割に専念できる
また、施設を学校授業だけでなく地域住民の利用にも開放することで、運営コストの抑制にもつながります。
安全と学びを両立するために、いまできること
今回紹介したように、学校のプール授業は今、大きな転換点にあります。
熱中症ややけどといった“想定外”のリスクが現実化している一方、子どもたちの命を守る学びとしての重要性も再認識されています。
今後は以下のような視点が重要になるでしょう。
- プールサイドの温度管理と日陰の設置
- WBGT(暑さ指数)を基準にした柔軟な授業判断
- 児童のこまめな水分補給・休憩時間の確保
- 安全・快適な環境を確保する民間施設との連携
地域や学校ごとに異なる事情がありますが、子どもたちの健康と教育のバランスをどう取るかが問われています。

水と共に学び、備えるために
プール授業は単なる“季節の風物詩”ではなく、子どもたちの安全教育そのものです。
過酷な暑さとどう向き合うか。教員の負担をどう減らすか。地域や保護者、学校が一体となって、未来を担う子どもたちを支える環境づくりが求められています。
この夏、ニュースで報じられたやけどや湿疹の事故を、単なる一過性の“トラブル”として終わらせるのではなく、今後の教育や環境整備への気づきに変えることが大切です。
あなたの地域の学校では、どのような対策が行われていますか?
安全で、学びの多いプール授業がすべての子どもたちに提供されることを願ってやみません。