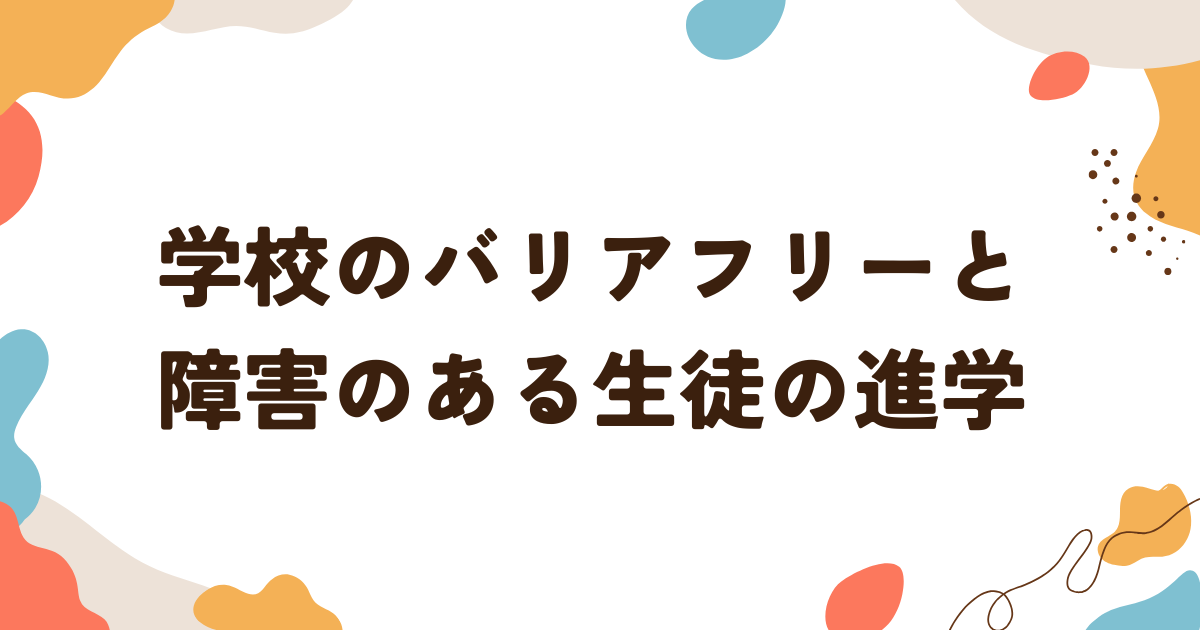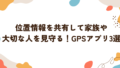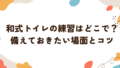「障害があるから」という理由で進学の選択肢が狭まってしまう――。そんな現実に心を痛める人も多いのではないでしょうか。近年、学校のバリアフリー化は少しずつ進んでいるものの、すべての学校が十分に対応できているわけではありません。特に公立高校では、設備や支援体制が整っていないことが理由で受け入れが難しいケースも見られます。
教育は誰にとっても平等であるべきだと思う一方で、現実には理想通りにはいかない部分も多く、バリアフリー化が抱える課題について考えてみたいと思います。また、「選べる環境」を作るために何ができるのか、見ていきたいと思います。
バリアフリー化は理想だけでは難しい
文部科学省は改正障害者差別解消法に基づき、障害者に対して「正当な理由なく特別な条件をつけるのは不当な差別」としています。しかし、実際には理想と現実のギャップが大きいのも事実です。特に公立高校では、予算や校舎の構造の制約から、バリアフリー化が進んでいない学校が多いのが現状です。
バリアフリー化にはエレベーターやスロープ、バリアフリートイレなどの設備、そしてそれをサポートする教職員の体制が必要です。しかし、これにはかなりの予算と人員が求められます。公立高校は限られた予算で運営されており、バリアフリー化を進めることが難しい学校もあります。
それでも、「設備がないから仕方がない」として進学の選択肢を狭めるのは避けたいものです。すべての学校で完璧な対応を求めるのは難しいかもしれませんが、少なくとも、学校と保護者が意見を交換する場を持つことは大切ではないでしょうか。

理想だけでは解決できない現実
「障害の有無に関係なく、すべての生徒が平等に学べる環境を作るべきだ」と感じる人は多いと思います。それはごもっともな意見です。学びたいという気持ちがあるのに、環境が整っていないことで進学を諦める――そんな状況を見過ごすことはできません。
ただ、現実的にはすべての学校に同じ対応を求めるのは難しいのが現状です。特に公立高校は予算の制約があるため、すべての学校で完璧なバリアフリー化を進めることは難しいかもしれません。
そこで考えられるのは、すべての学校を同じようにするのではなく、バリアフリーに対応した学校の選択肢を増やすことです。たとえば、地域ごとにバリアフリー設備が整ったモデル校を設けるなどの取り組みが、現実的な解決策になるのではないかと感じます。
多様な進学先を選べる社会へ
バリアフリー化を進めるために大切なのは、すべての学校を同じように整えることではなく、選べる環境を広げることも大切ではないでしょうか。
たとえば、バリアフリー対応が整った学校の情報を広く提供することで、障害のある生徒やその保護者が自分たちに合った学校を選びやすくなります。また、遠方から通う生徒には通学支援を提供することや、補助制度を整えることで、より多くの選択肢を提供できるかもしれません。
加えて、学校側の意識改革も重要です。もし設備面での対応が難しい場合でも、教職員が障害に対して理解を深めることで、生徒や保護者に安心感を与えることができるでしょう。学校全体が柔軟に対応できれば、「受け入れてもらえないかもしれない」という不安も軽減されるはずです。
すべての学校を完璧にすることが難しくても、生徒が自分に合った環境を選べるような社会が作れれば、より多くの人々が学びやすい環境に身を置けるようになるのではないでしょうか。