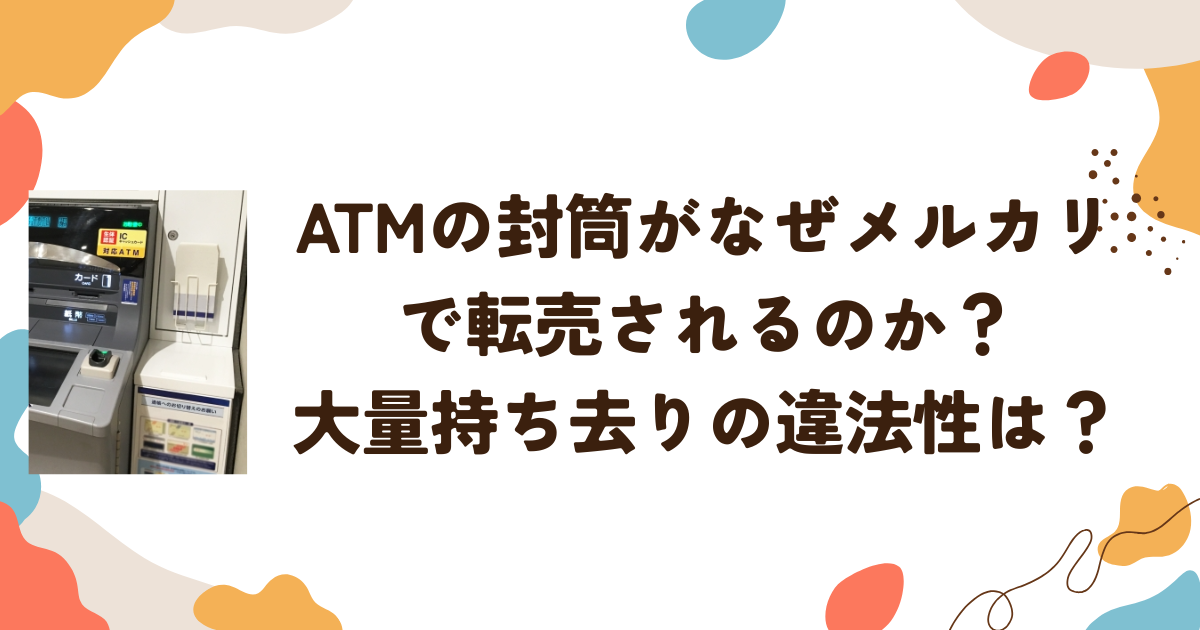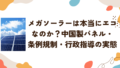2025年10月初旬、「ATMコーナーに設置されている現金用の封筒(銀行が無料提供しているもの)が、メルカリやヤフオクで大量に転売されている」という話題がSNSで拡散され、J-CASTニュースなど複数メディアでも報じられました。
本来は「ATM利用者の利便性のために無料で配布されている封筒」。それが “商品化”されている状況 に対し、銀行側もついにコメントを出す事態となっています。
ATM封筒は「無料なのになぜ売れる?」
この報道によれば、ゆうちょ銀行および地方銀行の封筒が「銀行 封筒」というキーワードでメルカリなどで多数ヒットしており、たとえばゆうちょ銀行の封筒40枚が税込300円で出品されて売り切れになっている例も確認されたとのことです。
また、人気ゲームキャラクター入りの封筒は 20枚で1,100円という高値で販売されるケースもあり、デザイン性や“珍しさ”を理由に価格がつけられている様子も見られます。

封筒は本来、ATM利用者の利便性を目的として無償で提供されているものですが、それが本来の用途を逸脱して“商品化”されているわけです。そして、こうした出品が増える背景には、「通常より早く封筒が減る」「封筒がないという利用者からの報告が出る」といった銀行側の認識もあります。
一方、銀行側は「封筒は利用者の利便性を重視して無料で提供しており、必要以上の持ち去りや転売行為は控えてほしい」という見解を示すにとどめています。対策としても「有効な方法は難しいが、注意喚起の掲示などを検討する」という回答にとどめており、根本的な解決策にはまだ至っていないようです。
利用者の立場からみる困惑と懸念
この問題が表面化したことで、ATM利用者の間には困惑や懸念の声も見られます。「ATMに封筒がない」「いつも使っていた封筒が見当たらない」「無料サービスがなくなるのでは」などです。無料で使える封筒が置いてあることを前提に現金の取り扱いをしていた人も多く、封筒が不足すれば利用者にとっては不便が生じます。
さらに、「こういう一部の人の行為のせいでサービスが制限されるのでは」という不満も漏れます。たとえば、銀行側が封筒の配布を中止・縮小する方向に動けば、利用者全体の利便性が損なわれる可能性があるからです。
また、この問題にはある種の「コレクション目的」が絡んでいる可能性も指摘されています。封筒の種類を複数揃えたものを“地銀セット”として出品している例なども見られ、封筒そのものを“趣味の品”として集めたい層が存在しているのではないかという見方も出ています。
ATMの封筒が置かれなくなるのか
ATMに備え付けられていた封筒は「現金用封筒」または「入金用封筒」などと呼ばれ、利便性向上や、現金を扱う際のセキュリティ・プライバシー保護への配慮として、多くの金融機関が長年にわたって行ってきた無料サービスでした。ATMが広く普及し始めた1970年代から1980年代以降、長期間にわたってこのサービスが提供されてきました。
しかし、「そもそもATMに封筒を置かない」という方針を採る銀行も、少しずつ出始めています。特に地方銀行や信用金庫を中心に、封筒設置を廃止する動きが報じられています。これは、資源節約(紙資源の削減)やコスト抑制、設備維持の合理化を目的とした動きと結びついています。
こうした動きは、SDGs(持続可能な開発目標)や環境配慮という文脈とも重なります。紙を削減し、無駄を出さない運用を目指すという観点から、封筒そのものを配布しない方向に転換する銀行が増えているのです。
しかし、封筒を置かないことは利用者の利便性を損なう面もあり、慎重な判断が求められるでしょう。
ATM封筒の転売は違法なのか?
このような封筒の大量持ち出しや転売行為は、必ずしも明確な法令違反に問えるものではない点に注意が必要です。封筒自体は「利用者向けの無償提供物」であり、法律上「所有権」が明確に利用者に移るものとは考えられません。そのため、営利目的での転売が直ちに違法と認定されるケースは限られます。
ただし、モラルや公共性の観点から、本来の提供目的を逸脱した行為として批判があり得ます。また、銀行が封筒を適切に管理できない状況を放置すれば、提供側の信頼低下や運用コストの増大につながります。
また、利用者保護や公共インフラの側面から、一定程度の規律を求められる可能性もあります。「無断で大量に持ち去る行為=公共物の損耗をもたらす行為」と評価されれば、業務妨害や器物損壊などの観点が問題になることもあり得ますが、実際の適用例は確認されていません。
サービスと資源の綱引き
この封筒転売問題はいくつかの視点から、現代社会が抱えるジレンマを浮かび上がらせています。
- 無料提供サービスの持続可能性
銀行はあくまで「ATM利用者の利便性を確保する」ために封筒を置いています。しかし、それを無制限に許すと、不正利用や持ち去りが増えてコスト負担が膨らむリスクがあります。提供側のコスト意識と利用者の利便性のバランスをどう取るかは難しい課題です。 - 環境配慮と資源削減の圧力
紙資源の無駄を避けるため、すでに一部の銀行では封筒設置をやめる動きが出ています。こうした動きは、環境配慮やコスト効率改善の観点から理解できますが、利用者が慣れ親しんだサービスを突然切り替えるにはリスクも伴います。 - モラルと公共性の再考
無料サービスを「当然」と捉える利用者と、それを“利益源”に目をつける者との間でモラルのすれ違いが起きています。公共性や共同利用の原則を守ろうとする認識をどう広げていくかも問われています。 - デジタル・キャッシュレス化との関係
近年、キャッシュレス決済や銀行のオンライン化が進む中で、現金引き出し・入金自体の利用頻度は相対的に減る傾向があります。封筒を使う機会そのものが減れば、この問題が“過去の遺物”になる可能性もあります。
封筒転売問題と将来への視点
この封筒転売問題に対して、銀行・利用者双方にとって現実的な対応の方向性を整理すると、以下のようなものが考えられます。
将来的には、キャッシュレス化・オンライン取引の拡大により、現金のやり取り自体が減少していく可能性があります。それに伴い、現金用封筒という“物理的な道具”の必要性も見直されるかもしれません。その過程で、“利便性を維持しつつ無駄を削る”運用が鍵を握るでしょう。