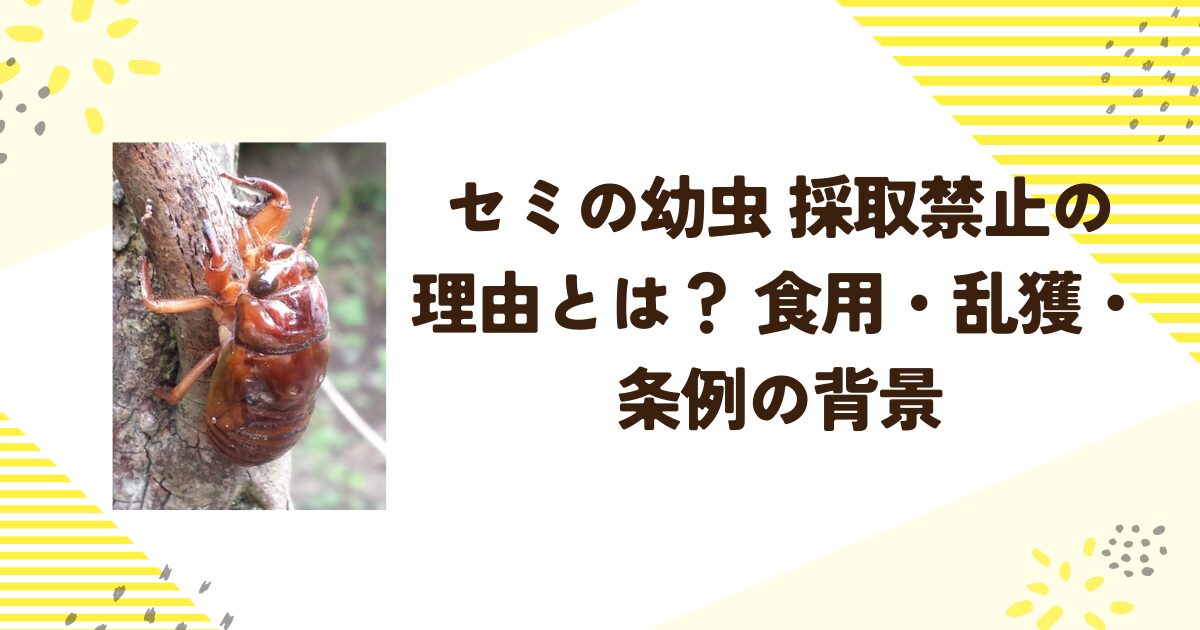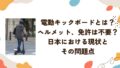最近、東京都江東区・猿江恩賜公園など都内の公園で、「セミの幼虫の採取は禁止」と注意書きが日本語はもちろん中国語・韓国語・英語でも掲示されたというニュースが話題になりました。
これは、梅雨明けの深夜から明け方にかけて、グループで幼虫を大量に採取する外国人(特に中国系)を複数目撃したことが原因です。公園側は、利用者から「食用にしているのでは?」などの苦情も受け、例年より早めに掲示したといいます。
セミの幼虫、なぜ「採取禁止」の張り紙?
管理者によれば、夜間の巡回で「虫かごに数十匹入れていた」「『日本語がわからない』と開き直った」などの事実も確認されており、単なる1〜2匹の採取でなく“乱獲レベル”だったため、度を越えた行為と判断したとのことです。
東京都では都条例で園内の動植物の採集が禁止されており、過去には杉並区や荒川区、埼玉県川口市でも同様の措置が取られてきました。これは環境保全の観点からも正当な対応ですが、一方で「セミ幼虫=食材」として捉える文化が存在する点に注目が集まっています。
セミ幼虫を食べる文化とは?その歴史と現代事情
世界に点在するセミ食文化
セミを食べる文化は世界的に見られ、古代中国では漢の時代から“焼きセミ用コンロ”が出土するなど、その歴史は古いです。また、アリストテレスやファーブルが幼虫の味を評価した記録もあります。
現代中国でも地域によっては、スーパーで冷凍セミ幼虫が売られており、開封市では600gで約140元(約2,800円)という“高級食材”として流通しているという事例もあります。
日本における昆虫食文化
日本でも伝統的に昆虫食文化が根付いており、イナゴやハチノコなどと並んでセミも食された記録が存在します。長野県ではかつてセミ幼虫の缶詰が販売されたこともあるそうです。文豪・井伏鱒二は、アブラゼミを「ビールのつまみによい」と讃えています。
セミの幼虫の味や調理法は?
調理方法はさまざまで、通例は幼虫が地中から這い出してくる羽化直前の“ソフトシェル”状態が一番美味しいとされます。食感はエビやナッツのよう、ナッツに近い濃厚な味わいという声が多く、シンプルな素揚げや天ぷら、煮付け、燻製、チリソース炒めなど、さまざまな料理法が紹介されています。
実際に食べた人の体験談を見ると、「ピーナツ風味でプリプリ」「甲殻類に近い」「草の青い風味もあるがおいしい」と肯定派が多数。一部では「青臭さが強い」「見た目が気持ち悪い」といった否定的な感想もありますが、調理法や下処理次第では美味しくなるとの意見が多いです。
昆虫食ブームとセミの幼虫の可能性
近年、昆虫食は環境面や栄養面で注目を浴びており、欧米でも「エコ・プロテイン」として認識が広がっています。日本国内でも虫食イベントや昆虫料理研究会が開かれており、セミ幼虫に関しても「セミ会」「串揚げセミ」などイベントが行われ、乾燥や粉末化され、「セミ塩」として調味料利用も進められています。
栄養素としては高タンパク質・低脂質で、必須アミノ酸やミネラルも多く含まれ、健康食材としてのポテンシャルも期待されています。

環境保護と採取規制の重要性
しかし、乱獲による生態系への影響は無視できません。公園での夜間採取は、羽化直前の個体を大量に奪うことで、セミの生息数減少や周辺生態系への影響を招く恐れがあります。実際、公園側の張り紙で触れているように、「子どもたちがセミを楽しみにしている」という声もあります。
それを踏まえ、自治体によっては商業目的や食用目的を禁じる条例を整備し、「採取禁止」の看板で住民向けにも注意喚起を行ってきました。東京都や埼玉県川口市などでは、過去に同様の張り紙が確認されており、「環境保全」と「地域の治安保持」を目的としています。
留意すべき法令とマナー
公園や公共施設内では、条例により「動植物採取全面禁止」である場合が多く、仮に昆虫食の意図があろうがなかろうが、採取行為自体が禁止されているケースがほとんどです。特に大量採取や深夜のグループ活動は、景観や安全、周辺住民への悪影響リスクもあるため、厳しく取り締まられています。

セミの幼虫と向き合う──文化と環境のバランスをどうとるか
以下にポイントを整理します。
セミの幼虫を食べるという文化
- 世界各地にある歴史的・現代的食文化。
- 味はエビ・ナッツ系で高タンパク、健康面でも有望。
- 調理法も多彩で、料理の可能性は広い。
採取の問題点
- 公園での乱獲は生態系への負荷や景観・治安問題を引き起こす。
- 法令上多くの公共施設では採取禁止。
- 観光・文化圏外の人にとっては非常識に映る行為で、摩擦の原因にも。
これからの展望
- 養殖・地産地消:採取ではなく栽培的に育てる方法を研究・普及。
- 公園以外の採取場所:農地や私有地で育てて、安全かつ持続可能な収穫。
- 文化交流の場として:昆虫食イベントなどを通じ、誤認や偏見を減らす。
- 法令整備と教育:文化としての価値を認めつつ、公共空間でのマナー・法令遵守を強化。
セミの幼虫を食べる文化
セミの幼虫を「食べる」という行為は、単なる“ゲテモノ食”ではありません。それは、人間の進化史に根ざした行為であり、美味と栄養、環境への配慮を両立しうる「持続可能な食文化」の可能性を秘めています。しかし、公園での無秩序な採取は当然、地域のルールや環境意識を無視した行為です。
これからは「どこで」「いかに」育て、「どうやって」調理し、「どう楽しむか」を多方面から真剣に考え、推進していくことが求められているのではないでしょうか。公園からプラットフォームへ──そんな未来の昆虫食文化を期待したいものです。