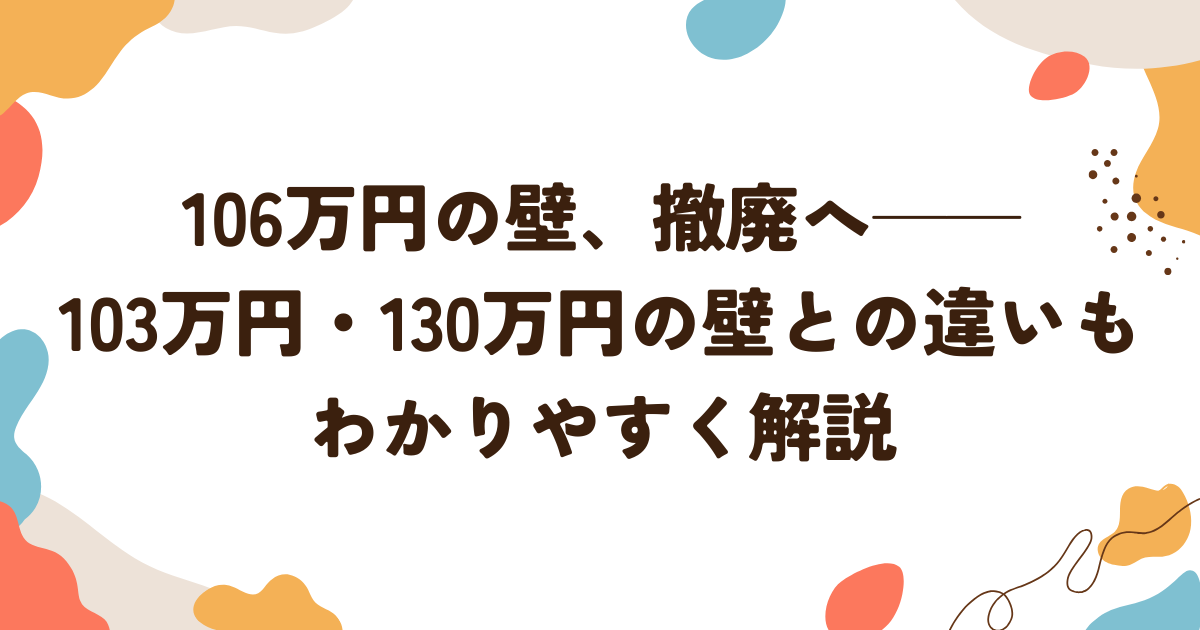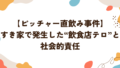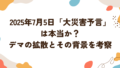2025年5月、政府はパートタイム労働者などの厚生年金加入拡大を柱とする年金制度改革法案を閣議決定し、国会に提出しました。その中心となるのが、いわゆる「106万円の壁」の撤廃です。
この制度改正は、パートやアルバイトで働く多くの方にとって収入の目安となっていた「○○万円の壁」という考え方を見直すきっかけとなります。本記事では、106万円の壁に加えて、103万円の壁、130万円の壁との違いを整理しつつ、今回の制度改正の影響をわかりやすく解説していきます。
そもそも「○○万円の壁」とは?
「○○万円の壁」とは、年収がある一定額を超えると社会保険料や税金が発生し、手取り収入がかえって減ってしまうという現象、またはそれを避けるための「収入制限ライン」を指します。主に以下の3つの壁がよく話題になります。
103万円の壁:所得税がかかるライン
これは「配偶者控除」の対象かどうかに関わる金額です。
- 対象者:扶養されている配偶者(多くはパート主婦)
- 内容:年収103万円以下であれば、所得税がかからず、かつ配偶者控除の対象になります。
- 超えるとどうなる?:本人に所得税が課税され、配偶者(主に夫)の税控除額が減ります。
つまり、103万円は「税制上の扶養」に関係するラインです。
130万円の壁:社会保険(健康保険・年金)に自分で加入しなければならないライン
- 対象者:配偶者の扶養に入っているパートなど
- 内容:年収130万円を超えると、扶養を外れて、自分で健康保険や国民年金(もしくは厚生年金)に加入する必要があります。
- 超えるとどうなる?:社会保険料の支払い義務が生じ、手取り収入が大きく減る可能性があります。
130万円の壁は「社会保険上の扶養」に関係しています。
106万円の壁:厚生年金への強制加入ライン(特定条件あり)
- 対象者:週20時間以上働く従業員で、勤務先が従業員51人以上などの要件を満たす場合
- 内容:年収が106万円以上になると、健康保険・厚生年金に強制加入となり、保険料が天引きされます。
- 問題点:企業や働き手の間で「106万円を超えると手取りが減る」という理由で、労働時間を調整する動きがありました。
なぜ「106万円の壁」だけが撤廃されるのか?
政府は今回、この106万円の壁を撤廃する方針を打ち出しました。背景には次のような理由があります。
- 最低賃金の上昇:全国の最低賃金は2024年時点で平均1,055円。週20時間×52週で働くと、年収はすでに約110万円を超えます。つまり、現実的に週20時間働けば「106万円の壁」はすでに突破されているのです。
- 労働者の保護:週20時間働くというのは、すでに正社員に近い働き方。厚生年金や健康保険などの社会保険が適用されるのが自然であるという考え方が定着しつつあります。
- 企業側の負担逃れを是正:これまで「106万円以内なら保険に入れなくてもよい」として、企業が保険料負担を避けるケースも少なくありませんでした。それにメスを入れる意味もあります。
改正内容の具体的ポイント
今回の年金制度改革法案では、以下のような内容が盛り込まれています。
- 年収要件(106万円以上)の撤廃:法成立から3年以内に段階的に実施
- 企業規模要件(従業員51人以上)の緩和・撤廃:2027年10月から緩和を開始し、2035年10月に完全撤廃
- 新たに厚生年金に加入する人への支援策:保険料負担の軽減措置(具体的な設計は今後の議論)
中小企業・個人への影響と不安の声
この制度改正により、社会保険の適用対象が一気に広がりますが、次のような懸念の声も聞かれます。
- 中小・零細企業の負担増:パート社員が厚生年金に加入することで、企業側にも保険料負担が発生。加えて最低賃金の引き上げも進んでおり、人件費の増加が重荷に。
- 働き手側の「現在バイアス」:将来の年金額が増えるメリットよりも、目先の手取り減少を避けようとする傾向が強く、「週20時間未満」に働き方を切り替える動きが出る可能性も。
- 生活保護との逆転現象:「年金より生活保護の方が手厚い」という声も。保険料を払い続ける制度が報われないという不信感が生まれている側面もあります。
手取りが減少する具体例
●年収106万円のパート労働者の場合
- 社会保険加入前:手取り約103万7000円
- 社会保険加入後:手取り約89万6000円
- 差額:約14万1000円の減少
このように、社会保険に加入することで手取りが大幅に減少するため、労働時間を抑えて加入を回避しようとする動きが見られます。
社会保険料の逆進性と低所得者への影響
社会保険料は所得に対して一定割合で徴収されるため、低所得者ほど負担が重くなります。例えば、国民年金保険料は月額1万6490円で、収入に関係なく一律です。そのため、月収15万円のフリーターでは負担率が約11%に達します。一方、高所得者の負担率は低く、制度の逆進性が指摘されています。
また、国民健康保険料も所得控除が少なく、所得が少ない人でも高額な負担となるケースがあります。例えば、所得が数百万円程度でも、保険料が年間90万円以上になることもあります
今後どうなる?私たちが考えるべきこと
「106万円の壁」の撤廃は、働くすべての人が社会保険に加入できる公正な社会を目指す方向性としては評価できます。しかし、それを実現するには、制度面だけでなく現場の現実にも寄り添った配慮が必要です。
特に、中小企業に対しては助成金や雇用保険との連携、保険料の一部免除など、具体的かつ持続可能な支援策が求められます。
一方、働く人にとっても「一時的な手取りの減少」だけにとらわれず、将来への投資として厚生年金に加入することの意味をしっかり理解することが重要です。
最後に
今回の「106万円の壁」撤廃により、多くのパート労働者が配偶者の扶養をはずれることになります。これによって厚生年金や健康保険に加入する対象が広がり、将来の年金額が増えるというメリットはあるものの、現在の手取り収入が減ることへの不安や不満の声も根強くあります。
特に、扶養をはずれることで新たに社会保険料を負担しなければならなくなった低所得者にとっては、今の生活への影響が大きく、「せっかく働いても手元に残らない」という声があがるのも無理はありません。
一方で、これまで企業や制度側が「短時間・低収入の働き方であれば社会保険は適用しなくてよい」として、いわば“制度の隙間”に労働者を置き去りにしていた面も否定できません。今回の改革は、そうした不公平を正し、正社員に近い働き方をするパート労働者にも社会保障を適用するという意味で、重要な一歩といえます。
今後は、扶養をはずれて社会保険に加入する人々への負担を軽減する支援策や、保険料の逆進性を緩和する仕組み、そして「将来の安心」と「今の生活」のバランスを取る制度設計が求められます。制度に参加する一人ひとりが納得し、安心して働ける社会の実現には、丁寧な説明と現実的な配慮が不可欠です。