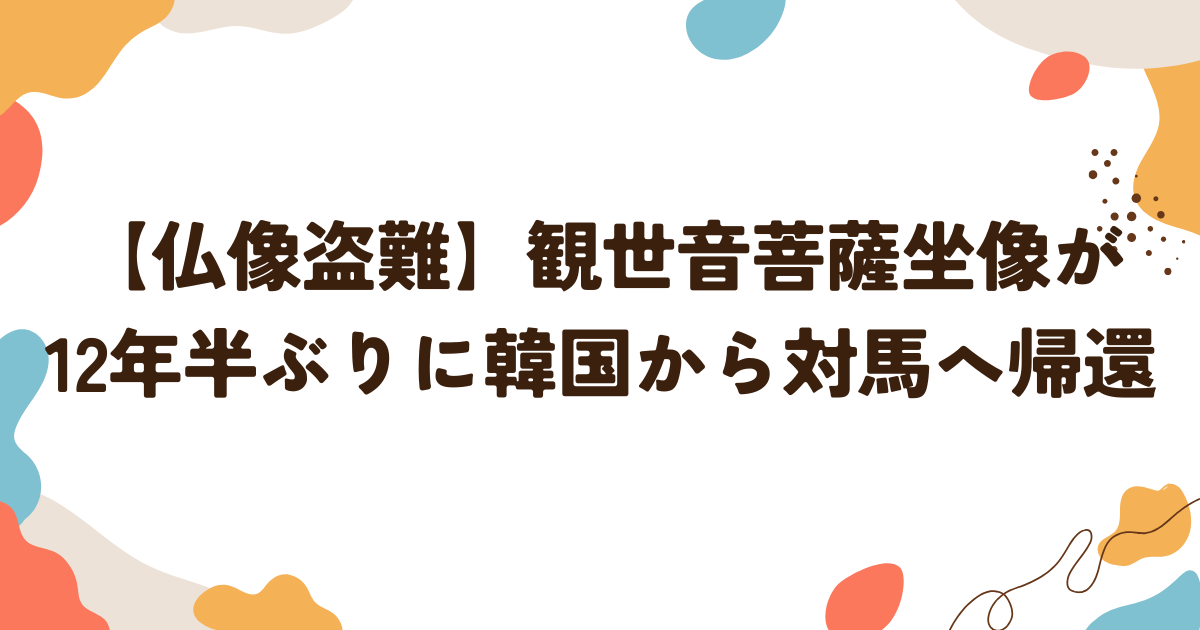2025年5月12日――長崎県対馬市の観音寺から2012年に盗難され、韓国へ持ち込まれた「観世音菩薩坐像」が、12年半の時を超えて、日本に帰ってきました。の返還は、日韓間の文化財返還問題における重要な節目となりました。
この記事では、この仏像盗難事件の全容とともに、他の事例や今後の対策について、わかりやすく、丁寧にご紹介します。
盗まれた仏像、12年半の旅路
事件が起きたのは2012年10月。長崎県・対馬市の観音寺から、「観世音菩薩坐像」が盗まれました。犯人は韓国人の窃盗団。仏像は海を越え、韓国へ。
しかし、ここで思わぬ展開が。韓国中部・瑞山市の「浮石寺(プソクサ)」が、「この仏像は14世紀に日本の倭寇に略奪されたものだ」と主張し、所有権を求めて韓国の裁判所に提訴したのです。
こうして、盗まれた仏像をめぐる日韓の法廷闘争がスタート。
そして2023年10月、韓国最高裁がついに「観音寺に所有権がある」との判決を確定。返還への道が開かれました。2025年1月には返還手続きが完了し、5月12日未明、仏像は福岡を経て対馬へと戻ってきました。
法要と博物館収蔵:文化財としての再出発
仏像が戻った5月12日、観音寺では檀家や地域住民を集めて法要が営まれました。
かつて本堂に静かに座していた菩薩像が、再びその姿を見せたのです。
しかし、防犯上の理由から、仏像はすぐに「対馬博物館」に移され、厳重に保管されることとなりました。
他にもある!仏像盗難の実態と深刻な現実
この事件だけが特別ではありません。実は日本全国、仏像や石仏の盗難が相次いでいます。
和歌山の大量盗難事件
2010年から2011年にかけて、和歌山県内では60件以上の仏像盗難が発生。被害仏像はなんと172体に上りました。犯人は逮捕されたものの、多くは未だ行方不明です。
オークションにも仏像が…?
ネットオークションで「仏像」「如来」「菩薩」などと検索すると、多数の仏像が出品されています。その中には、個人所有には不自然なサイズの仏像や、明らかに古い石仏、法具なども。
同じ出品者が複数の仏像を出品しているケースもあり、疑念を抱かざるを得ない状況です。
文化財は“国民共有の宝”――盗難防止のために必要なこと
寺院の多くが地方にあり、しかも「無住寺(住職が常駐していない寺)」が増え続けています。
奈良県警の調査では、無住社寺の約20%が無施錠。防犯カメラもなく、文化財が盗まれても気づかれないことが多いのです。
▼いま、必要な対策は?
- 防犯カメラの設置
- 地域住民と連携した見守り活動
- 文化財の詳細な写真・記録の保存
- オークションや古美術市場への監視強化
- 国と自治体の積極的な予算措置
とくに、“国民共有の財産”である文化財を守るためには、民間まかせでは限界があります。国レベルでの法整備と、予算配分の見直しが急務です。
◆国際的な文化財返還問題としての意義
今回の仏像返還は、単に“盗まれた物が戻った”という話ではありません。
韓国では一部世論が返還に反対しており、国内的にも難しい判断があったとされています。だからこそ、日韓両国の司法と関係者が冷静に判断し、返還が実現したことは、国際社会における重要な一歩です。
文化財の返還には、所有権・略奪の歴史・現地保存の可否など、多くの要素が絡みます。
今後の国際的なルール作りにおいても、この件は前例として重く受け止められるでしょう。