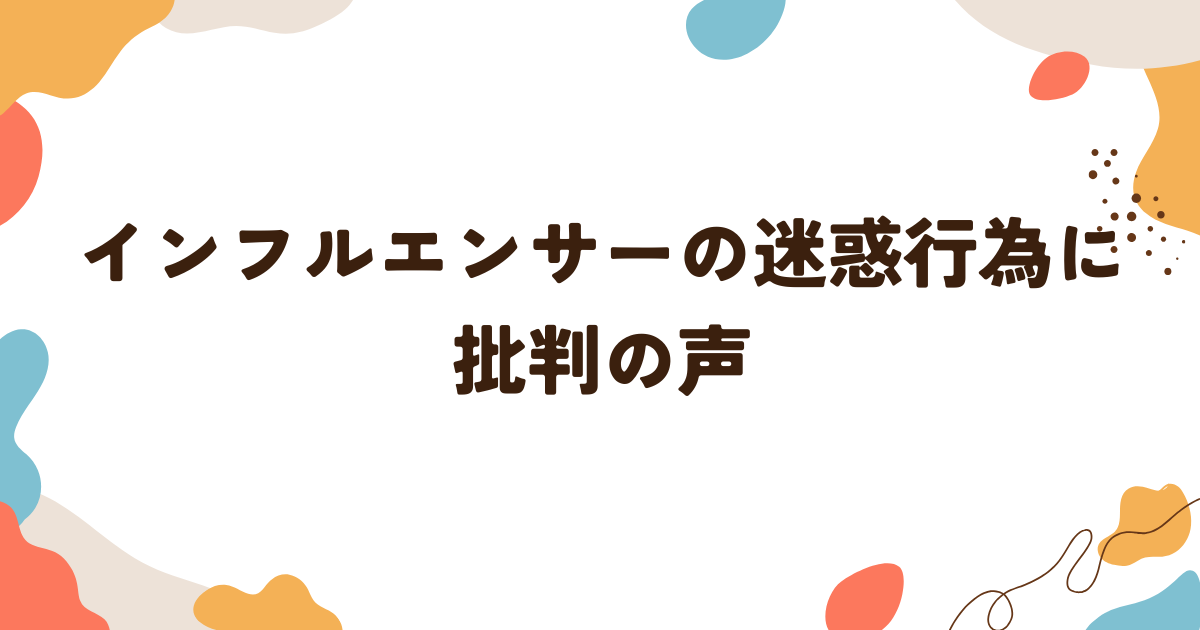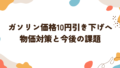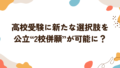近年、日本を訪れる外国人観光客が増える一方で、その中には文化的背景やマナーの違いからトラブルを引き起こす人も見受けられるようになりました。とくに、SNSや動画配信サイトで人気を集めようとする「迷惑系インフルエンサー」による行為が、日本国内でも大きな物議を醸しています。
最近話題となっているのが、「Sigma Boy」という名の海外インフルエンサーです。彼はフォロワー数約100万人という影響力を持つクリエイターで、東京・山手線車内でキャリーバッグ型のスピーカーから大音量の音楽を流し、さらにはホームでバク宙を披露するなど、公共の場での常識を逸脱した行動を繰り返しました。
さらに、渋谷スクランブル交差点では信号が青になるたびに交差点の中央でスピーカーの上に立ちバク宙を披露。交差点内で何度もパフォーマンスを繰り返し、歓声を浴びながらスマホでの撮影を煽るかのような姿がSNS上に拡散されました。
ネット上にあふれる批判の声
こうした迷惑系インフルエンサーの行動には、日本語・英語問わず多くの非難の声が上がっています。
「逮捕してくれ」
「なんで誰も注意しないの?」
「スピーカーに水ぶっかけたい」
「日本があなたを禁止することを願っている」
「二度と日本に来ないで」
このようなコメントが殺到する背景には、「日本人の我慢強さにつけ込んでいる」「明らかに日本の文化を軽視している」といった感情も見え隠れします。
なぜ取り締まらないのか?
こうしたインフルエンサーやユーチューバーの迷惑行為に対して、多くの人が疑問に思うのは「なぜ警察が取り締まらないのか」という点です。
日本の警察は基本的に「現行犯」での対応が原則であり、SNSに投稿された動画だけでは即座に逮捕や罰則につながるケースは限られています。また、軽犯罪法や条例違反に該当する場合でも、証拠の確保や手続きの煩雑さから、対応が後手に回ることが少なくありません。
さらに、外国人観光客に対しては外交的な配慮もあるため、強硬な措置が取りにくいという一面も否めません。
迷惑系ユーチューバーという現代の「現象」
今回インフルエンサーのケースに限らず、これまでも「迷惑系ユーチューバー」として物議を醸した人物は少なくありません。例えば、日本人の間でも有名な某ユーチューバーは、店舗に無断で突撃し商品を勝手にレビューしたり、公共交通機関内で大声を出すなどして炎上を繰り返しました。
彼らに共通するのは「目立つこと」が目的であり、注目を浴びることで動画の再生数が増え、結果として収益が得られるという構造です。つまり、倫理やモラルよりも「バズる」ことが優先されているのです。
路上ライブや無許可パフォーマンスの横行
渋谷や新宿などの繁華街では、路上ライブやダンスパフォーマンスを無許可で行う人々も少なくありません。本来、公共の場所で演奏や演技をするには警察署からの道路使用許可が必要です。
しかし、実際にはそのような許可を得ずに人通りの多い場所でパフォーマンスを行い、SNSにその様子をアップするケースが後を絶ちません。特に夜間や週末には、渋谷センター街などが「無法地帯」と化すこともあります。
これも「見てもらえる場所」「拡散されやすい場所」であることを見越して行動しているわけで、視聴数至上主義の悪しき影響がここにも表れています。
プラットフォームの責任
ここで重要なのは、迷惑行為を助長する構造そのものに問題があるという点です。SNSや動画配信プラットフォームは、再生回数や「いいね」に応じて収益を生む仕組みを提供しています。結果として「過激であればあるほど稼げる」構図が成立してしまっています。
本来、そうした行為を未然に防ぐためには、各プラットフォームが一定の審査機能や報告体制を強化し、迷惑行為や違法行為には報酬を支払わない、あるいはアカウント停止といった対処を行うべきです。
日本の社会と観光客マナーのすれ違い
外国人観光客が日本でトラブルを起こすケースも増えており、今回のインフルエンサーによる行為もその一例です。背景には、「日本は優しい国」「何をしても許される」という誤解もあるかもしれません。
しかし、静かな公共空間を重んじる日本文化において、無遠慮なパフォーマンスや大音量の音楽は明確な迷惑行為です。こうした価値観の違いを認識し、日本を訪れる際には一定のマナー教育がなされるべきです。
観光立国を目指す日本において、こうした「迷惑行為への対策」は避けて通れない課題です。
終わりに
迷惑系インフルエンサーの問題は、一個人の行動を超えて、現代社会の構造的な歪みを映し出しています。単なる迷惑行為として片づけるのではなく、私たちが何を許容し、どのような行動に報酬を与えてしまっているのか、根本から見直す必要があるのではないでしょうか。
プラットフォームの在り方、法制度の運用、市民の意識――いずれもが連携しなければ、この問題は今後さらに深刻化していくことでしょう。目立つことが「勝ち」ではないという価値観を、改めて問い直す時が来ているのです。