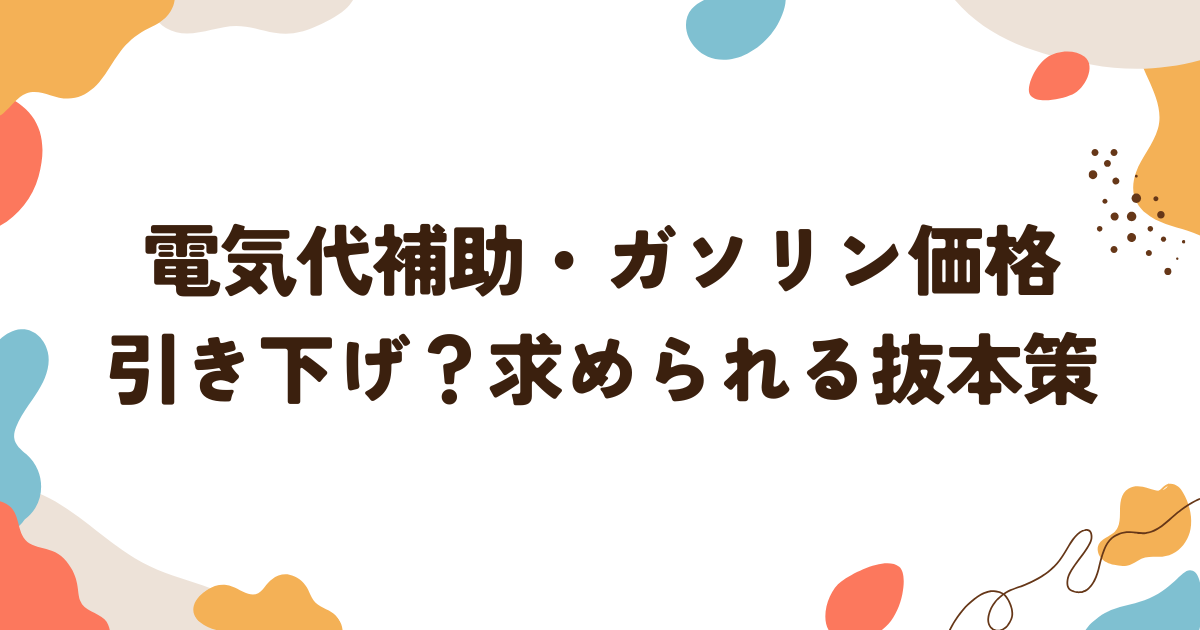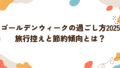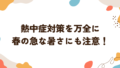2025年4月20日、石破茂首相はNHK「日曜討論」に生出演し、物価高騰を受けた経済対策について意欲を示しました。
特に、夏場の電気代補助やガソリン価格の引き下げに取り組む方針を明言し、「国民の負担を少しでも減らしたい」と強調しています。
石破首相は、電気代について「夏に大きく上がることがある。いつの時期にどのような対策が必要なのかを十分に考え、政府としてしっかり取り組む」と述べました。また、企業や家計への支援についても、与党や野党との協議を重ねながら、持続可能な経済の構築を目指すとしています。
単なる短期的な支援ではなく、新しい産業やサービスの創出を促す投資型の経済へ転換することも視野に入れていると説明しました。
しかし、現金給付や消費税減税を求める声も根強く、今後の議論の行方に注目が集まっています。
電気代補助、これまでと今後の見通し
こ数年、政府は光熱費の高騰に対応するために、電気代への補助金制度を段階的に実施してきました。
2023年度には「電気・ガス価格激変緩和対策事業」として、一般家庭向けに1kWhあたり7円程度の補助が行われ、電力会社を通じて料金から自動的に割り引かれる仕組みが取られました。補助期間は当初2023年1月から2024年5月使用分までの予定で行われてきました。
その後、「酷暑乗り切り緊急支援」として、追加の支援策が講じられ、2024年8月・9月・10月使用分についても、使用量に応じた料金の値引きが実施されることが決定されました。
ただし、2025年度以降の補助については、現時点では具体的な計画は示されておらず、石破首相が言及した「夏の電気代補助」が正式に実現するかどうかは、今後の政府方針にかかっています。
石破首相が打ち出した「夏の電気代補助」が正式に決定すれば、再び家計負担の軽減が期待されますが、実施時期や規模は未定です。
ガソリン税と「トリガー条項」 廃止への動き
ガソリン価格対策について語るうえで外せないのが、「トリガー条項」の存在です。
トリガー条項とは、ガソリン価格の全国平均が160円を3か月連続で超えた場合に、暫定税率(25.1円/L)を停止する仕組みです。
しかしこの条項は、2011年の東日本大震災後にガソリン税を復興財源に充てる目的で凍結され、それ以降、ガソリン価格が高騰しても発動されていません。
近年、トリガー条項の凍結解除や暫定税率の見直しを求める声が強まり、2024年末には自民党・公明党・国民民主党の3党が暫定税率そのものの廃止に合意しました。
しかし、廃止の具体的な時期はまだ決まっていないのが現状です。
国民生活に直結する問題だけに、早急な対応が求められています。
消費税減税を求める声も
物価高が続く中で、消費税減税を求める声も高まっています。
特に、食料品や光熱費(電気・ガス・水道)については、消費税を免除するべきだとの意見が多く聞かれます。
現在、食料品には軽減税率8%が適用されていますが、光熱費は標準税率10%が課されています。
生活必需品であるにもかかわらず、家計への負担は無視できないものとなっており、「せめてエネルギー分野の消費税は撤廃すべき」という主張も根強く存在しています。
消費税減税については与党内でも慎重な声が多いものの、国民の実感としては「生活を守るための減税を」という切実な思いが背景にあります。
エネルギー補助は庶民に実感しやすい支援策
経済対策として、現金給付が話題になることもありますが、ばらまき批判がつきまとうのも事実です。
これに対し、電気・ガス・ガソリンなどのエネルギー補助は、所得や家族構成に関係なく、すべての人々にメリットが行き渡りやすい支援策といえます。
エネルギー分野への補助の最大のメリットは、「実際に安くなった」と生活の中で実感できる点です。
特に、光熱費がかさむ冬季や夏季には、家計への支援として非常に意味のある施策となります。
単なる一時的な給付ではなく、日々の暮らしを支える本質的な支援が求められているのです。
選挙前の「ばらまき」批判も根強く
一方で、こうした支援策が選挙直前に打ち出されることについて、「ばらまきではないか」という批判もあります。
現金給付や減税、補助金が、政権への支持率向上や選挙対策を意図しているのではないかとの疑念は根強く、過去にも同様の批判が繰り返されてきました。
国民が求めているのは、単なる一時的な人気取りではなく、中長期的に安定した生活を支える政策です。
人口減少・高齢化が進む日本において、今必要なのは、将来を見据えた確かな施策です。
エネルギー政策においても、単なる価格補助にとどまらず、再生可能エネルギーの普及や省エネ推進、持続可能なインフラ整備といった未来への投資が不可欠です。
政治の真価は、こうした本質的なビジョンを示せるかどうかにかかっています。