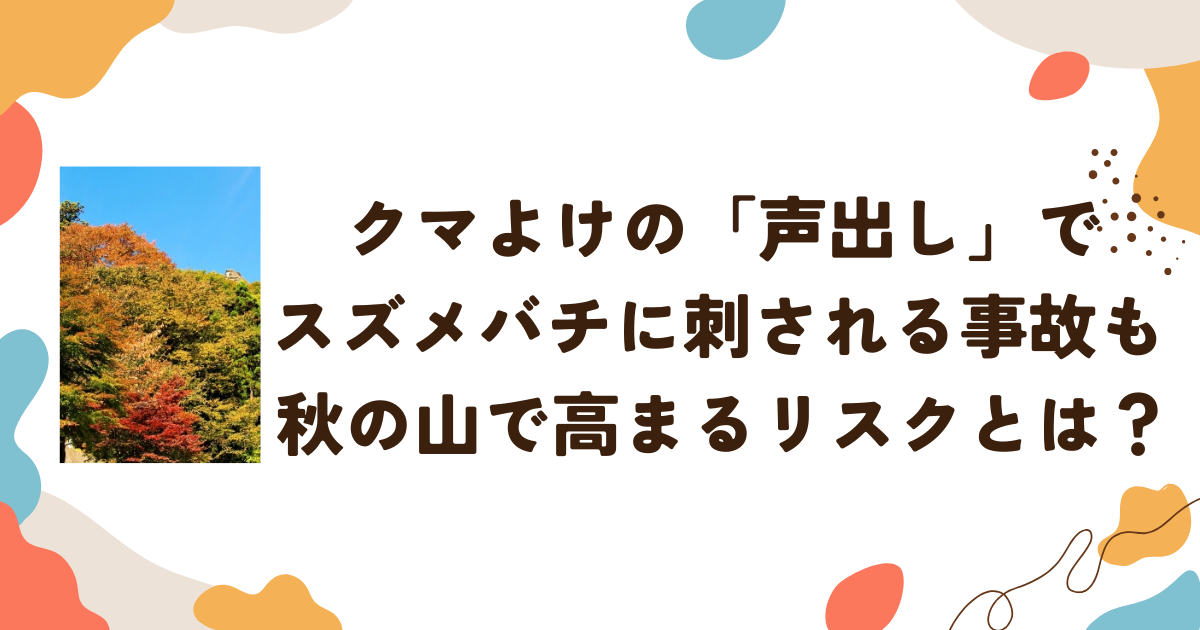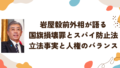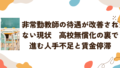近年、登山道や里山で「クマよけのために大声を出して歩いていた人が、スズメバチに襲われる」という事故が報告されています。
一見、正しいように思える“声出し行動”が、実は別の危険を招くこともあるのです。
本記事では、スズメバチの出現時期や冬越しの仕組み、秋に特に注意すべき理由、そしてクマ対策としての大声の有効性と注意点を詳しく解説します。

クマ警戒の「声出し」がスズメバチを刺激か
2025年10月7日、広島県廿日市市栗栖の旧津和野街道で、市内の小学校が実施した校外学習中に児童ら計19人がハチに刺され、病院に搬送される事案が発生しました。参加したのは小学6年生27人のうち15人と引率教員・ボランティアら合わせて19人で、いずれも命に別条はないと報じられています。現場は山間部で携帯電話が圏外となる場所があり、119通報が可能になるまで約15分かかったとの情報があります。
当日は午前9時20分ごろにグループが山に入り、引率は教員2名とボランティアガイド5名が同行していました。安全対策として、ガイドから「クマに遭遇しないように声を出して進む」よう指示があり、児童らは鈴を鳴らしながら歌をうたって移動していたと報告されています。
約6.5キロの行程の中間付近、午前10時50分ごろに数匹のハチを確認した後、後方の児童の悲鳴に反応して10匹以上のハチが枯れ木の穴から一気に飛び出し、群れに襲われる形になったと現場の校長らは説明しています。校長や引率者は児童にかがむよう指示し、撃退用スプレーで一時的にハチを遠ざけて避難させたとされています。
現場では一部の児童が耳や背中、尻、足などを刺され、精神的ショックで動けなくなった子もいました。救急隊が到着して状態を確認した結果、幸い全員軽症で命に別状はないとされています。

なぜ「声出し」が刺激になったのか
今回の報道では、広島市森林公園こんちゅう館などの専門家が「スズメバチは音や振動に敏感で、刺激されると攻撃的になる」と説明しています。
スズメバチ類は樹洞や枯れ木の穴などに巣を作ることが多く、集団で行動する個体数が多い時期に近づくと防衛本能から群れで反応することがあります。特に夏から秋にかけて巣が大きくなり働き蜂が増えるため、接近した人間の声や鈴の振動、悲鳴などが「侵入」や「脅威」として認識される可能性があるとされています。
専門文献でも、夏〜秋にかけて働き蜂が増えて攻撃性が高まること、巣の近くで一定方向に多数のハチが飛んでいる場合は巣があるおそれが強いことが指摘されています。最初に見えた2〜3匹が威嚇行動をとり、その後仲間を集めて攻撃に転じる例は知られています。
スズメバチの出現時期は?活動のピークは9〜10月
スズメバチの活動は、春の女王バチの単独行動から始まります。
4月〜5月にかけて女王が巣を作り、6月ごろから働きバチが羽化し始め、巣の勢力が一気に拡大します。
そして夏の終わりから秋(9月〜10月)にかけて、巣の規模が最大となり、もっとも攻撃的になります。
この時期、巣の中では新しい女王バチが育てられており、働きバチは巣を守るために非常に警戒心が強い状態です。
人間の声や振動、香水や黒い衣服などにも敏感に反応し、わずかな刺激でも攻撃してくることがあります。
特に山道や農道などでは、木の枝の中や地中などに巣を作っていることがあり、知らずに近づくと突然刺される危険があります。
冬を越すのは「新女王」だけ 巣の再利用はされない
寒さが深まる11月中旬を過ぎると、スズメバチの活動は徐々に鈍り、やがて働きバチは死に絶えます。
しかし、新しく生まれた女王バチだけが冬眠に入る点が重要です。
女王は樹の根元や落ち葉の下など、安全な場所に潜り込み、冬の寒さをしのぎます。
そして翌春、再び活動を始め、新しい巣を一から作り直します。
つまり、スズメバチの巣は年を越して使われることはないため、冬場に見つけた巣は空である場合がほとんどです。
ただし、初冬の暖かい日に活動を再開する個体もいるため、11月中旬までは油断できません。
秋はスズメバチが最も危険な季節
9〜10月は、スズメバチが「繁殖期」と「食糧不足期」を同時に迎える時期でもあります。
巣の中では次世代の女王が育つ一方で、周囲の昆虫や果実が減少し、ハチたちはエサを求めて広範囲に飛び回ります。
このため、人間の発する音・匂い・動きに過敏に反応する傾向が強まり、登山者や農作業者との接触事故が増えます。
実際、環境省のまとめでは、スズメバチによる刺傷被害の大半が9〜10月に集中しています。
また、働きバチの数がピークに達するこの時期は、巣の防衛本能が最高潮に達します。
「巣を見つけたら静かにその場を離れる」「黒っぽい服を避ける」「香水をつけない」など、刺激を与えない行動が重要です。

クマよけに「大声」は本当に効果があるのか?
クマは本来、人間を避ける動物です。
そのため、「自分の存在を知らせる」ことが最大の予防策とされています。
登山中に鈴やラジオを鳴らしたり、複数人で話しながら歩くことは、クマよけとして有効です。
しかし、今回のように「大声を出しながら歩いていたらスズメバチに刺された」という事故は、
まさにクマ対策とハチ対策のバランスの難しさを示しています。
大きな声や振動は、クマを遠ざける効果がある一方で、スズメバチにとっては敵の接近音に聞こえる場合があります。
特に巣の近くで叫ぶ、金属音を立てる、ラジオを大音量で流すなどの行為は危険です。
最近のクマ被害は増加傾向
環境省や各自治体の報告によると、ここ数年、クマの出没件数と人的被害は全国的に増加傾向にあります。
特に、2025年は秋田・富山・福島などでクマによる重傷事故が相次いでいます。
クマは本来、人を避ける動物ですが、食料不足や山の実りの減少により、人里近くに出てくることが増えています。
こうした背景から、登山や山道を歩く際には「声出し」が推奨されてきました。人の気配を知らせることで、クマが近づかないようにするためです。実際、鈴やラジオ、会話などの音はクマよけに一定の効果があるとされています。
「声出し」がスズメバチを刺激するリスク
しかし、今回のようにクマを警戒して大きな声を出す行為が、スズメバチを刺激してしまう危険性があります。スズメバチは大きな音や振動、黒い服装、急な動きに反応して攻撃行動をとることがあります。特に巣の近くで声を張り上げたり、集団で騒いだりすると、巣の防衛本能を刺激することになりかねません。
専門家によると、「クマ対策としての声出し」は一定の効果があるものの、スズメバチが多い秋の山では静かな声や鈴の音にとどめるなど、状況に応じた配慮が必要だと指摘されています。特に児童や生徒を引率する場合には、安全確認を徹底し、蜂の巣の位置や活動の有無を事前に把握しておくことが望ましいです。
学校行事と安全管理の課題
今回の事故を受けて、「あえてこの時期に子どもたちを山に連れて行く必要はなかったのではないか」という意見も聞かれます。秋の山は景色が美しく、自然学習の場として魅力的ですが、同時にスズメバチやクマの活動期と重なる時期でもあります。
学校側は「クマよけのための声出し」を指導していたとしても、環境全体を考慮すれば、もう少し慎重な判断が求められたのではないかという声が上がっています。
教育現場では、自然体験の重要性と安全確保の両立が課題となっています。登山や遠足を実施する際には、地元自治体や森林管理事務所などから最新のクマ・蜂情報を入手し、リスクを最小限にする対策が不可欠です。天候や気温によって活動状況が変わるため、「毎年同じ時期だから大丈夫」とは限らない点にも注意が必要です。
まとめ
秋の山では、クマよけの「声出し」がスズメバチを刺激してしまうという、思わぬ事故が起きる可能性があります。スズメバチは11月ごろまで活動し、クマは冬眠前に食料を求めて活発に動く時期です。どちらも人間にとって危険な存在であり、行動次第で事故を防げるケースも多くあります。
安全な登山や校外学習のためには、「自然を怖がる」よりも「自然を正しく知る」ことが何より大切です。環境への理解と慎重な判断があってこそ、秋の山の魅力を安心して楽しむことができるのです。