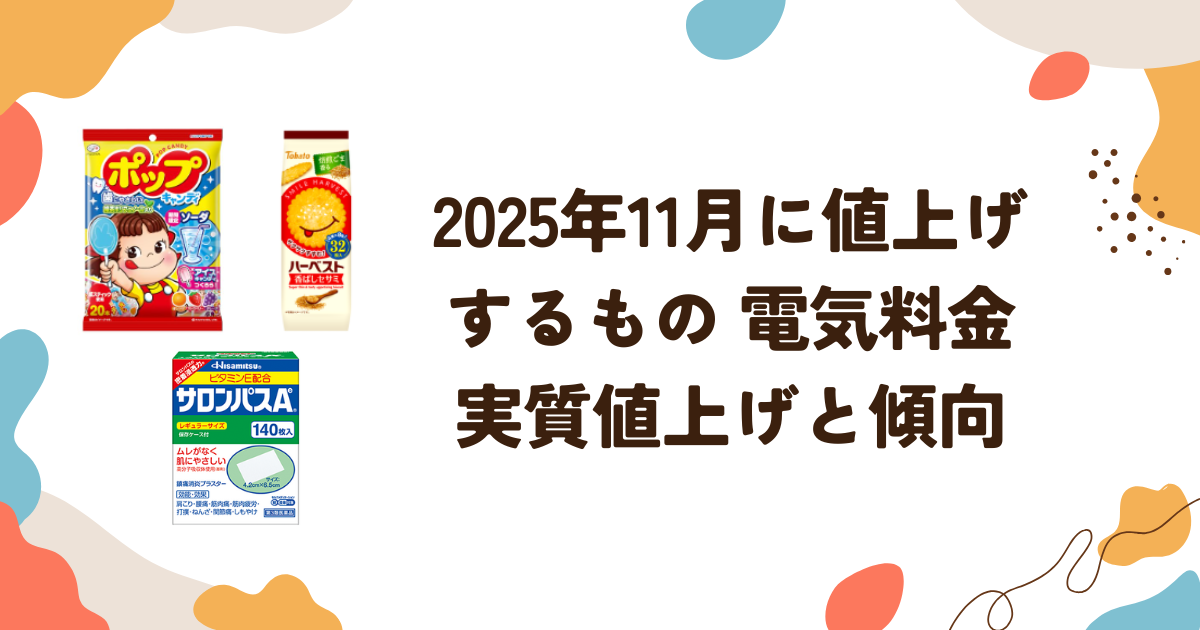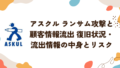2025年11月に実施予定で、発表されている価格改定では、これまでの大規模ラッシュに比べると「控えめ」です。今年は暮らしに直結する「値上げ」が相次ぎました。本稿では、2025年11月の値上げ傾向とその背景、12月までの見通し、実質賃金・物価・米高騰の影響含め、年間を通した振り返りまでを解説します。
11月の値上げ傾向
2025年通年で食品メーカーによる価格改定が多く、年初から累積で品目数は増加しています。
ただし11月単月の改定は「大波」ではなく、国民生活への影響が表面化しにくい小刻みな改定が中心です。帝国データバンクの集計でも、2025年は年間で多数の品目改定があるものの、11月は比較的件数が抑えられています。
アサヒビールでは国産ウイスキー、テキーラの値上げを予定していましたが、システム障害の影響により価格改定を延期しています。価格改定日については現時点で未定。
補助金終了による電気料金値上げ
2025年11月分(10月使用分)の電気料金は、前月と比べて上昇します。
主な理由は、原油や石炭の輸入価格が上昇したことと、これまで家計を支えてきた政府の電気料金補助金が9月で終了したためです。補助金がなくなることで、電気代が上がる形となりました。
ただし、ここで明るいニュースもあります。高市総理が「冬季に再び電気・ガス代への補助金を再開する方針」を表明したことで、今後、再度の値下げが見込まれています。正式な開始時期や補助内容の詳細は今後の発表次第ですが、政府としても「物価高の中での冬の家計支援」を重視している姿勢が見られます。

2025年11月に値上げするもの
| メーカー名 | 商品カテゴリ | 主な対象商品 | 値上げ幅 | 実施時期 |
|---|---|---|---|---|
| 不二家 | チョコレート | 「ミルキーチョコレート袋」、ペコちゃん商品各種、サンリオキャラクターズ商品各種、「ハートチョコレート袋」ほか | 約5~15% | 11月1日出荷分より |
| 東ハト | ビスケット菓子 | 「ハーベスト」 | 11月1日納品分より | |
| スターバックスコーヒージャパン | 家庭用コーヒー商品 ・ティー商品 | 「ハウスブレンド」「コロンビア」など | 8% | 11月10日より |
| 久光製薬 | サロンパス、フェイタス | 「サロンパスAe」「温熱用具 直貼」「フェイタスZαローション」など | 3~30% | 11月4日出荷分より |
| 日本郵便 | ゆうメール | ~150g | 180円⇒190円 | 11月1日より |
2025年12月も「少なめ」見通しの理由
12月は報道では「12月も大規模な一斉値上げには至らない」との見方が多く出ています。理由は次の通りです。
- 企業は年末商戦を見据え大幅値上げを避ける傾向(消費の落ち込みを警戒)。
- 燃料価格の国際相場が安定傾向を見せれば燃料調整費の上積みが限定的となる可能性。
ただし「少なめ=影響がない」わけではなく、毎月の小幅上昇の積み重ねは年末にかけて家計負担を押し上げます。特に光熱費と食費の同時上昇は家計にとって厳しいため、個々の家庭では備えや節約の工夫が必要です。
2025年の値上げを振り返る — 規模、分野、原因
年間の規模感
帝国データバンクの調査などでは、2025年は食品分野を中心に年間で多数の価格改定が行われ、累計で大きな品目数に達しています。特に調味料・飲料・乳製品などで改定が目立ちました。
主な原因
- 国際的な原材料・エネルギー価格の変動 — LNGや石油由来燃料の価格推移が電気・ガス料金へ波及。
- 物流費・人件費の上昇 — 物流コストや人手不足を背景に、企業が価格に転嫁。
- 農産物(とくに米)の気象・需給ショック — 猛暑などの気象要因や観光需要増で供給と流通にひずみが出て価格が上昇。政府の在庫放出や調整が実施されたが、短期的な実売価格への反映は遅れることがありました。
実質賃金と物価の関係 — 家計にとっての“実感”はどう変わったか
物価上昇が続くなかで注目されるのが実質賃金の動きです。名目賃金が上昇しても物価上昇がそれを上回れば、実質的には購買力が低下します。
2025年前半〜中盤のデータでは、季節要因(賞与)で名目が押し上げられる時期もありましたが、通年で見れば物価の上昇が家計の負担を強めている局面が存在します。
政府統計や経済調査機関の分析では、実質賃金の伸びが依然として脆弱である点が指摘されています(賞与増が一時的に実質を押し上げる局面はあったものの、持続性が課題)。
米高騰の実情と影響
2025年は米の小売価格が大きく注目されました。生産面では収量増を見込む年もありますが、流通・保管・販売政策の影響で実売価格が下がりにくいケースが生じ、消費者価格は高止まりしました。
政府は備蓄米の放出や価格調整策を打ち出して消費者負担緩和に動いたものの、流通のボトルネックや販売ルートの問題から、現場での価格低下は限定的だったとの報告もあります。
米は主食であり家計支出に占める比率が高いため、継続的な高値は低所得世帯に特に厳しい影響を与えます。
家計でできる具体的な備え
- 定期的な家計の「見える化」 — 電気・ガスの使用量と料金を月ごとにチェックし、無駄な待機電力や過剰暖房を見直す。
- まとめ買いと価格単位比較 — 内容量・単価を比べ、長期保存が利く食品は安いときにまとめて買う(ただし賞味期限に注意)。
- サブスクや定期サービスの見直し — 利用頻度が低いサービスは解約・一時休止を検討。
- 政府の支援制度や地域支援情報の確認 — 低所得世帯向けの支援や、一時的な補助がある場合があります。
- 食材の代替とレシピ工夫 — 高騰している食材は別素材で代替するなど、献立で調整。
先を見据えた「小さな備え」が大きな差を作る
2025年11月の値上げは、かつての大波と比べれば「控えめ」と見える面がありますが、毎月の小幅な上昇が積み重なれば家計の負担は確実に増します。実質賃金の改善と物価の鈍化が今後のカギであり、政府・企業の対応動向(価格調整、支援施策、流通の改善)を注視するとともに、家計レベルでは「見える化」と生活の柔軟な見直しが求められます。