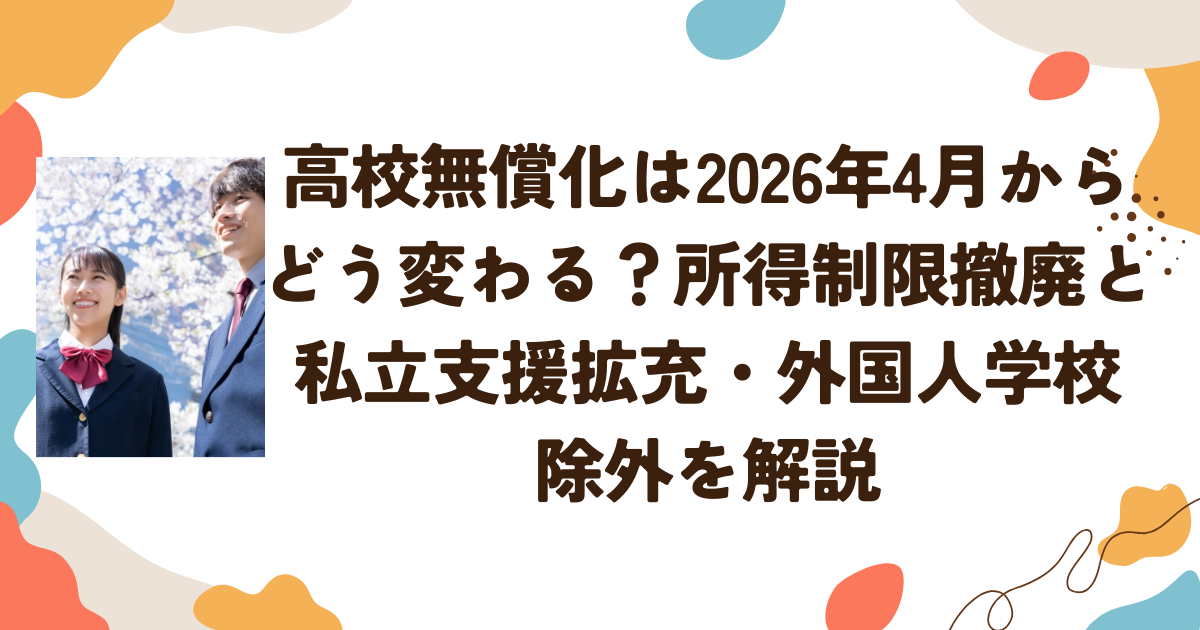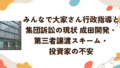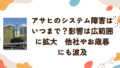高校無償化は、子どもの教育機会を保障するために導入された制度であり、日本社会における「教育の平等」を象徴する政策のひとつです。
これまで段階的に拡大されてきましたが、2025年10月、公明党・自民党・日本維新の会の3党による協議で「外国人学校を対象外にする」という制度案が浮上しました。この方針は、教育の公平性、人権、財源問題をめぐって大きな論点となっています。
本記事では、制度の歴史、対象外とする理由、海外との比較、今後の課題などをわかりやすく詳しく解説します。
高校無償化はいつから始まったのか?制度の基本と背景
日本で「高校無償化」が導入されたのは2010年4月です。当時の鳩山政権の政策として、「高等学校等就学支援金制度」がスタートしました。
▼制度の趣旨
- 家庭の経済状況にかかわらず高校教育を受けられるようにする
- 教育格差の是正
- 高校進学率の維持・上昇
- 少子化対策の一環
公立高校は授業料が実質無償化され、私立高校についても支援金によって授業料負担が軽減される仕組みが作られました。それまでは、経済的理由で高校に進学できないケースも一定数見られ、特に母子家庭や非正規雇用世帯で問題化していました。

▼2026年4月から高校無償化はどう変わる?所得制限撤廃と私立への支援拡充
2026年4月からの高校無償化制度では、これまで議論されてきた「所得制限の撤廃」と「私立高校への支援拡充」が本格的に実施される予定です。最大のポイントは、世帯収入による制限をなくし、すべての家庭が支援の対象となるという点です。
・公立高校:授業料0円
・私立高校:上限約30万円 → 45万円へ拡大予定
・年間数千億円規模の財源が必要
まず、所得制限の撤廃についてです。国公立高校の授業料に関しては、2025年度からすでに所得制限が撤廃されましたが、2026年度からは対象が私立高校にも拡大されます。従来は年収910万円未満の世帯に限られていた就学支援金の加算部分についても、収入に関係なく支給されるようになります。これによって、高所得世帯を含むすべての家庭が制度の対象となり、「高校授業料は原則無償」という方向性が明確になります。
次に、私立高校への支援拡充です。現在の就学支援金制度では、私立高校に対する国の支給額には上限がありますが、2026年度からはその上限が引き上げられる方針です。新制度では、全国の私立高校の授業料平均にあたる年間45万7千円を上限に助成が行われます。これにより、授業料が平均水準前後の私立高校であれば、実質的に無償化が実現すると見込まれています。
ただし、注意点もあります。今回の制度は授業料のみを対象としたものであり、制服代・教材費・部活動費・通学費などの付随費用は従来どおり自己負担です。また、私立高校の中には授業料が年間45万7千円を上回る学校もあるため、その超過分は保護者が負担する必要があります。
外国人学校はなぜ対象外とされたのか?新制度案のポイント
2025年10月18日に共同通信が報じた内容によると、自民党・公明党・維新の会による「高校無償化の新制度案」では、次の点が明らかになりました。
▼主な変更方針
- 外国人学校を対象外にする
- 収入制限を撤廃し、すべての世帯を対象に拡大
- 財源確保の方法として「税制対応」(増税の可能性)を示唆
- 実施後3年で制度の検証を行う
これまでの制度では、一定の基準を満たした外国人学校(インターナショナルスクールや民族学校など)も指定校として支援金の対象に含まれていました。今回の新方針では、その指定制度自体を廃止する方向です。
▼なぜ除外するのか?政治的・財政的理由
現時点で報道されている理由や背景として、以下のようなポイントが挙げられます。
- 「国費で支援する以上、日本の教育課程に準拠した学校を優先すべき」という考え
- 留学生や一時滞在者など、将来的な日本定住が見込めない層が含まれる
- 財源規模が膨らみすぎることへの懸念
- 教育内容の統一性や管理体制の確保が難しい
- 国内世論の反応に配慮
自民党と維新の会は特に「定住性」や「税負担との整合性」を重視しており、公明党は慎重姿勢も見せつつ財源問題で合意に傾いています。

海外ではどうしている?外国籍児童の教育支援の実態
諸外国でも「義務教育〜高校段階」は無償または公費負担が一般的ですが、対象範囲や外国籍児童への扱いは国によって大きく異なります。
▼例① ドイツ
- 公立校は授業料無料
- 私立やインターナショナルスクールは原則自己負担
- 滞在資格により支援内容が変動
▼例② フランス
- フランス在住なら国籍不問で公立校に入学可能
- インター校や宗教系学校への補助は限定的
▼例③ 韓国
- 公立高校は授業料無料
- 朝鮮学校など民族系学校は補助対象外または自治体判断
▼例④ アメリカ
- 義務教育は学区の税金で賄われる
- 留学生や一定条件外の子どもは対象にならないことも多い
日本の今回の判断は、欧米のように「公教育重視・私立等は対象外」とする方向性に近いとも言えます。ただし、国内には一定数の外国籍児童・定住者が存在するため、一律除外による不公平感が課題となっています。
高校無償化をめぐる賛否と社会的影響
今回の方針には、それぞれの立場から賛成・反対の意見が上がっています。
▼賛成意見
- 税金で支援するなら日本の教育課程を踏まえた学校に限定すべき
- 留学生など一時滞在者を含めると財源負担が増えすぎる
- 外国人学校は独自教育を重視しており、国の管理が難しい
- 子ども・子育て支援策全体との整合性が必要
▼反対・懸念の声
- 日本に住む外国籍の子どもや永住者も多く、一律除外は不公平
- 国連など国際機関から人権問題として指摘される可能性
- 多文化共生や国際教育の現場が圧迫される
- 国籍ではなく「実際の居住実態」を基準にすべき
特に、民族学校やインターナショナルスクールに通う子どもたちの多くが「日本育ち・将来も日本で働く見込み」である点を重視する声もあります。
財源問題と「税制対応」への注目
今回の制度案では「新たに安定的な財源を税制措置も含めて確保する」と明記されました。既存財源の流用は否定されているため、次のような可能性があります。
- 所得税・住民税の一部見直し
- 教育関連の目的税創設
- 企業負担の拡大
- 消費税の将来的な増税議論
「全世帯対象」「所得制限撤廃」という方針が現実化すれば、年間5,000億円規模の追加支出になるとの試算もあります。外国人学校を除外することで財源の抑制を狙っているという見方もあります。
今後のスケジュールと見通し
現時点(2025年10月時点)でわかっている動きは以下の通りです。
- 3党実務者協議:10月22日以降に文案調整
- 年内に制度設計の大枠をまとめる可能性
- 実施後3年で制度検証
- 施策別の支援制度(外国人向け)を設計する可能性も
政府・与党による「高校無償化の再定義」と「線引きの明確化」は、教育政策だけでなく移民・多文化共生・財政問題とも深く関係します。
まとめ:高校無償化の拡大と排除の狭間で問われる「公平性」
高校無償化はこれまで、多くの家庭の負担を軽減し、日本社会の教育水準を支える政策として機能してきました。所得制限撤廃などの拡充策は歓迎される一方、「外国人学校除外」という新方針は議論を呼ぶテーマです。
今後の鍵を握るポイントは以下の3つです。
- 支援対象の線引きと定住性の判断基準
- 財源確保と国民負担の是非
- 国際的な人権・教育保障との整合性
日本社会が「誰の教育を公費で支えるのか」という問いにどう答えるかが、今まさに問われています。今後の制度設計や国会審議次第で、教育環境が大きく変わる可能性もあります。続報に注目しつつ、背景理解を深めておくことが重要です