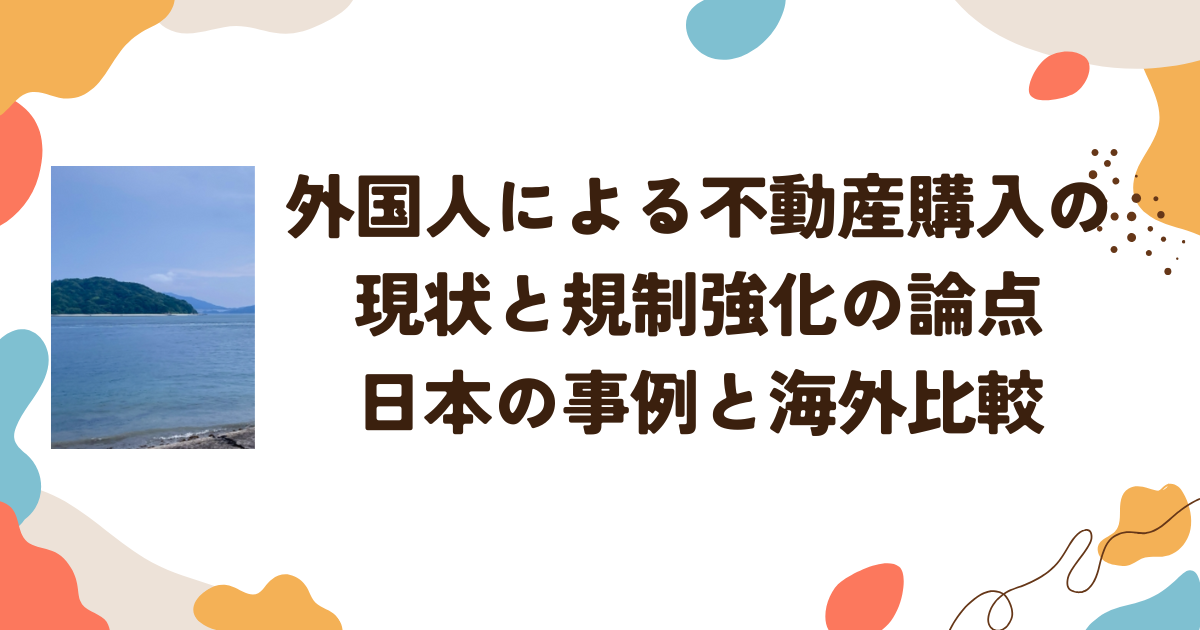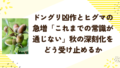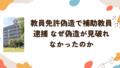日本政府は、外国人による不動産取引について、カナダ、ドイツ、韓国、台湾の制度を今年度中に調査する方針を示しました(読売新聞報道)。
これは、2022年に施行された「重要土地等調査・規制法(重要土地等調査法)」の見直し条項を踏まえ、諸外国の制度を参考に国内法のあり方を検討する狙いです。今回の調査対象国はいずれも「外国人や非居住者の不動産取得」をめぐって何らかの規制や政策を持っており、各国の仕組みは参考になる点が多いと言えます。
まず、日本側の現状を整理すると、重要土地等調査法は自衛隊施設周辺や国境離島など安全保障上重要な土地について所有者や利用状況の調査を行い、必要に応じて規制をかける仕組みを整えました。しかし、この法律は「外国人による取得そのものを全面的に禁止する」制度ではなく、あくまで重要地域周辺の利用監視や事前届出といった枠組みに留まります。政府は施行後5年での見直し規定を設けており、今回の比較調査はそのための具体的材料集めです。

では、調査対象国の代表例と日本との比較で注目すべき点を見ていきます。
カナダ:直接的な制限と税制措置の組み合わせ
近年、カナダは外国人による住宅購入が地域の住宅価格を押し上げるとの批判に応え、連邦や州レベルで規制を強化してきました。代表的な措置としては、一定期間の外国人購入禁止(いわゆる「Foreign Buyer Ban」)の導入や、ブリティッシュコロンビア州などでの追加の不動産取得税(外国人に対する追加譲渡税、追加Property Transfer Tax)など、直接的な購入制限と税措置を組み合わせる手法が取られています。こうした手法は「購入は許すがコストを上乗せして投機を抑える」か、「一定期間・一定区域で購入自体を制限する」かの二つのアプローチのどちらか、あるいは両方を使う点で分かりやすい対策です。
ドイツ:一般には緩やか、だが用途別・地域別の制約あり
ドイツは一般的に外国人の不動産取得を広く認めています。EU域内の移動の自由や投資の自由と整合するため、居住用不動産や都市部の商業地については大きな制限を設けていないことが多い一方、農地や森林、国防に関わる区域については州(Länder)ごとに追加の承認や報告が必要になる場合があります。つまり「物件の種類(農地等)や場所(基地周辺など)に応じた差し替え」が行われる点が特徴です。ドイツの仕組みは、日本の「重要地域の指定+個別許認可」方式とも近いところがありますが、欧州内の法的枠組みが影響する点に注意が必要です。
韓国:居住実態や投機抑制を重視する行政運用
韓国では都市部を中心に外国人の不動産取得について厳格化の動きが出ています。特に短期の転売や居住実態のない投資目的の購入を抑えるために、「購入後に一定期間居住すること」などの条件を付す事例や、特定地域での購入制限の検討が行われています(政策は頻繁に更新されるため、逐次の確認が必要です)。韓国の例は「投機抑制をいかに実効的にするか」という課題への参考になります。
台湾:相互主義と会社設立要件
台湾は一般に外国人の不動産取得を認める一方、「相互主義(相手国が台湾人に対して同様の扱いをするか)」を基準にするケースや、外国企業が不動産を持つ場合には現地法人の登記や追加の制約を課すルールが見られます。つまり「国籍や法人形態に応じて手続きや可否が変わる」仕組みで、これも日本が参考にしやすい制度の一つです。
外国人に既に購入された不動産をどうするか
「規制強化は分かるが、既に買われてしまった物件はどうするのか」という声はもっともな指摘です。法改正で後から既存の所有権を遡って剥奪することは、法律の遡及禁止や財産権保護の観点から慎重にならざるを得ません。現実的な手法としては次のような選択肢が考えられます。
- 届出・報告義務の強化:既存所有者にも一定の報告義務を課し、安全保障上問題がある用途変更や第三者への譲渡を制限する。
- 利用規制(用途限定):軍事施設周辺など重要地域に限り、使用目的や賃貸先に対する制約をかける(行政による使用差止めや条件付許可)。
- 課税・罰則の導入:投機目的や違法取得が疑われる場合に追加課税や罰則を適用することで実効性を高める。
- 買い取り制度の設計:極度に安全保障上の問題がある場合に限り、国や自治体が公的資金で買い取るスキームを検討する(財政負担と正当手続きの検討が必要)。
これらのうち、実行可能性と憲法・国際法上の課題を同時に検討する必要があります。特に既得権を剥奪するような強硬策は、国内外での訴訟リスクや外交問題を招きかねません。
外国人による土地取得の代表的事例
① 北海道ニセコ地区 ― 外資による地域活性化と地価高騰の典型例
北海道・ニセコは、世界的に人気のスキーリゾート地。2000年代以降、特にオーストラリアやシンガポール、香港などの外国資本が大規模に参入。国際水準の高級ホテルやコンドミニアムを次々と開発しました。外国資本による投資が最も成功し、かつ最も劇的に地域を変貌させた事例の一つです。
一方で、地価や物価の高騰により、地元の住民や日本企業が住居やビジネスを維持することが難しくなる「ニセコ化」と呼ばれる現象も指摘されています。

② 森林・水源地の買収 ― 目的不明・規制不備が露呈するケース
北海道や宮崎県などで、中国系資本を中心とした外国人・法人による森林・水源地の大規模買収が確認されています。日本の広大な森林や、水源地となる土地が、外国資本によって密かに取得されている事例は、特に安全保障や環境の面で大きな懸念事項となっています。
買収される土地は数百ヘクタールに及ぶものもあり、主に中国系資本によるものが多いと報じられています。
- 資源の独占リスク: 水資源は生命線であり、その土地が外国資本に押さえられることへの不安。
- 目的の不透明さ: 買収の目的が太陽光発電などと説明されるケースもありますが、開発されずに放置されたり、具体的な利用目的が不明確な場合も多く、地域住民の不安が高まっています。
③ 笠佐島(山口県) ― 離島買収と住民不安・安全保障の象徴的事例
山口県周防大島町の離島・笠佐島で、中国籍の個人・法人による島の大部分(約94万㎡)の購入されました。人口わずか数人の小規模離島ですが、自衛隊の岩国基地や呉基地に比較的近い場所に位置しているため、「外国資本による土地取得が、有事の際に日本の安全保障に影響を及ぼすのではないか」という懸念が持ち上がりました。
土地の利用目的が不明瞭な中、島民は不安を募らせ、有志とともに「笠佐島を守る会」を設立し、土地の買戻しを目指す活動を開始しました。
安全保障上の論点
- 近隣には岩国基地・呉基地など重要拠点
- 国会・議会でも取り上げられ、重要土地規制の議論に波及
- 「合法ではあるが、規制の空白地帯」が浮き彫りに

外国人による不動産取得問題
外国人による不動産取得問題は、安全保障、地域経済、投資誘致、個人の財産権という複数の価値がぶつかる複雑なテーマです。
今回の政府の比較調査は、他国の成功例・失敗例を学びつつ、日本の実情に即した制度を設計する良い機会になります。ただし、制度設計は「何を守るために、誰にどんな負担を課すのか」を国民に丁寧に説明し、既に購入している人々への配慮や法的安定性を保つことが不可欠です。
今後、政府の調査結果が公表され次第、具体的な法改正案や施行時期が議論されることになります。