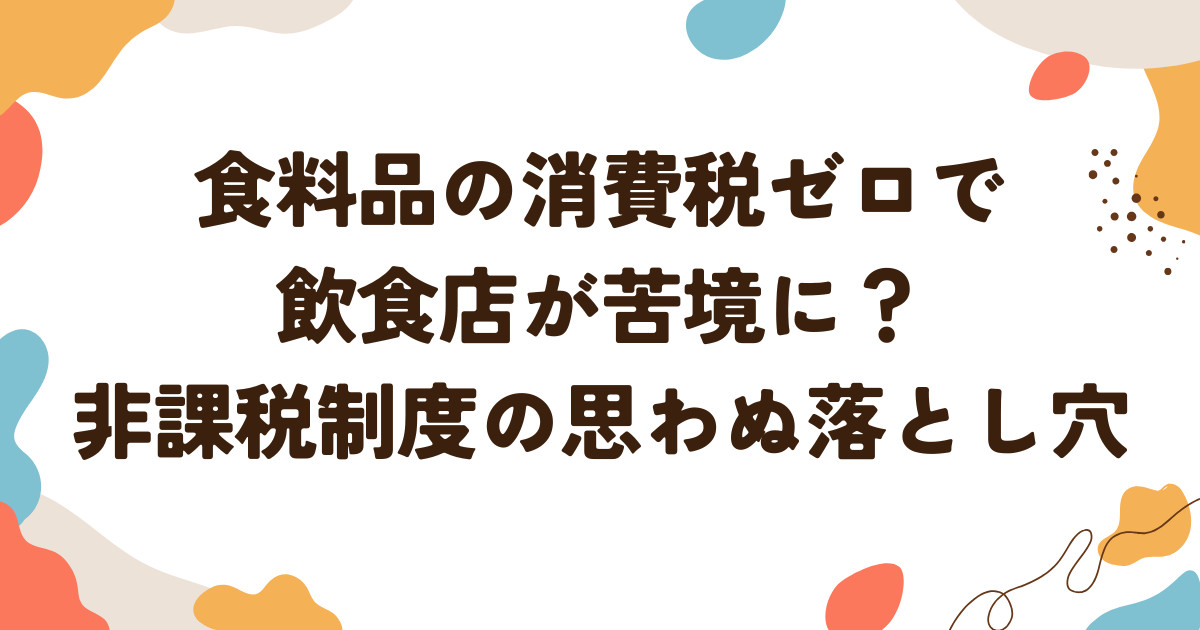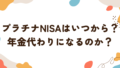物価高に苦しむ家計を救う施策として、「食料品の消費税をゼロにする」案が注目を集めています。立憲民主党や日本維新の会などが掲げるこの政策は、確かに買い物をする一般消費者には歓迎されるでしょう。
しかし、その一方で、飲食業界や中小企業、とりわけ個人経営の飲食店にとっては、経営に深刻な影響を及ぼしかねない“落とし穴”が潜んでいるのです。
消費税減税をめぐる現状と議論の焦点
2025年現在、政府は消費税について「全世代型社会保障制度を支える重要な財源」と位置づけており、「税率を引き下げることは適当ではない」との立場を維持しています。しかし、与党内からも減税を求める声は高まりつつあります。
自民党の参議院議員を対象としたアンケートでは、約8割の議員が消費税減税を支持しているようです。さらに、連立を組む公明党も石破政権に対し、「減税を前提とした経済対策の実施」を要請しており、政府与党内での意見の乖離が注目されています。
こうした中、物価高騰への対策として消費税の見直しを訴える動きが活発になっています。実際、JNNの最新の世論調査でも「食料品の消費税を下げるべき」との回答が最多となっており、国民の間でも減税への期待が高まっていることがうかがえます。
各政党が提案する消費減税
立憲民主党では、泉健太代表が「食料品の非課税も検討すべき」と主張し、物価高騰への対策として消費税の減税を提案しています。ただし、党内では慎重な意見もあり、野田佳彦代表は「減税だけ言っていれば受けはよいと思うが、将来世代にとってプラスになるかどうかというと必ずしもそうではない」と述べ、財源の裏付けがない減税政策に懸念を示しています。
日本維新の会では、吉村洋文代表(大阪府知事)が2025年5月9日の記者会見で「2年限定で食料品の消費税をゼロにすべきだ」と発言しました。吉村氏は、トランプ前米政権による「相互関税」に端を発するスタグフレーション(景気後退と物価上昇の同時進行)を懸念し、「補助金よりも減税による即効性ある対策が重要」と述べています。
国民民主党も「時限的に一律で消費税を5%に引き下げる」ことを提案しており、景気刺激と家計支援を同時に実現する手段として位置づけています。消費の拡大とデフレ圧力の軽減を狙いとし、持続可能な経済成長への橋渡しとしたい意図が見られます。
れいわ新選組の山本太郎代表は、消費税の廃止を最も効果的な経済政策と位置づけています。彼は、消費税が低所得者層にとって大きな負担となっており、消費税を廃止することで年間約22万円、つまり約1カ月分の給料が手元に戻ると試算しています。これにより、消費が活発になり、デフレ不況からの脱却が期待できると主張しています。
外食は10%、テイクアウトは0%?深まる業態格差
もし、食料品が「非課税」扱いになった場合、テイクアウトやスーパーでの購入は消費税0%になりますが、飲食店の店内飲食はこれまで通り10%課税対象のままです。
このため、「同じ食事でも家で食べれば安くなる」という意識が広がれば、店内利用を避ける動きが強まる可能性があります。コロナ禍でテイクアウトが浸透した現在、外食と内食の格差が税制によってさらに広がり、街の飲食店の来客数が激減する恐れがあります。
食料品の仕入税額控除ができない!?
さらに大きな問題は、「仕入税額控除」ができなくなる点です。
通常、飲食店は食材(食料品)などの仕入時に支払った消費税を、売上時に受け取った消費税から差し引いて納税しています。しかし、「非課税」とされた場合、仕入にかかる消費税は控除できず、税負担が増す仕組みになります。これは、利益率の低い中小飲食店にとって死活問題です。
加えて、仕入れのすべてが食材(食料品)だけで完結するわけではありません。光熱費、酒類、備品、外注費、家賃などは引き続き課税対象であり、それらに対する控除ができないのは、大きなコスト増を意味します。
インボイス制度との二重苦、業務負担も増大
現在のインボイス制度では、仕入や売上に関して正確な記録と証明書類が求められます。そこに「課税」「非課税」「軽減税率」など複雑な税区分が加わると、現場では処理の煩雑さが一層増します。とくに小規模な飲食店では、経理負担を自力でこなすケースも多く、人的・時間的コストがかさみます。2019年の軽減税率導入時にも混乱が相次ぎましたが、今回も同様の混乱が再燃する可能性は否めません。
まとめ:一見優しい政策が中小企業を追い詰めるリスクも
「食料品の消費税ゼロ」は、一見すると家計支援の切り札のように見えますが、その裏で多くの飲食店や中小企業にしわ寄せが及ぶ構造があります。公平性と実効性の両立を考えるならば、単なる税率引き下げではなく、現場の実情に即した柔軟な制度設計と、十分な周知・支援が不可欠です。