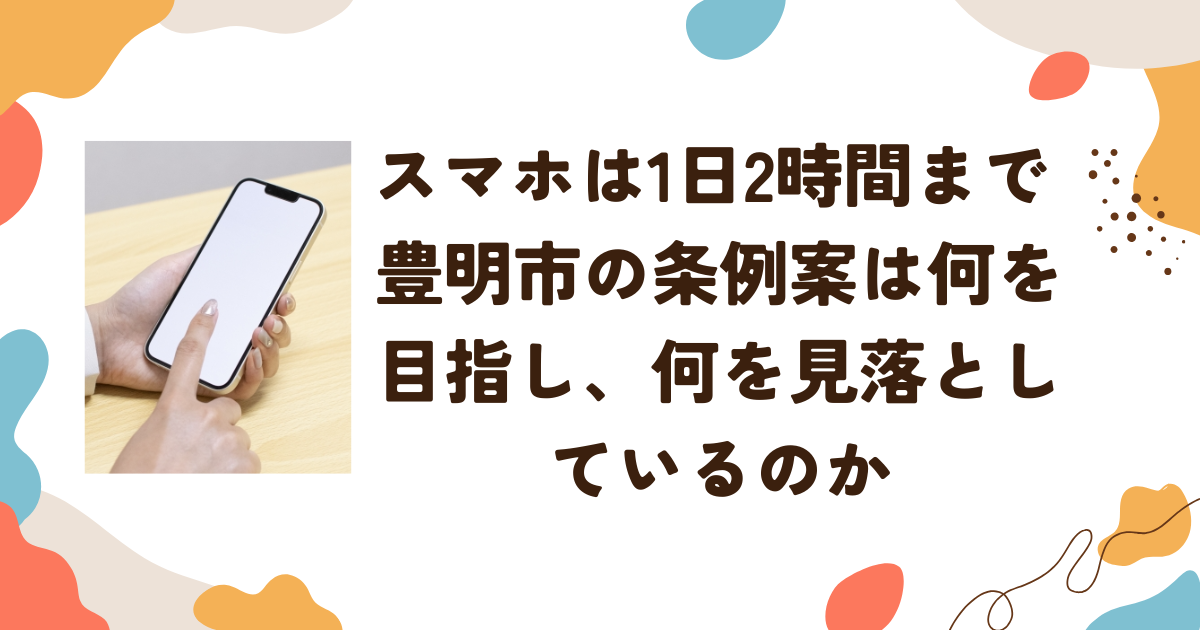愛知県豊明市で、「スマートフォン等の使用を1日2時間以内を目安」とする条例案が9月に提出される見通しだというニュースが話題になっています。対象が子どもだけでなく市民全員に広がる点、そして「スマホ等」にタブレットやゲーム機などネット接続可能な端末まで含める点が、議論を呼ぶ理由でしょう。市の説明では罰則のない推奨型(目安)で、仕事や学習は含めず、あくまで余暇時間における利用抑制をねらうとしています。まずは、事実関係を丁寧に確認しながら、何が論点なのかを整理していきます。
豊明市の条例案――「罰則なし」「余暇の目安」という位置づけ
豊明市は、SNSやゲームの長時間利用に伴う健康・生活リズムの乱れ、家庭内コミュニケーションの希薄化、ネット依存への不安などを背景とし、市民の“意識づくり”を促すために「1日2時間以内」を掲げる方針です。市の公式説明では、
- 対象は市民全体(年齢を問わない)
- 学校や仕事に必要な利用は対象外(余暇時間に限定)
- 罰則は設けない
と明記されています。つまり「法律で縛る」というより「望ましい生活習慣づくりの合図」に近い設計です。
報道各社も「罰則なしの目安」であること、9月提案見通しであることを伝えています。拙速な断罪ではなく、まずは位置づけを正確に理解することが大切です。

「2時間」という数字の由来――小児科医会の“目安”と国際的な議論
日本の小児科領域では、日本小児科医会が長年「メディア接触は1日2時間を目安」という啓発を行ってきました。これは、睡眠・食事・遊び・対話など本来必要な生活時間を圧迫しない範囲としての実務的なガイドで、厳密な医学的“上限”ではありません。近年の啓発資料でも「“目安”として生活に取り入れてほしい」という表現が繰り返されています。
一方、WHOは2019年に5歳未満向けのガイドラインで「座位でのスクリーンタイムは少なめに」と示しましたが、年長児・思春期に関してはコンテンツの質と生活全体のバランスへ目を向けるべきだとする専門家の見解も広く共有されています。固定的な時間カットオフ(「○時間以上は有害」)を裏づける強固なエビデンスはなお限定的、というのが国際的なコンセンサスに近い状況です。
文部科学省も、インターネット・動画視聴と学習状況の関連に関心を持ちつつ、実態や要因は複雑であることを踏まえた資料を公表してきました。単純な「時間=悪」ではなく、何に時間を使っているか(受動的視聴か、創作・学習・交流か)や睡眠・運動・屋外活動が鍵になります。
視力低下は「スマホのせい」だけではない――屋外活動の効果
「スマホ長時間=近視悪化」というイメージは強いですが、研究の蓄積からは屋外活動時間の少なさが重要なリスク要因であることが繰り返し示されています。たとえばJAMAに掲載されたランダム化比較試験では、日中の屋外活動を増やす介入が、小学生の新規発症近視を有意に抑える効果を示しました。“どれだけ外で過ごすか”が、視力保護には大きな意味をもつというわけです。
包括的レビューでも、スクリーンタイムの増加は様々な健康リスクと弱~中程度の関連を示す一方、因果関係は複雑で家族の生活ストレスや睡眠不足、運動不足など他の要因が絡み合うことが指摘されています。「量」だけで全てを説明できない――ここが政策設計の肝です。

先行例・香川県「ゲーム条例」から学べること
国内の先行例としてよく挙げられるのが、2020年に施行された香川県の「ネット・ゲーム依存症対策条例」です。こちらも罰則のない推奨型で、平日60分・休日90分が目安でしたが、科学的根拠の乏しさや効果検証の不十分さを巡り、今も議論が続いています。県議会では第三者評価の必要性や用語の妥当性(「ゲーム依存」→「ゲーム行動症」)などが論点化され、エビデンスに基づく検証(EBPM)の重要性が改めて浮き彫りになりました。
海外の動向――中国の“強力な未成年規制”は参考になるのか
中国では、未成年のオンラインゲームを週3時間(金・土・日20~21時)に制限するなど、国家主導の強い規制を導入しています。背景には依存対策に加えて、オンライン空間の統制や未成年保護といった政策目的が絡みます。日本の地方自治体が採るべきアプローチとしてそのまま輸入するのは難しく、“社会的・政治的コンテクスト”の違いを踏まえた慎重な参照が必要です。
中国以外のスマホ・ゲーム規制の動向
世界では子どもや若者を中心に、スマホやゲームの使い方を制限する動きが広がっています。
- フランス:2018年から義務教育世代の学校でスマホ使用を全面禁止。3歳未満の子どもにはスクリーン禁止を提言し、15歳未満のSNS利用には保護者の承認を義務づける法整備も進めています。
- スウェーデン:公衆衛生機関がガイドラインを出し、2歳未満はスクリーンなし、学齢期の子どもでも最大2~3時間までを推奨。
- オーストラリア:16歳未満のSNS利用を法律で禁止する方針。違反したプラットフォームには高額の罰金を科す仕組みです。
- イギリス:オンライン・セーフティ法で子どもに有害なコンテンツ対策を義務化。SNSの利用時間を制限する制度も検討中。
- 韓国:かつて16歳未満は深夜0~6時のオンラインゲームを禁止する「シャットダウン法」を実施しましたが、2021年に廃止されています。
スマホは悪か?―“時間の長短”より“使い方の質”へ
最新の知見は、画面を見ている“時間そのもの”よりも“何をしているか(質)”が子どもの発達やウェルビーイングに与える影響が大きいことを示唆します。創作・学習・協働的な活動は自己効力感やスキルを高めやすい一方、受動的・反復的な視聴は睡眠や運動の時間を奪いがちです。家族や学校でのルール設計は、単なる「総量規制」よりも生活リズム・睡眠・運動・屋外時間の確保とセットで考えると整合的になります。

まとめ――「時間で縛る」から「暮らしを整える」へ
「スマホは悪か?」という問いに、白黒の答えはありません。私たちが向き合うべきは“時間そのもの”ではなく“暮らしの全体設計”です。
- 睡眠・食事・運動・屋外時間・家族の会話を土台に置く。
- そのうえで、創造・学習・協働につながる“良質なデジタル”を伸ばす。
- そして、実態を計測し、結果を公開し、改善する(EBPM)。
豊明市の条例案は、市民対話のきっかけとして意味を持ち得ます。もし本当に健康や学び、コミュニケーションを良くしたいのなら、目安の掲示にとどまらず、上に挙げた支援と検証を伴う包括的なアプローチへ踏み出すべきです。それは「ハイテク機器=悪」という単純な図式から離れ、テクノロジーを生活の味方にするための遠回りに見えて、実は最短の道なのだと思います。