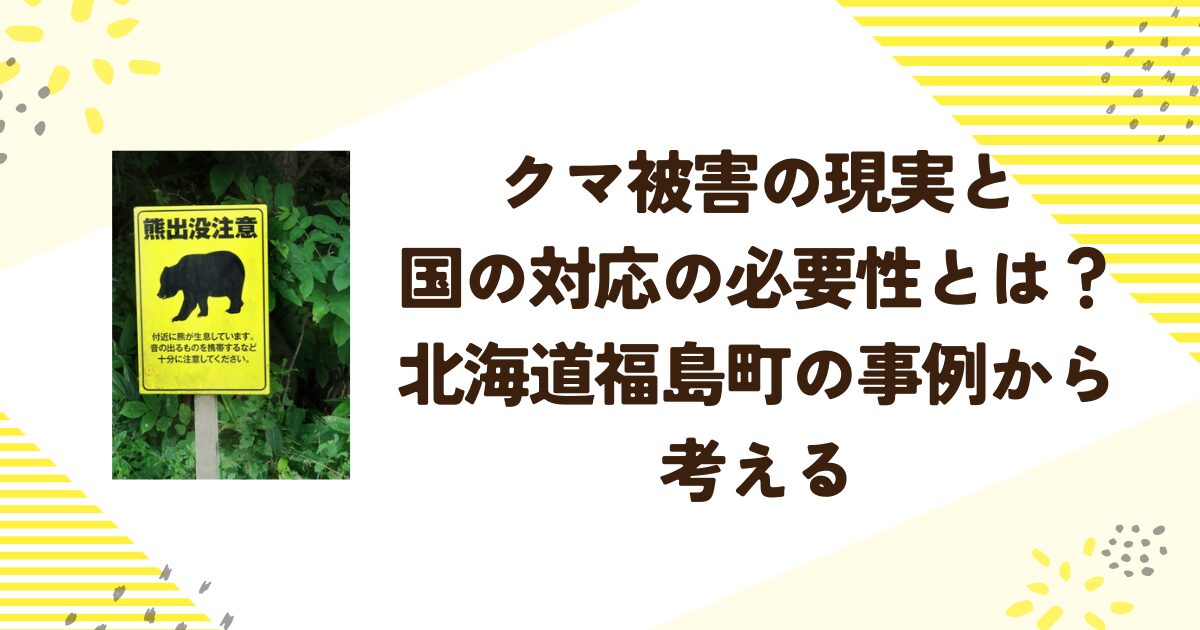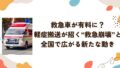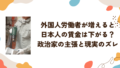近年、クマ被害が全国で多発しています。特に2025年7月、北海道福島町で起きた新聞配達員の男性がヒグマに襲われ死亡する事件は大きな衝撃を呼びました。
北海道福島町でのクマ被害:駆除されるももう1頭いるか
被害が発生したのは7月12日早朝。福島町で新聞配達中だった52歳の男性が、クマに襲われ命を落としました。遺体は草むらで発見され、100メートル以上引きずられた形跡がありました。
福島町では事件後、警戒態勢を強化し、地元猟友会の協力でヒグマの駆除に乗り出しました。7月18日には体長2メートルを超える大型のヒグマ1頭が駆除されました。
DNA分析の結果、2021年に同町内で77歳の女性を襲い死亡させたクマと同一個体であることが判明しました。
なぜ住宅街で発砲できたのか
北海道福島町でのクマ駆除では、住宅街での発砲という異例の措置がとられましたが、これは緊急時に限り警察の命令によって発砲が許可される法的根拠に基づくものでした。
通常、市街地での猟銃使用は法律で原則禁止されていますが、過去にも札幌市内で同様のケースがあり、命の危険が差し迫った状況下で例外的に発砲が実施された前例があります。
さらに、2025年9月からは改正鳥獣保護管理法が施行され、市町村長の判断で、クマやイノシシが生活圏に侵入し危険があると認められた場合には、ハンターによる発砲(緊急銃猟)が可能となります。
この法改正により現場での対応は迅速化されると期待される一方で、実際には安全確認やチェックリストの遵守が求められるため、時間を要するという懸念もあります。そのため、緊急時に即応できるよう、事前に行政とハンターの連携体制を整えておくことが重要だと指摘されています。

消えないクマ被害リスク
また、今回駆除されたクマの他にも福島町周辺には複数のクマが存在している可能性があり、今後も警戒を怠ることはできません。
クマは明確な縄張りを持たず、複数の個体が同一地域を利用することもあるため、一頭を駆除したからといって被害リスクが消えるわけではないのです。むしろ強い個体がいなくなることで、他のクマが市街地に接近しやすくなる恐れもあります。
こうした状況の中で、専門家は「日常が脅かされている地域住民だけでなく、自分の地域は関係ないという思い込みを捨て、全国の人々が人とクマとの適切な距離感を再認識する必要がある」と警鐘を鳴らしています。人間の生活と野生動物の共存には、法律・対策・意識のすべてにおいてバランスある姿勢が求められているのです。
苦情電話が相次ぐ
福島町でのクマ駆除をめぐり、1週間で50件以上の苦情電話が町に寄せられました。「クマを殺すな」「駆除の判断基準は何か」といった内容が多く、そのほとんどは町外からのものでした。
町の担当者は「市街地にクマが出没しており、住民の安全を最優先にした対応だ」と説明していますが、野生動物保護の観点と安全確保の間で葛藤が続いています。
クマ駆除に反対する声の背景には、倫理的・環境的・社会的な理由があります。特にSNSで拡散される駆除されたクマの映像や写真に対し、感情的な反発が強まっていることが目立ちます。
また、「クマが人里に現れるのは人間の生活圏の拡大が原因であり、人間側にも責任がある」という考え方も根強いです。さらに、安易な駆除は生態系全体に悪影響を及ぼす恐れがあり、群れの秩序が崩れることで若いクマがより大胆に人里に出没し、かえって被害が増える「逆効果」も指摘されています。駆除だけでは餌不足や里山の放置といった根本問題を解決できないため、総合的な対策が必要だという声が強まっています。

クマ被害が増えている背景
なぜ今、クマが人里に頻繁に出没するようになっているのでしょうか。その背景にはいくつかの要因があります。
- 山林の餌不足
気候変動や山林の劣化によって、クマが本来生息する森の中で十分な食料を確保できなくなっています。特にドングリやクリなどの堅果類が不作の年は、クマの出没が急増します。 - 人間の生活圏への依存
生ゴミや家庭菜園、果樹園など、人間の生活圏に近い場所にある「餌」がクマを誘引します。人間に対する警戒心が薄れ、生活圏に入り込むクマが増えています。 - クマの個体数増加
狩猟人口の減少と保護政策の影響で、近年クマの個体数が増加傾向にあります。個体密度の上昇が縄張り争いや人里への流入を引き起こす要因ともなっています。
クマ被害対応自治体だけでは限界
こうした事態に対して、各地の自治体が対応を強化しているものの、限界があるのが現実です。出没エリアが広域にわたることや、自治体ごとの財政・人員の差、さらに専門知識を持ったハンターの高齢化と減少など、対応のバラつきが問題になっています。
そこで必要とされているのが「国としての包括的な対策」です。
クマ被害に対する国の動きと今後の課題
政府は2024年から2025年にかけて、クマ被害への対応を強化する法整備と施策を進めています。
- 鳥獣保護管理法の改正により、市街地でも市町村長の判断で「緊急銃猟」が可能に
- ヒグマ・ツキノワグマを「指定管理鳥獣」に指定し、夜間の捕獲や予防的管理が可能に
- ヒグマ対策パッケージ2024の策定。電気柵の設置支援、科学的データに基づいた出没予測などを盛り込んでいます
しかしながら、まだ十分とはいえません。今後さらに必要とされる対応は以下の通りです。
- ハンターの若年層育成と制度整備
- ドローンやAIによる監視・追跡の導入支援
- 国民への正確な情報発信と教育(過剰な「クマ殺すな」論への理解促進)
- 地域間連携を促進する中央組織(クマ対策庁など)の創設
- 捕獲個体のDNAデータベース化など科学的管理の拡充

命を守るために私たちにできること
最前線で対応する自治体や猟友会、研究機関の努力だけでは、被害を完全に防ぐことはできません。クマ被害を防ぐためには、私たち一人ひとりが「山菜採りや登山時の鈴の携帯」「ごみ出しの時間厳守」「目撃情報の共有」など、基本的な行動にも注意を払う必要があります。
また、「クマを殺すな」という声が感情的に語られるのではなく、現場の危険性や住民の不安、そして科学的管理の重要性を理解した上で発言されることが、今後の冷静な議論と対策に不可欠です。
北海道福島町で起きたクマによる死亡事件は、単なる一地域の出来事ではなく、今後全国的に起こり得るリスクを象徴しています。再発を防ぐためには、自治体任せにせず、国が中心となって法制度・科学・教育のあらゆる面から支えることが求められています。
自然との共生と、安全な暮らしは両立できるのか。今こそ、社会全体でその解決策を考えるときです。