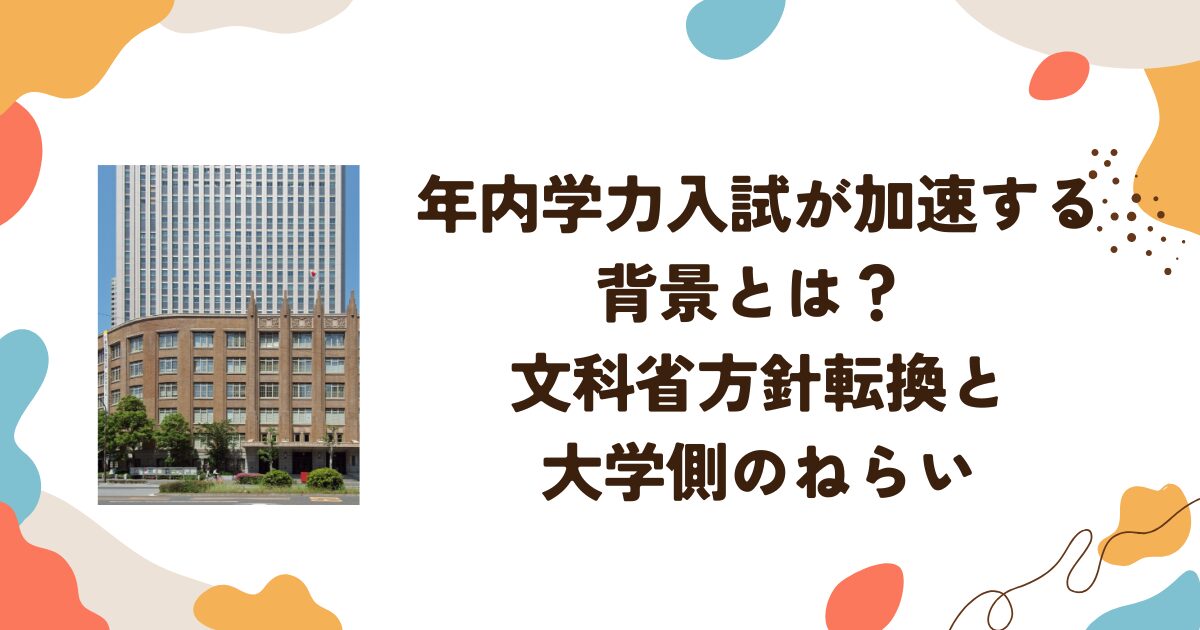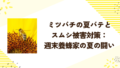2025年度から、首都圏の私立大学で年内学力入試を新たに導入する大学が拡大しています。
文部科学省の制度変更を背景に、今年度、首都圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)の私立大学194校中、23校が学力試験を課す年内入試を新設しました。昨年度から実施している14校と合わせ、首都圏私大の約2割が年内学力入試を導入する見込みです。
年内学力入試が容認されるに至った背景
これまで、大学入試における学力試験は、文部科学省が定めたルールに基づき「2月1日以降」に実施することが原則とされてきました。これは、特定の大学が高校の教育活動に過度な影響を及ぼさないようにするための措置であり、総合型選抜(旧AO入試)や学校推薦型選抜では、面接・小論文・調査書などを活用し、学力以外の観点から評価することが求められていました。
しかし、実際には関西圏を中心に一部の私立大学で、こうしたルールに反して年内に事実上の学力試験を課す選抜が広く行われており、その動きが次第に首都圏にも波及しました。とくに2025年度入試では、東洋大学が正式に年内学力試験を導入したことで、首都圏の大学にも同様の動きが広がりました。

その背景には、大学側が少子化に伴う受験生の減少を見据え、より早期に優秀な学生を確保したいという思惑があります。とくに中堅私大では、総合型や推薦型だけでは学力の担保が難しく、「ある程度の基礎学力も確認したい」との現場の声が強まっていました。また、受験生にとっても早い段階で進路が決まることが精神的な安定につながるという利点があるため、一定のニーズも存在していました。
こうした大学側・受験生側の実情を受け、文部科学省は2025年6月に公表した「令和8年度大学入学者選抜実施要項」において方針を転換。小論文や面接、志望理由書などとの併用を条件に、年内の学力試験実施を条件付きで容認することとしました。これは、現場の実態に即した柔軟な対応を取りながらも、高校教育への過度な影響を抑制するための“妥協点”とも言える措置でした。
年内学力入試と通常スケジュールとの比較
一般選抜(従来)
- 共通テスト:1月中旬(2026年度は1月17・18日予定)
- 個別学力検査(大学独自試験):2月1日〜3月下旬
年内入試:総合型・学校推薦型
- 総合型選抜:9月1日以降出願開始、試験日:10月上旬から11月中旬頃
- 学校推薦型選抜(公募推薦含む):11月1日以降出願開始、試験日:11月中旬から12月中旬頃

なぜ大学側は「年内学力入試」を導入するのか?大学の狙い
早期に志願者を確保し、入学者数を確定したい
少子化の影響で、大学間の受験生確保競争が激化しています。年内入試によって志願者を早期に確保でき、経営の見通しが立てやすくなります。
書類・面接中心だった年内型の選抜に「学力試験」を加えたいというニーズ
大学側からは「本当に入学後に必要な学力を把握したい」という声が強く、文科省も面接や小論文などの評価手法と組み合わせる条件で容認しました。
関西圏ではすでに慣行化しており、首都圏でも「追随」の流れ
近畿大学、龍谷大学、京都産業大学などでは以前から年内学力入試(基礎学力テスト型)が広く行われ、首都圏でも同様の導入が時間の問題でした。
東洋大学は2025年度入試で、英語+国語または英語+数学の2教科基礎学力試験型の公募制推薦を実施し、約2万人の志願者を集め、大きな成功を収めました。
年内学力入試を導入する大学の具体例
- 東洋大学:25年度より「英語+国語」または「英語+数学」の基礎学力テスト型公募制推薦を実施し、大規模志願者を集めた。26年度からは制度を整理し総合型選抜(一部書類や小論文も併用)に変更予定。試験会場も全国に拡大予定。
- 昭和女子大学:26年度から「公募制推薦入試 基礎学力テスト型」を導入予定。11月に全国4会場で試験、12月に合否発表。英検スコアに応じて英語試験免除や換算も可能。
- 関東学院大学:25年度から総合型選抜に「基礎学力評価型」を設け、26年度も継続。書類審査+基礎力テスト(高校2年までの基礎範囲)+面接で選抜。併願も可。
首都圏ではほかに、立正大学、拓殖大学、大妻女子大学、玉川大学などが基礎学力テスト型の年内入試導入を予定しており、急速な広がりが予想されます。
年内学力入試のメリットとデメリット
メリット
- 受験機会が早まる:「可能性を早期に確保」「安心して高校生活後半を過ごせる。
- 受験科目が絞られている(例:2教科のみ)ため、準備の焦点化と効率化が可能/英検スコア等を活用できる大学もある。競争率が分散されることで、本命対策に時間を割ける/滑り止めとして有効。大学側の利点:志願者・合格者数の早期確保、広域募集の拡大、定員管理の安定性向上。
デメリット・懸念点
- 高校教育への影響:年内入試が高校3年の学習時間を圧迫し、カリキュラムや学力養成を阻害する恐れが指摘されています。
- 浅い進路選択:慎重な進路検討の前に決断を迫られるリスクあり。形式偏重・名ばかり推薦の批判:少科目・書類中心で「簡単に合格できる推薦」となり、選抜の質が低下する危惧もあります。費用負担:年内の受験料や合格後の入学金前納など、経済的な負担増要因もある(例:東洋大学などは3万5千円+入学金前納)。受験モチベーション維持の問題:早期合格でその後の勉強意欲が低下し、学力停滞につながるケースも。
年内学力入試の今後の展望と高校側への影響
文科省の調整に注目
年内学力入試の拡大について、文科省と高校・大学間の連携がカギになります。今後、入試要項の変更や高校現場への配慮が求められています。
高校現場の対応が重要に
高校側は、年内入試対応によって3年次の学習指導計画が圧迫される懸念を抱えています。特に、進学指導と高校教育の両立のための実践的なサポート体制整備が求められています。
受験生・保護者への情報提供強化
年内学力入試の形式や費用、合格後の扱い(併願可否、辞退の可否)など、具体的情報を丁寧に開示することが不可欠です。大学側も募集要項で明確にする必要があります。
多様な入試制度の展開・整備
今後は、筆記試験だけでなく多面的評価を重視した選抜制度のさらなる整備が期待されます。「学力の三要素」(知識・技能、思考力・判断力、主体性・多様性・協働性)を総合的に評価する方向性にも注目です。
変わりゆく大学入試、高校3年生の学びと進路選択への影響
- 首都圏の私立大学で年内に学力試験を実施する入試制度が急速に拡大中で、今後も広がりが予想されます。
- 大学にとっては志願者確保や制度の多様化につながる一方で、高校側からは「教育の質や学力育成への影響」を懸念する声が強まっています。
- 受験生や保護者にとっては、メリット(早期進路決定・準備の焦点化・複数受験機会)とデメリット(経済的負担・進路の浅慮・学習意欲の低下)を十分検討した上で、自分に合った選択をする必要があります。
- 高校と大学、そして文科省が協調して透明性と公平性を確保しつつ、多様な選抜方法を整備していくことが、これからの入試制度改革の鍵となるでしょう。