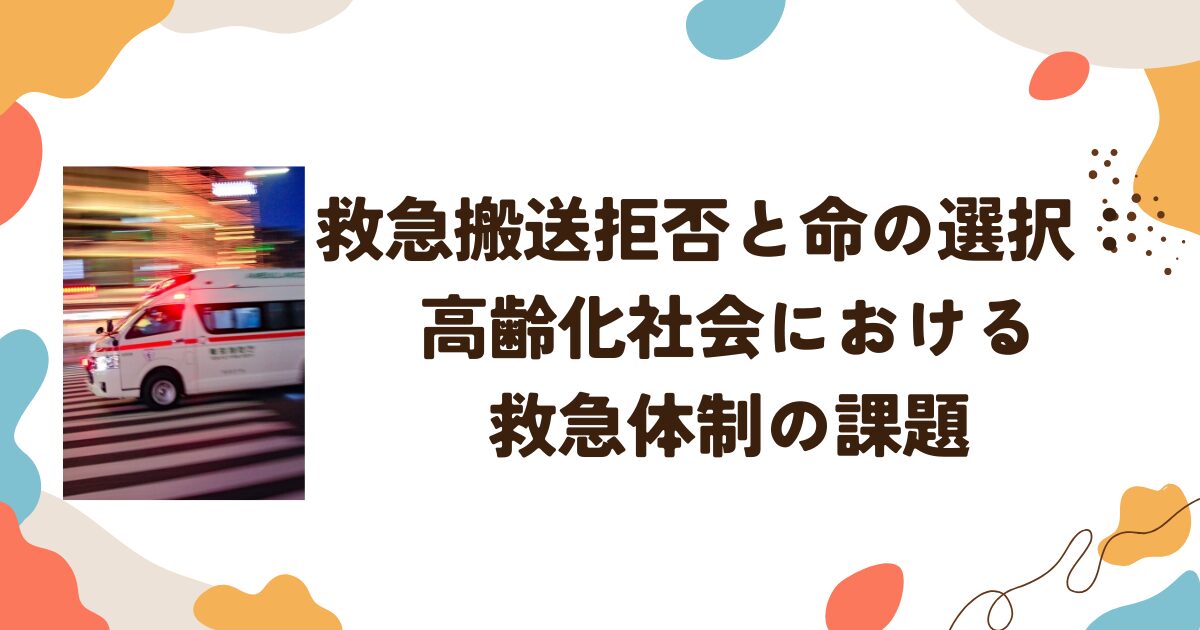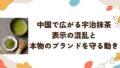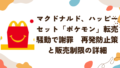2025年7月29日、静岡県掛川市で起きたある悲劇が明らかになりました。50代の男性が体調不良を訴えて119番通報したものの、救急車が出動せず、5時間半後に心肺停止状態で発見され、死亡が確認されたのです。
なぜ、救えるはずの命が失われてしまったのか?
この事例は、日本が直面する超高齢化社会において、救急体制が抱える深刻な課題を浮き彫りにしています。本記事では、事件の経緯や背景を深掘りし、同様の悲劇を防ぐために私たちに何ができるのかを考えます。
事件の経緯:なぜ救急車は出動しなかったのか
この痛ましい事件は、通報時の指令員の判断ミスから始まりました。
最初の通報があったのは、2024年10月15日の午後5時25分頃。男性の母親から「2日間ほど動けず、足が痛い」との連絡がありました。しかし、対応した指令員は「緊急性は低い」と判断。さらに、家族から「サイレンを鳴らさずに来てほしい」という要望や搬送先の指定があったため、救急車ではなく介護タクシーの利用を勧めてしまったのです。
約5時間半後、再び母親から「容体が悪化し、もうほとんど動かない」との通報が入りました。急いで救急車が出動したものの、男性はすでに心肺停止状態。病院で死亡が確認されました。
後の報告書で、指令員は「緊急ではないという先入観にとらわれた」「容体を詳細に聴取すべきだった」と反省を述べています。この言葉は、私たちに多くの教訓を与えています。

超高齢化社会が救急対応を難しくする3つの理由
日本の救急搬送の多くは、65歳以上の高齢者が占めています。しかし、高齢者の救急対応には特有の難しさがあります。
- 症状の訴えが不明瞭になりがち 高齢者の中には、体調不良や痛みをうまく言葉で表現できない人や、遠慮して症状を控えめに伝える人が少なくありません。そのため、電話口での聞き取りが不十分だと、重篤な病気を見過ごしてしまうリスクがあります。
- 先入観による誤判断 「高齢者だから仕方ない」「持病があるから緊急ではない」といった先入観が、指令員の判断に影響を及ぼすことがあります。今回の事例でも、指令員が「緊急ではない」と思い込んでしまったことが悲劇につながりました。
- 搬送拒否への対応不足 「家族に迷惑をかけたくない」「お金がかかるから」といった理由で、本人や家族が救急車の搬送を拒否するケースも多く見られます。しかし、説得できる体制やマニュアルが不足している現状があります。
類似事例から見る、全国で起こりうる救急の課題
今回の静岡の事例は、決して特別なものではありません。全国各地で同様のケースが報告されています。
- 茨城県つくば市:高熱で震える3歳児を救急隊が「けいれんではない」と判断し搬送せず。後に急性脳症と診断され、重度の障害が残りました。
- 埼玉県本庄市:交通事故で頭部を負傷した74歳男性が搬送を辞退。その後、公園で倒れ死亡。死因は頭部骨折でした。
これらの事例は、救急の初期判断がどれほど難しいか、そしてたったひとつの判断ミスが取り返しのつかない結果を招く可能性があることを示しています。

命を守るために必要な4つの改善策
では、このような悲劇を二度と繰り返さないためにはどうすればよいのでしょうか。
- 電話トリアージの全国標準化 重症度や緊急度に応じて治療の優先順位を決めるトリアージを、電話対応にも導入・全国標準化することで、救急車の適正出動と重症者の見逃しを防ぐことができます。
- 聞き取りマニュアルと研修の充実 高齢者や子どもの症状を正確に把握するための詳細な問診項目を標準化し、すべての指令員が定期的に訓練を受ける体制を整えることが不可欠です。
- 搬送拒否への説得体制の強化 「迷惑をかけたくない」といった理由で搬送を断る人に対し、命を守るために強く説得できる体制やマニュアルを整備する必要があります。
- 住民への啓発活動 緊急時に、家族が何をどう伝えれば適切な対応を受けられるのか。平時から地域全体で周知し、住民の救急に関する知識を向上させることも重要です。
救急隊に求められる説得力
また、救急搬送の現場では、傷病者やその家族が搬送を拒否するケースが少なくありません。多くの場合、その背景には「家族に迷惑をかけたくない」「お金がかかる」といった、本人の命に関わる判断を鈍らせる要因が潜んでいます。
このため、救急隊員はただ意思を尊重するだけでなく、現場の状況を総合的に判断し、搬送の必要性を強く説得することが求められます。特に高齢者や子ども、精神的なショックを受けている方などは、自身の状態を正確に伝えられないことが多く、一見軽症に見えても、後に重篤化するリスクを素人が判断することは困難です。
こうした課題に対応するためには、搬送の必要性を客観的に判断するためのチェックリストや、具体的な説得方法、記録と報告の手順などを盛り込んだマニュアルを整備し、定期的な研修を通じて隊員のスキルを向上させることが不可欠です。これにより、搬送判断の質の向上と、それに伴う悲劇の防止に繋がることが期待されます。

まとめ:救急対応は、社会全体で取り組むべき課題
今回の静岡の事例は、救急隊や消防だけの問題ではなく、社会全体で命を守る仕組みをどう作るかという、私たち一人ひとりに突きつけられた課題です。
- 丁寧な問診
- 先入観の排除
- 説得力のある搬送促進
- 住民への教育
これらの取り組みを通じて、救急の質を高めていく必要があります。