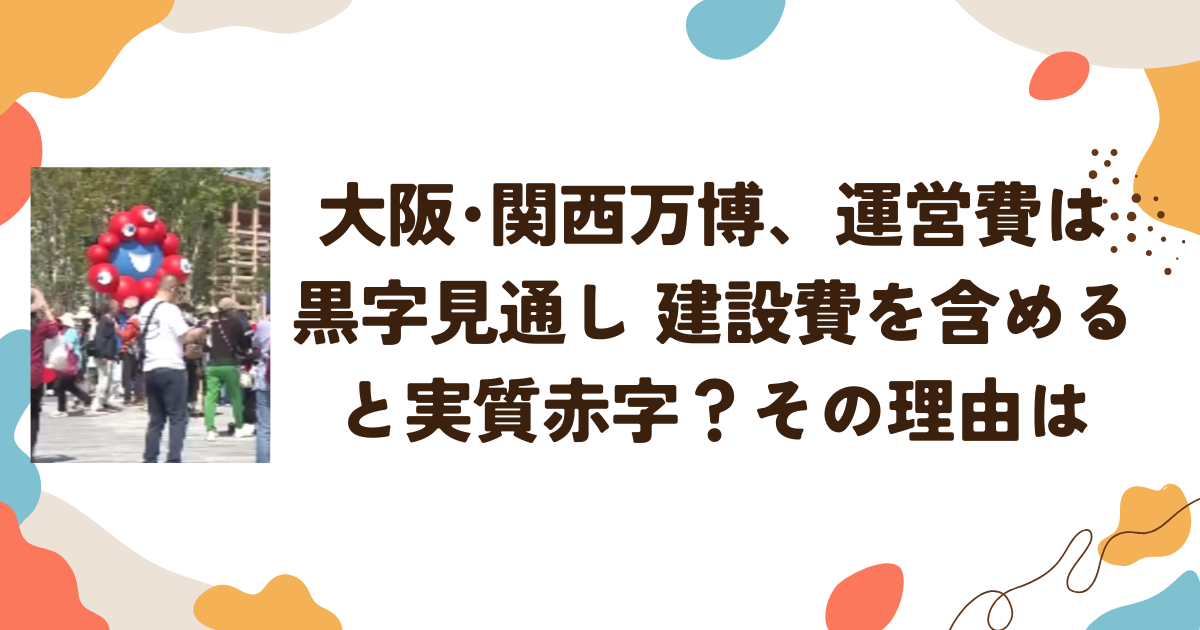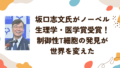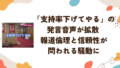2025年4月から開催されている 大阪・関西万博2025。閉幕が迫る中、運営する日本国際博覧会協会から「230億〜280億円の黒字見通し」との発表がありました。
このニュースを聞いて「え、あれだけ建設費が膨らんだのに黒字なの?」と思った人も多いはずです。
実はこの“黒字”には重要な前提があります。今回は、万博の収支構造を整理しながら、なぜ黒字とされているのか、その背景と注意点をわかりやすく解説します。
万博が黒字見通しと言われるのは「運営費ベース」
まず結論から言うと、今回の黒字見通しは 「運営費だけを対象とした黒字」 です。
つまり、会場建設費や撤去費、インフラ整備などの巨額な費用は含まれていません。
運営費とは?
運営費とは、万博を実際に動かすための費用のことです。
人件費・警備・清掃・イベント開催・広報・電気代などがこれにあたります。
大阪・関西万博の運営費は 約1,160億円。
この費用を、チケット販売や協賛金、グッズ販売、出展料などの収入でまかなう形になっています。
黒字見通しの根拠:チケット売上が好調
万博協会が黒字見通しを発表できた理由のひとつは、入場券の売れ行きが想定を上回っている ためです。
- 損益分岐点とされた入場者数:1,800万人
- 現時点で販売済み入場券:約1,900万枚以上
- チケット収入:約1,000億円超
さらに、会場内の飲食・グッズ販売からの納付金(売上の一部)も上振れし、当初予算より30億円以上多い収入が見込まれています。
また、経費削減努力により最大50億円の費用抑制も実現できる見通しです。
こうした積み上げの結果、運営費ベースで230〜280億円程度の黒字が見込まれているのです。
一方で、建設費や撤去費は「別会計」
ここで注意したいのが、今回の黒字発表はあくまで「運営だけ」での話ということです。
万博全体でみると、実は建設・撤去・インフラ整備などの費用が別に存在します。
会場建設費:2,350億円
万博会場を建てるための費用は 約2,350億円 にのぼります。
当初1,850億円の予定から、資材高騰や人件費上昇によって約500億円上乗せされました。
この建設費は、国・大阪府・経済界が3分の1ずつ負担する形です。
関連インフラ費用:数千億円規模
夢洲(ゆめしま)へのアクセス道路、鉄道延伸、港湾整備などの公共インフラにも巨額の投資が行われています。
日本総合研究所の試算では、関連整備費を含めると 7,000億円〜1兆円規模 に達する可能性もあるとされています。
撤去・解体費用も今後発生
会期終了後は、パビリオンや仮設建物の撤去、整地、環境回復などに大きな費用が必要です。
協会自身も「最終的な決算は2028年3月の協会解散時に確定する」としています。
通常のイベントでは「建設費・撤去費」も含めて収支計算
一般的な大型イベント(たとえば五輪や博覧会)では、建設費や撤去費を含めたトータルの収支で「黒字・赤字」を判断します。
たとえば:
- 東京オリンピックでは、運営費だけでなく競技場建設や交通整備も含めた総費用を集計。
- ドバイ万博や上海万博も、建設・撤去を含む「全体プロジェクト」として評価されました。
そのため、「運営費だけが黒字」という報道は、一部だけを切り取った数字という見方もできます。
吉村洋文大阪府知事も「運営黒字を強調するのは誤解を招く」と発言しており、報道の見せ方には注意が必要です。

なぜ「運営費ベース」での黒字が発表されたのか
大阪・関西万博の「黒字見通し」は、会場建設費や撤去費を除いた“運営費だけの試算”に基づいています。
この形式が採用された理由は、主に以下の3点にあります。
① 建設費は国・自治体が負担、運営費は協会が管理しているから
大阪・関西万博の費用構造は大きく分けて次の2つです。
- 建設・整備費:国・大阪府・大阪市などの公費負担(約2350億円規模)
- 運営費:日本国際博覧会協会(民間・入場料・スポンサー収入など)
つまり、運営費と建設費では予算の出所と会計主体が異なるため、協会が直接管理している「運営部分」だけを独自に収支計算できる仕組みになっています。
そのため、協会としては「自分たちが責任をもつ範囲では黒字化できる見通し」と公表することが可能なのです。
② 財務面での「安心感」を示す狙い
建設費の増大や開催準備の遅れが相次ぐなか、世論では「本当に開催できるのか」「税金の無駄ではないか」という批判も強まっていました。
こうした空気を払拭するため、協会が「運営自体は健全に回る」というメッセージを打ち出すことで、スポンサー企業や入場券販売への信頼感を高める狙いがあると考えられます。
③ 会計処理上、運営と建設を混ぜると「黒字・赤字」が見えにくくなる
建設・解体費用は数年にわたる公共投資であり、減価償却や国・地方の補助金処理が絡むため、年度ごとに「黒字・赤字」を単純に算定できません。
そのため、国際博覧会の運営では慣例的に、「運営収支」と「建設関連支出」を分けて報告するケースが多く、今回もそれに倣った形です。
黒字は喜ばしいが「全体黒字」とは限らない
確かに、運営費ベースでの黒字化は快挙です。
しかし、万博全体の財政を考えると、まだ楽観はできません。
- 会場建設やアクセス整備を含めると、全体としては赤字の可能性が高い
- 撤去・再開発費を差し引くと、実質的な黒字は小さい
- 将来的な維持管理(例:大屋根リングを一部残す計画)の費用も必要
つまり、「運営が黒字=万博全体が黒字」ではないのです。
黒字確定までに残る「不確実性とリスク」
また、「黒字見通し」とはいえ、確定までには次のような不確実性・リスクが残されています。
- 想定外の追加支出(天候の影響、災害対応、補修・保守など)
- 入場券の払い戻しやキャンセル対応
- 運営後半期での来場者減少
- 会場撤去・解体費用、残存施設維持費用などの後工程コスト
- 会計処理上、想定外支出が出た場合の影響
こうした点を踏まえ、協会も慎重な姿勢を崩していません。実際、「黒字額が確定するのは会場解体などを含め、協会が解散する2028年3月末以降」と説明しています。
黒字分はどう使われる? “レガシー”への期待
協会によれば、黒字分(剰余金)は単なる利益ではなく、今後の地域や技術発展に活かす方向で検討される予定です。
具体的には:
- 万博の象徴「大屋根リング」の一部を残し、地域の観光拠点に活用
- 科学技術・環境関連のプロジェクト支援
- 万博の成果を検証する研究基金の設立 などが検討されています。
吉村知事も「黒字を維持管理費に充てるのが現実的」と述べており、“レガシー(遺産)”をどう残すかが今後の焦点となります。
黒字は「前向きな結果」だが
今回の 大阪・関西万博の黒字見通し は、入場券の売れ行き好調や運営の効率化による明るいニュースです。
しかし、それはあくまで運営費ベースの黒字に過ぎません。
建設・撤去・インフラ整備を含めた「全体の採算」で見れば、依然として慎重な判断が必要です。
建設費や解体費用を別勘定にする報道は、一般市民に「万博はもう成功した」と誤解を与える可能性もあります。大阪・関西万博は、経済波及効果や観光誘致の面でも注目される一大国家プロジェクトです。だからこそ、単なる“黒字発表”だけでなく、総合的なコスト評価と透明性のある財務報告が求められます。