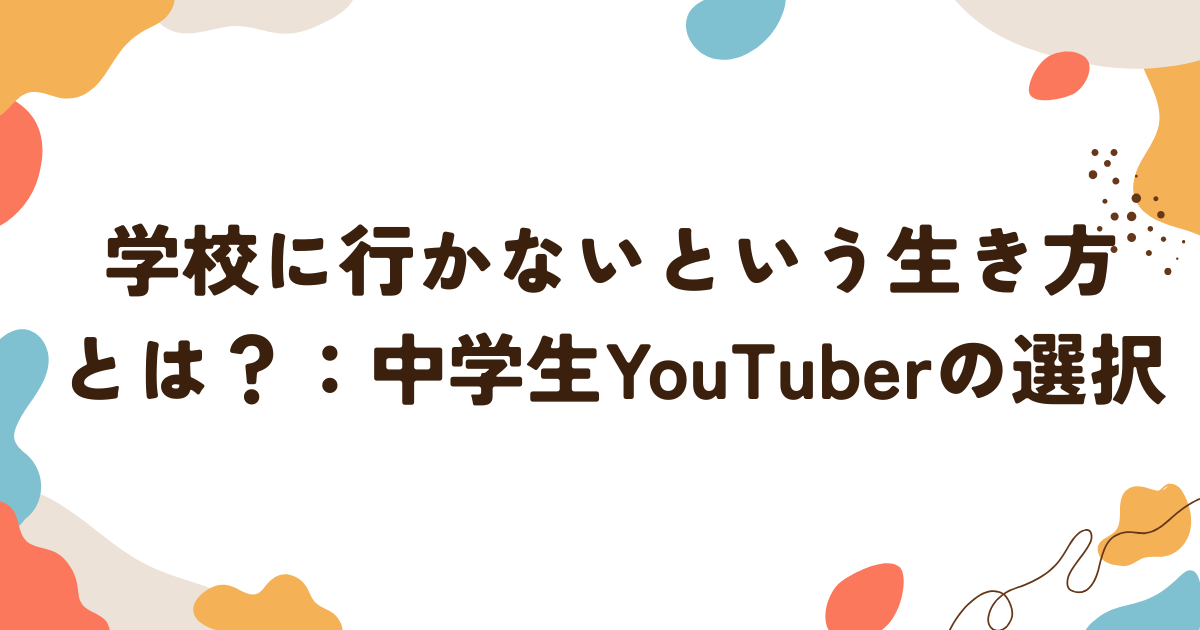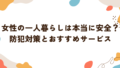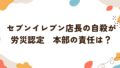子どもが中学生になると、自然と「学校に通うのが当たり前」という意識が根づいている家庭が多いことでしょう。しかし年、「学校に行かない」という選択をする家庭もあります。
その中でも注目されているのが、小学生時代から人気を集めてきたYouTuber、Tarou(たろう)さんの事例です。彼の生き方を通して、教育や進路についてあらためて考えてみましょう。
小学生YouTuber・Tarouさんのプロフィール
- 名前:Tarou(たろう)
- 年齢:12歳(2024年時点)
- 活動:YouTubeでフォートナイト実況、ライブ配信
- チャンネル登録者数:約19万人
- 目標:プロゲーマーとして世界大会出場・優勝
- 学歴:インターナショナルスクール → 公立小学校 → 中学校は通わず在籍のみ
- 居住地:かつては東京都青山、現在は山奥の村に移住
- 家族構成:両親と弟2人。両親は高学歴でリモートワーク中心の生活
Youtubeチャンネル:たろうチャンネル

Tarouさんは、現在中学生の年齢ながらも学校には通っていません。その代わりに、自宅でゲームの練習と自主学習を中心に生活を組み立てています。
肯定的な意見:子ども主体の学びを尊重
このような選択に対し、肯定的な声も多くあります。
「学力は後からでも取り戻せる。今しかできないことに集中すべき」「子どもに地頭があるなら、無理に学校に通わせる必要はない」といった意見が見られます。
実際、Tarouさんは1日9~11時間の練習をこなし、動画配信も継続しながら、着実にプロゲーマーの夢に向かって歩んでいます。家族がそれを全力で支え、地方への移住など環境づくりにも積極的です。
また、現代ではYouTubeやeスポーツで収益を得る道も現実的になりつつあります。「ゲームで生計を立てられるのなら、それも立派な選択肢」という価値観も受け入れられ始めています。
家庭が協力し合い、地方へ移住して環境を整えるなど、子どもの夢を全力で応援している姿勢も印象的です。
否定的な意見:社会性や人間関係の経験が失われる懸念
一方で、「学力は取り戻せても、学校で得られる社会性は戻らない」とする声も根強くあります。
中学校というのは、勉強だけでなく、「協調性」や「人との距離感」「ルールを守る習慣」などを学ぶ大切な時期です。特に思春期に差し掛かるこの年代での友人関係や我慢の経験は、後の人生に大きな影響を与えることがあります。
また、義務教育とは「中学校までの教育を受けさせることが親の責任」とする制度です。完全に通学せず、指導要領に沿った学びも行わないのであれば、社会的な義務を果たしていないという批判も起こり得ます。
学校に行かないことへの後悔
学校に行く機会があったにもかかわらず、敢えて行かなかったことに後悔する人も少なくありません。年齢相応の教育というものがあり、特に思春期は成長において大きな分岐点となります。
学校での学びや交流は、社会性を養うだけではありません。学年ごとのカリキュラムに基づいた学問の積み重ねが、子どもにとって重要な基盤を作り上げます。そのため、学校に行かなかったことで、その後に、取り戻せない経験や能力があったのではないかという後悔が生じることも考えられます。

真似できる?できない?一般家庭との違い
Tarouさんのような選択が注目される一方で、「一般家庭は真似すべきではない」という意見もよく見かけます。
というのも、このスタイルには次のような前提条件があるためです:
- 保護者が高学歴・高収入で、自由な働き方ができる
- 自宅学習を支える時間とスキルがある
- 安定した生活基盤がある
これらが揃っていなければ、学校に行かずに学びを継続するのは現実的に難しいといえます。
「学校に行かない」という選択の本質とは?
「学校に行かない=逃げ」ではなく、「自分に合った学びの形を見つけた結果」であるならば、それは否定されるべきではありません。
ただし、そうした選択をする際には、「将来的な社会との接点」や「基本的な教育内容」をどう補っていくのか、家庭や子ども自身がしっかりと考える必要があります。
まとめ:教育のゴールは「選べる力」を育てること
Tarouさんのように、若いうちから夢に向かって努力し、実際に結果を出している姿は多くの人にとって刺激となるでしょう。学校教育にとらわれず、「自分のやりたいこと」に向かう姿勢は、これからの時代の学びの一つの形です。
しかしその反面、学校にしかない経験、失ってしまうものへの理解も欠かせません。選択肢が増えた現代だからこそ、子ども自身が自分で進路を選べる力を育てることが、教育の本質ではないでしょうか。