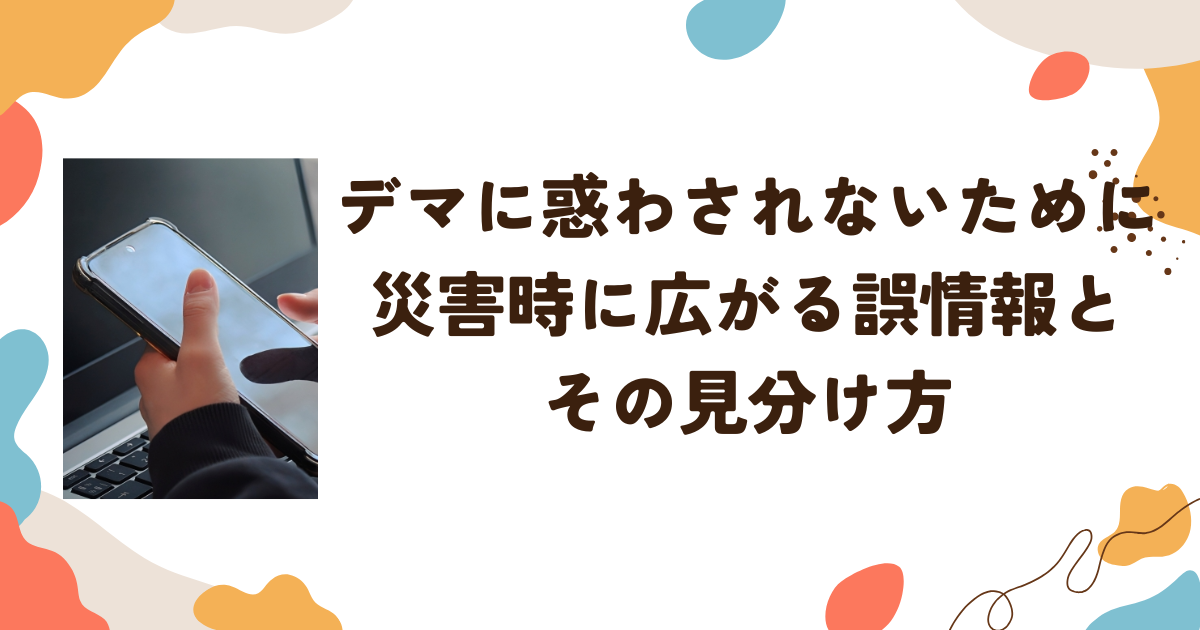デマは災害時に必ずといっていいほど現れ、私たちを混乱させます。 地震や豪雨といった非常時には、人々が安心できる情報を強く求めるあまり、根拠のない噂や誤情報が一気に拡散するのです。誤った情報を信じてしまえば、避難行動や救助活動に支障をきたす可能性があり、時には命を危険にさらすことにもつながります。
2016年の熊本地震では「動物園からライオンが放たれた」というデマがSNSで拡散し、2024年の能登半島地震では「二次避難をすると仮設住宅の抽選から漏れる」といった誤情報が広がりました。災害時に誤った情報を信じて行動してしまうと、避難や救助の妨げになりかねません。
この記事では、なぜ災害時にデマが広がるのか、そして誤情報を見抜く方法をわかりやすく解説します。

災害時にデマが広がる理由
1. 情報の空白と不安心理
災害が発生すると、人々はすぐに状況を知ろうとします。しかし、公式の発表や報道が出揃うまでには時間がかかります。その「情報の空白」を埋めるように、根拠のないうわさや推測が広まりやすくなります。不安や恐怖心が強いほど、人は信ぴょう性を深く考えずに情報を受け入れてしまいます。
2. 流言の公式
心理学では「流言の公式」という考え方があります。
デマの拡散度=重要性 × 曖昧さ
災害に関する情報は命や安全に直結するため「重要性」が高く、さらに正確な情報が不足しているため「曖昧さ」も大きい。この2つが掛け合わさることで、一気にデマが広がるのです。
3. 善意や承認欲求による拡散
「誰かの役に立てるかもしれない」と思ってシェアした情報が、実はデマだったというケースもあります。善意からの拡散は悪気がないだけに止めにくい問題です。また、「注目されたい」「バズりたい」という承認欲求から虚偽情報を投稿する人も存在します。
4. 判断力の低下
災害時は強いストレスや疲労が重なり、冷静な判断がしづらくなります。普段なら疑う情報でも「とりあえず信じて行動しよう」と考えてしまうことが、デマ拡散の一因です。
5. デマの内容は段階で変化する
災害直後は「動物園からライオンが逃げた」といったショッキングな噂や「人工地震説」など原因に関するデマが広がりやすい傾向があります。その後は「救助要請」や「避難方法」、さらに復興期には「義援金詐欺」「著名人の発言デマ」といった形に変化していきます。
実際に起きた災害デマの例
熊本地震(2016年)
「熊本市動植物園からライオンが逃げた」という投稿がSNSで拡散。写真付きで広められましたが、画像は全く別の国で撮影されたものでした。動植物園には100件以上の問い合わせが殺到し、業務が妨害される事態に。投稿者は偽計業務妨害容疑で逮捕されました。

能登半島地震(2024年)
「二次避難をすると仮設住宅の抽選から漏れる」といった誤情報や、「外国人窃盗団が来ている」といった根拠のないデマが広がりました。また、住所付きの虚偽救助要請がSNSに投稿され、実際に警察や消防が出動するケースもありました。さらに、偽の寄付サイトやQRコード付きの投稿も見られ、支援活動に混乱をもたらしました。
災害時にデマを見抜く方法
それでは、実際に災害が起きた時に、どうすればデマを見抜けるのでしょうか。ポイントを整理します。
1. 一呼吸おいて冷静になる
「これは拡散しなきゃ」と思ったときほど注意が必要です。慌てず、一度立ち止まって確認しましょう。
2. 発信者を確認する
その情報を発信しているのは誰でしょうか?自治体や防災機関、信頼できる報道機関であれば安心ですが、匿名の個人や出所が不明な場合は注意が必要です。
3. 公式情報と照らし合わせる
自治体のホームページ、内閣府、防災関連機関の公式発表、テレビやラジオのニュースと比較して真偽を確かめましょう。SNSだけに頼るのは危険です。
4. 画像や動画をうのみにしない
熊本地震のライオンのように、全く別の場所の写真が流用されることがあります。画像検索などで出所を調べるのも有効です。
5. ファクトチェックを利用する
日本では、ファクトチェック団体や防災関連のサイトで誤情報が否定されることもあります。「怪しい」と思ったらまず調べる習慣を持ちましょう。
6. 拡散前に「本当に必要か」考える
情報をシェアする前に、「自分の責任で広められる内容か」「他人に迷惑をかけないか」を考えましょう。善意の拡散が結果的に混乱を招くこともあるのです。
日頃の備えが正しい判断を支える
災害時の誤情報は、誰にでも騙されるリスクがあります。しかし、日頃から正しい情報の入手先を確認しておくことで被害を最小限に抑えることができます。
- 自治体や防災アプリを日常的にチェックしておく
- ラジオやテレビなど複数の情報源を持つ
- 家族や地域で「情報の扱い方」を話し合っておく
これらの備えが、いざという時に冷静な判断につながります。
まとめ
- 災害時は不安と情報不足が重なり、デマが広がりやすい
- 熊本地震や能登半島地震でも誤情報が大きな混乱を生んだ
- デマを見抜くには、発信者・情報源・公式発表との照合が大切
- 善意の拡散も混乱を招くため、「立ち止まって考える」ことが重要
「災害デマに惑わされない力」は、日常から培うことができます。防災の日をきっかけに、家族や地域で話し合い、自分自身の情報リテラシーを高めていきましょう。