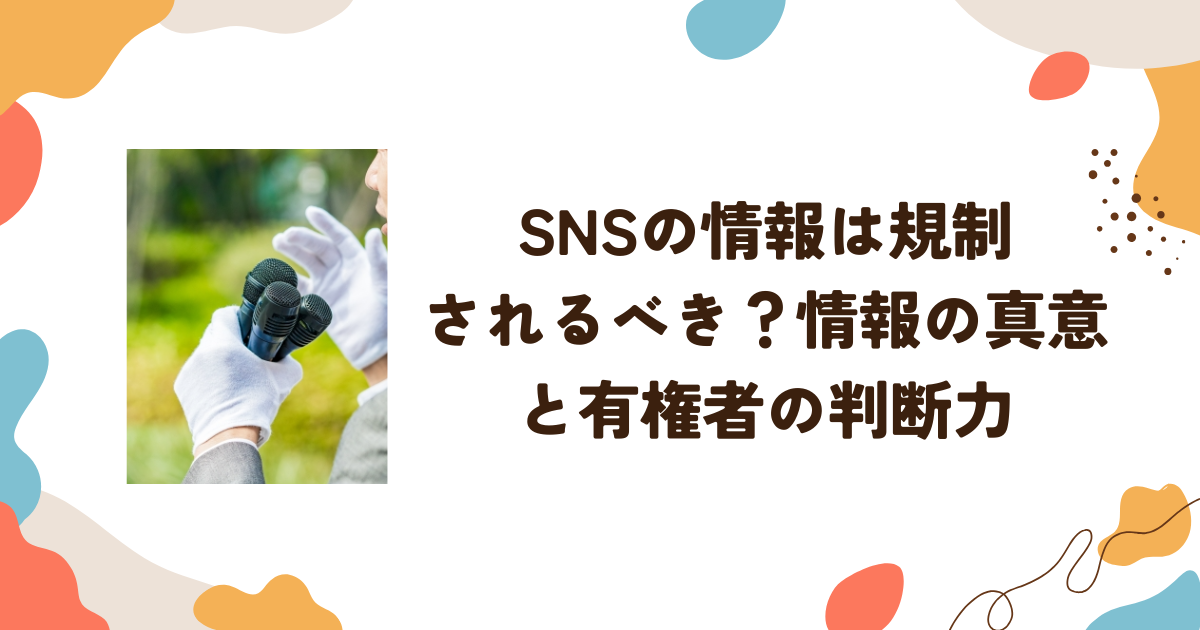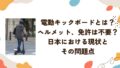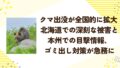SNSを中心に広がる多種多様な情報は、有権者にとって喜ばしい一方で、その真偽を判断することは容易ではありません。
2025年7月20日に投開票を迎える第26回参議院議員選挙(参院選)。その最終盤を迎え、情報の氾濫が、選挙を取り巻く大きな課題になっています。最近の報道でも、識者や有名人が「慎重な情報選別」を訴える発言が相次いでいます。
大越健介キャスターの警鐘
テレビ朝日系「報道ステーション」で、元NHKキャスターの大越健介氏が、参院選前夜の報道を締めくくる形で、次のように呼びかけました。
「SNS上に氾濫する情報については、まず一呼吸置いて、真偽を含めて慎重に内容を見極めていくことをおすすめします」
また、大越氏は、旧来型政党への信頼が揺らぐ今こそ、有権者自身が「どういう情報に接し、どう判断するのか」がこれまで以上に重大であると指摘。政治の方向を決めるのは最終的に一人ひとりの責任であることを強調しました。
この発言は、情報の出どころが多岐にわたる現代において、特定の情報に飛びつくことなく、冷静かつ慎重に精査する姿勢の重要さを示しています。

ひろゆき氏が訴える「デマ摘発」の必要性
一方、SNSなどで影響力を持つ実業家の西村博之氏(ひろゆき)も、選挙戦中の「デマ流布」について問題提起を行いました。
Twitter(X)上で、ひろゆき氏は具体例こそ挙げませんでしたが、次のように述べています。
「選挙中に候補や政党のデマを流すと捕まるんだけど、そろそろちゃんと捕まえてほしいよね」
そして、公職選挙法第235条を引用し、
「当選を得させない目的をもつて…虚偽の事項を公にし…四年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する」
と根拠法を示したうえで、警察とメディアによるリアルタイムな対応を強く求めています。ネット上の誤情報やフェイクニュースが、選挙の公正さを脅かす重大事であるという事実を、改めて世間に突きつけた形です。
この投稿には、次のような反応が寄せられています。
「警察には頑張って欲しいです」
「こういうの、選挙終わってからじゃなくて‘リアルタイム’で対応してくれないと意味ない」
こうした声は、SNSの即時性と拡散力が、同時に責任と慎重さを求める現実を明確に示しています。
法律は追いついているのか?──ネット選挙解禁と課題
日本では2013年の公職選挙法改正により「インターネットによる選挙活動」が解禁されました。当初は候補者自身がHPやメールを用いる範囲が想定されていましたが、その後のSNSや動画プラットフォームの普及拡大により、選挙に関連する情報の発信と拡散が急激に増加しました。
しかし、2025年3月に行われた最新の改正では、主にポスター上の品位や写真掲載規制に関する見直しが中心で、SNS上の情報規制の強化には至りませんでした。表現の自由とのバランスを理由に、SNS規制は未だ議論が十分でなく、現実のネット情報環境とは乖離が生じています。
このため、有権者、メディア、法執行機関それぞれが自覚を持ち、日々目に触れる情報を吟味する態度が重要性を増しています。
なぜ「情報リテラシー」が鍵なのか
今回の参院選では、旧時代的な政党への信頼が揺らいでいる現状があり、有権者が投票先を選ぶ際の判断材料は、ますます多様化しています。一方で、SNSでは切り抜き動画や偽情報が拡散されやすく、感情に訴える情報が受け手を惑わせるケースも少なくありません。
以下のような態度が求められます。
- 出所を確認する
誰が発信しているのか、信頼できるアカウントや情報源かどうかを見極める。 - 複数のメディアや公式情報と照らし合わせる
公示資料、候補者の公式声明、報道各社の調査結果と比較する。 - 感情的に反応する前に“一呼吸”
大越氏が訴えたとおり、第一印象だけで信じず、一度内容を落ち着いて評価する。 - 公職選挙法の存在を忘れない
公職選挙法第235条は虚偽情報拡散を罰する規定であり、法的規制の可能性があることを理解しておく。
こうした姿勢を持つことが、これからの民主主義において不可欠です。
メディア、政府、警察はどう対応しているのか
メディア側も、自らの報道品質に対する監視が強まりつつあります。報道ステーションに出演した大越氏は「まず一呼吸おいて慎重に判断を」と強調し、特に高齢者への一方的な情報提供ではなく、複数メディアへの接触や批判的視点の必要性を述べました。
一方で、警察や選挙管理委員会によるネット上の監視体制も強化されつつありますが、「リアルタイムかつ即時対応」はまだ十分ではありません。ひろゆき氏が指摘したように「選挙中にデマを見つけたら即対応してほしい」という声は、実態と理想のギャップを突いています。
「投票行動」は最後の判断材料
どれほど有益な情報を集めても、最終的に投じるかどうかを決めるのはあなた自身の判断です。大越氏が語ったように、「情報環境がどう変わっても、国の進路を決めるのは有権者一人ひとり」であり、その責任は揺るぎません。
参院選では、選挙区選挙と比例代表選挙、さらには個人名と政党名で投票先を分けられる制度があります。これにより、有権者は政策や人物像、政党の運動方針など、複数の要素を踏まえて投票先を決めることが可能です。
情報社会で問われる「報道の質」と受け手の覚悟
SNSの普及によって、誰もが発信者となれる時代になりました。確かに、SNSにはフェイクニュースや切り抜き動画など、信頼性の低い情報も多く存在します。しかしその一方で、SNSがあるからこそ、オールドメディア(新聞・テレビなど)の報道姿勢や情報の偏りに対する「健全な疑問」も、社会全体で持たれるようになったともいえます。
とくに、高齢者を中心にテレビからの一方的な情報だけに頼る傾向は根強く、SNSの情報拡散力に勝るとも劣らぬ「刷り込み」が起きているケースもあります。つまり、情報の信頼性や影響力は、どの媒体にもそれぞれの危うさがあり、一面的な批判では片付けられない問題です。
このような時代だからこそ、マスメディアこそが率先して「真実を報道する」という本来の使命に立ち返るべきです。視聴率や話題性に傾倒した番組作りではなく、地道で確かな取材に基づいた報道が、今の社会には求められています。
そして、受け手である私たちも、与えられた情報をそのまま受け入れるのではなく、自ら問いを持ち、複数の情報を照らし合わせて判断するリテラシーを育てていかなければなりません。
「この国の進路を決めるのは、有権者一人ひとりである」という大越氏の言葉の重みを、私たちはもう一度胸に刻むべきときです。