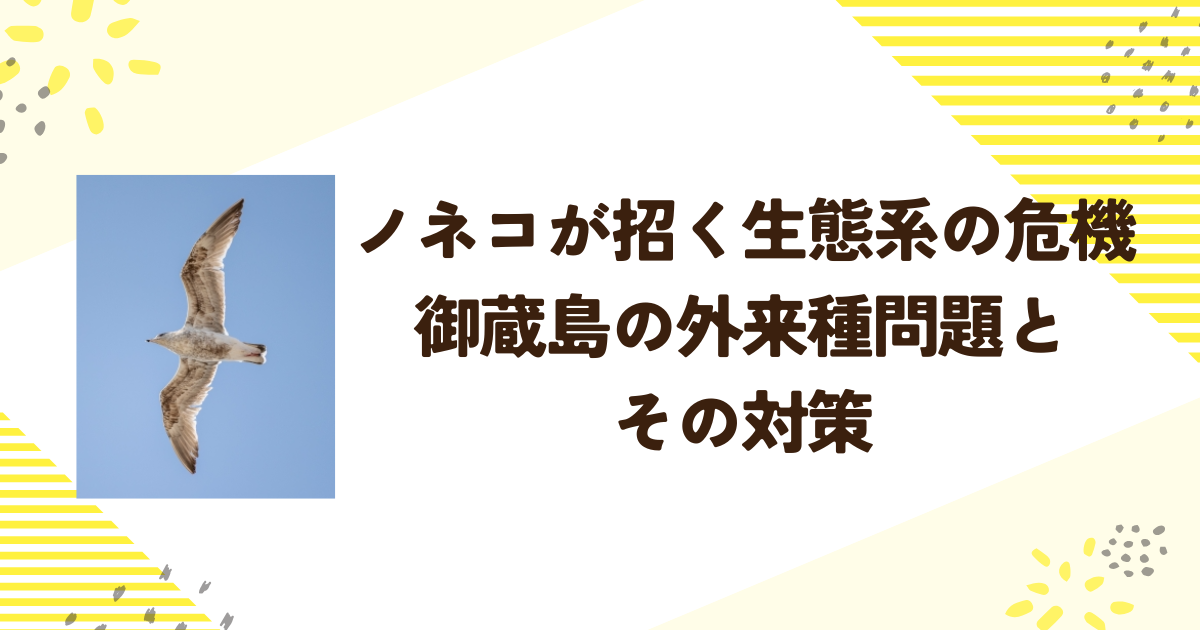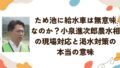東京都・伊豆諸島に浮かぶ御蔵島で、いまノネコ(野生化した猫)が引き起こす深刻な生態系の危機が注目されています。御蔵島は、世界最大の「オオミズナギドリ」の繁殖地として知られていますが、近年、その数が急減。原因の一つとされているのが、ノネコによる大量捕食です。
もともと人間に飼われていた猫が野生化し、山や森で独自に生きるようになったノネコは、警戒心の薄い鳥や希少な小動物にとって大きな脅威となっています。御蔵島では、年間3万羽以上のオオミズナギドリがノネコに襲われていると推定されており、対策が急務です。
本記事では、ノネコとは何か、なぜ問題なのか、そして野良猫との違いや現在の対策について詳しく解説します。自然と動物、そして私たち人間がどう共存していくべきか──そのヒントを、御蔵島の現状から探っていきます。
ノネコとは何か?野良猫との違いと法的扱い
「ノネコ」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。これは、かつて人間のもとで飼われていた猫が、山や森などで野生化し、完全に人間の生活から自立した状態で暮らしている猫のことを指します。
見た目は一般的な「野良猫」と変わりませんが、法的には明確な違いがあります。野良猫は「動物愛護管理法」の対象として保護されますが、ノネコは「鳥獣保護法」に基づく有害鳥獣として扱われ、自治体が駆除(捕獲・殺処分)することが可能です。
興味深いのは、ノネコとして捕獲・殺処分された場合、公式な「殺処分数」としてはカウントされないという点です。一方、野良猫として扱われた場合は殺処分に含まれます。こうした線引きには実際のところ曖昧さがあり、現場では多くの課題を抱えています。
御蔵島で進行するノネコによるオオミズナギドリの捕食被害
東京・伊豆諸島の御蔵島(みくらじま)では、ノネコによる深刻な生態系破壊が進行しています。御蔵島は世界最大の「オオミズナギドリ」の繁殖地として知られており、かつては175万羽以上がこの島に営巣していました。
しかし、2024年から2025年にかけての調査により、ノネコ1頭が年間約330羽のオオミズナギドリを捕食しているという驚きの推計が発表されました。島内で捕獲されたノネコの数を基に計算すると、年間の捕食数は少なくとも3万5,000羽以上に及ぶとされます。
この鳥は非常に警戒心が弱く、夜間に巣穴から出入りするため、待ち伏せ型の捕食を得意とするノネコにとっては「格好の獲物」となってしまうのです。

渡り鳥の繁殖期とノネコの活動期が重なるリスク
これまで、オオミズナギドリは3月頃に繁殖のため御蔵島へ戻ると考えられてきました。しかし、最近の調査では、1月末の段階でノネコのフンからすでにオオミズナギドリの羽根や骨が確認されており、実際には1月中から繁殖地に戻っていたことが明らかになりました。
つまり、従来の想定より約1〜2か月も早い時期から捕食が始まっていたことになります。これは、これまでの捕食被害の評価が過小であった可能性を意味し、今後の対策を見直す必要があることを示しています。
ノネコの生態系への影響──奄美大島や徳之島の例
御蔵島だけでなく、鹿児島県の奄美大島や徳之島でもノネコの被害が報告されています。特に奄美大島では、かつて外来種マングースによる生態系破壊が問題となり、35億円の予算と四半世紀にわたる時間をかけて根絶が実現されました。
ところが、今度はノネコが固有種の「アマミノクロウサギ」や「ケナガネズミ」「アカヒゲ」などを捕食していることが明らかとなり、「第二のマングース」として再び警鐘が鳴らされています。
環境省や地元自治体は、2018年からノネコの捕獲・譲渡事業に着手し、2024年までに671匹を捕獲。しかし、繁殖の早さや森林内への拡散により「いたちごっこ」の様相を呈しているのが現状です。

ノネコ問題への対策と課題
御蔵島では、山階鳥類研究所や東京都獣医師会などが連携し、捕獲されたノネコの不妊手術を行った上で本土に移送し、里親を探す活動を進めています。これにより殺処分を避けながら生態系への影響を軽減することが目的です。
ただし、こうした対策には多くの課題があります。捕獲に必要な人手や資材、費用の確保は簡単ではありません。また、島外に出すには健康状態のチェックや運搬体制の整備も必要です。
さらに、動物愛護団体との間で意見の相違もあります。「ノネコの殺処分は許されない」とする立場と、「希少種の保全が優先」とする立場の対立が続いており、社会的合意の形成が今後の大きな課題となります。
制度のグレーゾーンと保護団体との対立
繰り返しになりますが、ノネコと野良猫は生物学的に同じ種であり、見た目では区別できません。ところが、法的には全く異なる扱いを受けるため、「これはノネコだった」とされれば殺処分しても統計に記録されず、逆に野良猫として扱われれば保護対象になります。
この曖昧な制度のもとで、猫の扱いをめぐる混乱や、現場での判断ミスが問題視されています。例えば、ある地域では野良猫への虐待行為が「ノネコと間違えた」として正当化される事例すら出ており、法制度の見直しが求められています。
生態系保護と動物福祉の両立に向けて
私たちは今、「絶滅危惧種を守る」という命題と、「猫も大切な命である」という価値観の間に立たされています。
ノネコの問題を正しく理解し、対策を進めるためには、まず科学的な事実に基づいた議論が不可欠です。その上で、地域住民や保護団体、行政、研究者が協力し、持続可能な方法を模索していく必要があります。
一つの命を守るために、もう一つの命を犠牲にすることがないように──。それを可能にするのは、情報の共有と社会全体の理解、そして柔軟で創造的な制度設計です。
ノネコ問題に私たちはどう向き合うべきか
ノネコ問題は、単なる「猫の問題」ではありません。そこには、絶滅の危機にある野生動物と、人間社会のあり方、生態系のバランス、動物福祉と倫理、法制度の限界など、さまざまな課題が複雑に絡み合っています。
御蔵島で起きていることは、日本各地の離島や山間部、あるいは都市のすぐ近くでも起こり得る「予兆」かもしれません。
猫も野鳥も、どちらも私たちにとって大切な存在です。だからこそ、感情論だけではなく、理性的な議論と行動が求められます。