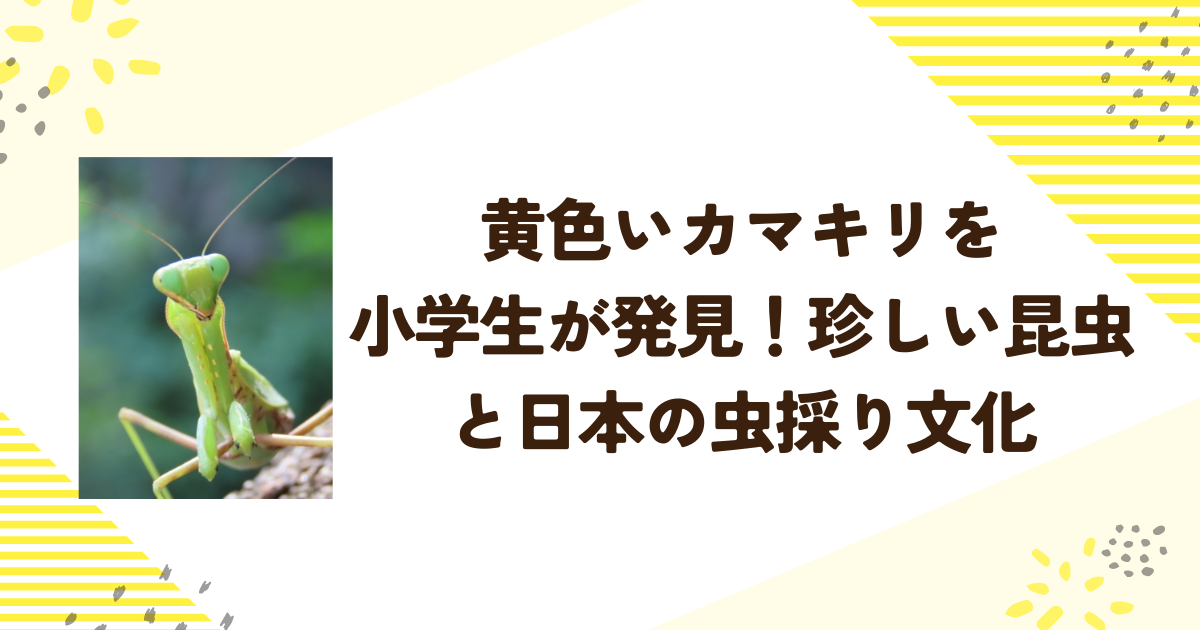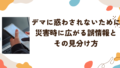沖縄県本部町の八重岳で、南風原町立北丘小学校2年の上地結磨さん(7)が、全身が黄色いカマキリを見つけました。木にくっついている“黄色い何か”に気づき、最初は葉だと思ったそうですが、近づくと虫だと分かり、伯父に抱き上げてもらって捕獲に成功。「初めて見たのでうれしかった」と話し、将来は「昆虫博士になりたい」と夢を語りました。
専門家によると、この個体は「ハラビロカマキリ」の幼虫である可能性が高く、通常は緑色をしているため、黄色は非常に珍しいといいます。

専門家も驚いた「黄色の理由」
沖縄大学の盛口満教授は、この黄色について「色素を作る遺伝子の突然変異が考えられる」と説明しています。
一般的にハラビロカマキリは緑や褐色の体色をしていますが、黄色はほとんど確認されていません。
ここで興味深いのは、昆虫の体色がどのように決まるかという点です。
- カマキリの場合:基本的には遺伝的な要因が大きく、環境によって急激に色を変えることはありません。
- バッタの場合:環境や周囲の条件によって色が変わることがあります。草地に多い緑の個体、土の多い場所に適応した褐色の個体などが見られるのです。
つまり、カマキリにおける「黄色」という体色は、単なる環境適応ではなく、突然変異や発育過程で生じた特殊な要素である可能性が高いと考えられます。

日本では「黄色いカマキリ」はとても珍しい
日本に生息するカマキリの多くは緑色で、一部に褐色の個体が見られる程度です。黄色い個体は観察記録が極めて少なく、今回のように子どもが偶然発見するケースは特に珍しいといえます。昆虫愛好家や研究者の間でも「一生に一度見られるかどうか」と言われるほどの希少性があります。
小学生が発見した珍しい昆虫たち
実は、日本では小学生が大人顔負けの“珍しい発見”をして話題になることが度々あります。
黄色いウナギ(バナナウナギ)
三重県では小学1年生の男の子が、黄色と黒のまだら模様を持つウナギを捕まえました。通称「バナナウナギ」と呼ばれるこの個体は、色素異常による突然変異で、ごくまれにしか見つからないものです。
雄のナナフシ
愛知県では小学6年生が「トゲナナフシ」のオスを発見しました。日本で見られるトゲナナフシはほとんどがメスで、オスの存在は非常に稀。専門家からも「一生に一度見られるかどうか」と評価されるほどの驚きの発見でした。
こうした例は、子どもの好奇心と観察力が自然界の新しい発見につながることを示しています。

日本独自の「虫採り文化」と子どもの観察力
日本の夏といえば、網と虫かごを持って昆虫採集を楽しむ子どもの姿が定番です。セミやカブトムシ、クワガタを追いかける体験は、世代を超えて受け継がれてきました。
なぜ海外には虫採り文化がないのか?
一方、海外では子どもが虫採りをする習慣はあまり一般的ではありません。その背景にはいくつかの理由があります。
- 昆虫に対する考え方の違い
日本では昆虫が季節の風物詩として親しまれてきましたが、欧米などでは害虫や不快な存在とされることが多く、触れるものではなく駆除すべき対象として扱われる傾向があります。 - 安全性や衛生面の懸念
日本の里山に生息する昆虫は比較的安全ですが、海外では毒を持つ昆虫や危険な種類も多いため、「触ってはいけない」と教育されることが少なくありません。 - 都市化と自然環境の違い
日本の公園や校庭にはセミやトンボが普通に飛び交いますが、欧米の都市部では昆虫を見つけるのが難しく、自然と子どもが触れる機会も減っています。 - 教育・文化的背景
日本では夏休みの自由研究や理科の授業と虫取りが結びついており、昆虫図鑑や採集キットも豊富に市販されています。対して海外では昆虫観察は研究者や博物館の領域として扱われ、子どもの遊びとは結びつきにくいのです。
こうした要因が重なり、虫採りは日本ならではの独特な文化となっているのです。
発見したらどうする?珍しい虫との向き合い方
もし珍しい虫を見つけたら、次のような点に気をつけましょう。
- 無理に捕まえず、写真に残すだけでも十分な価値があります。
- 捕獲した場合は、できれば地元の博物館や自然科学館に相談すると、学術的な記録になります。
- 飼育する場合は、その虫の習性を調べ、最後は自然に返すことを考えるのも大切です。
こうした対応を通して、子どもが自然との関わり方を学び、科学的な視点を育てることができます。
まとめ:子どもの「気づき」が未来を広げる
沖縄で発見された黄色いカマキリは、自然の多様性と偶然の面白さを私たちに示してくれました。小学生の「なんだろう?」という素朴な疑問と観察力が、研究者も驚く発見につながるのです。
今後も日本の虫取り少年・少女たちが、まだ知られていない生きものの姿を見つけるかもしれません。自然は、身近な山や川の中にこそ、大きな驚きと学びを秘めています。