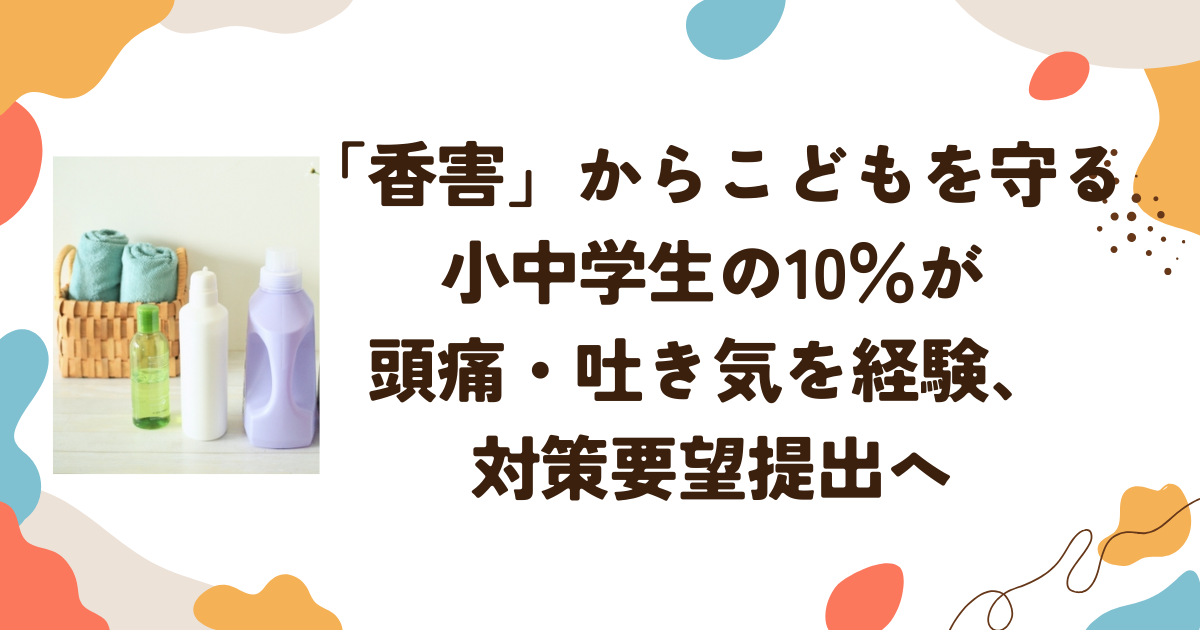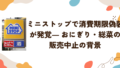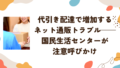「香害」という言葉をご存じでしょうか。柔軟剤や洗剤、芳香剤などに含まれる人工香料によって、頭痛や吐き気、めまいなどの体調不良を引き起こす現象を指します。いま、この「香害」が学校現場でも深刻化しており、子どもたちの学習環境に影響を与えていることが調査で明らかになりました。
2025年8月20日、消費者団体などが実施した調査から、小中学生の10.1%が学校で「香料による頭痛や吐き気など」の症状を経験しています。
日常の「良い香り」が、子どもたちの健康に悪影響を与えることが問題になっています。洗剤や柔軟剤に含まれる人工化学香料によって、学校生活中に体調を崩す児童生徒の存在が明らかになったのです。
この調査は、消費者団体「香害をなくす連絡会」(日本消費者連盟など)および超党派の「香害をなくす議員の会」が取りまとめたもので、2024年5月〜2025年1月にかけて、北海道・新潟・兵庫など9都道県・21自治体の小中学生約8,000人と未就学児約2,000人の保護者などが対象でした。その結果、全体(未就学児含む)では8.3%の子どもが香料による体調不良を経験しているということでした。

「香害」とは?化学物質過敏症との関係
「香害」とは、柔軟剤や洗剤、芳香剤、香水などに含まれる人工香料や揮発性有機化合物(VOC)が原因で、頭痛・吐き気・めまい・皮膚症状などを引き起こす健康被害を指します 。
実際、シャボン玉石けんの調査(2021年)では、人工香料によって不快感を覚える人は71%、体調不良を感じた人は36%にのぼるという結果もあります 。
小中学生に限定した調査では、専門家によれば1~2割の児童生徒が香りによる体調不良を訴えるとの報告もあり、給食用エプロンを介した柔軟剤の香りや、保護者の香水に反応して体調を崩すケースもあるとのことです。
調査結果の分析と実態の深刻さ
今回の調査(2024年5月〜2025年1月、9都道県・21自治体)は、学校現場における「香害」を実態として捉える大規模なものです。小中学生8,000人強+未就学児2,000人強という回答数は、実態把握の信頼性に寄与しています。
そのうち小中学生の10.1%が「学校で香料による頭痛や吐き気を経験した」と回答した点は、決して無視できない数字です。学校は学びの場であるだけに、体調の問題が学習環境に大きな影響を及ぼす懸念があります。

学校や自治体での対応は?
実際に、教育現場では柔軟剤の香りに配慮する動きが徐々に広がっています。たとえば、共用の給食用エプロンに強い香りが残ることを避けるため、「エプロンを個人持ちに」「柔軟剤使用を控えてほしい」といった要望が保護者からもあがっています。
また、教育現場では以下のような対応も報告されています。
- 授業中、香料に反応する児童を窓際の席に配置し、換気を強化した教室環境づくり
- 重症の場合、オンライン授業や個別教室の設置など、学校外の学習環境の提供
- 教職員や保護者向けに「香害」「化学物質過敏症」に関する勉強会の開催
文部科学省でも、2012年に「学校における化学物質による健康障害に関する参考資料」をまとめ、学校現場や教育委員会が組織的に対応することを促す内容を提示しています。
とはいえ、“香害”についての医学的裏付けやエビデンスはまだ不十分であるため、国として全国一律の対応策を出すのは現時点では難しいとの認識もあります。
今後求められる取り組み
消費者団体は今回の調査結果や学校での実態を踏まえ、文部科学省に以下のような対策強化を求めています。
- 啓発活動の実施:教員・保護者・子どもたちへの「香害」への理解促進
- 学校現場での全国的な実態調査
- 柔軟剤・洗剤などの製品成分の公開・規制検討
- 香料使用のモラルや指針の整備
わたしたちにできること
香害は外から見えにくく、周囲が気づかないまま苦しんでいる子どももいます。また「香り」は個人の自由であるという感覚も強いため、指摘しづらい問題でもあります。
しかしながら、実際に体調不良を感じる子どもがいること、香害が学習環境に悪影響を及ぼすことは、社会全体が知っておくべき大切な事実です。
家庭でも学校でも、以下のような配慮が進められると良いでしょう。
- 登校時の衣類や給食衣に強い香りの柔軟剤を使わないよう心がける
- 保護者や教職員が情報を共有しあい、チェックリストや注意事項を文書化する
- 香害が起こりやすい状況(給食当番・参観日など)には告知や対応策を立てる
- 匂いに敏感な子どもや保護者に配慮する姿勢を社会全体で取り育てていく
終わりに:子どもたちの学ぶ環境を守るために
「良い匂い」はたしかに心地よく、気分をリフレッシュさせてくれるものです。でも、人によって心地よく感じる香りもあれば、体調を崩してしまう人もいます。特に子どもたちは自分の症状をうまく言い表せないこともあるため、大人がその声に敏感であることが求められます。
今回の調査結果(小中学生の10.1%が学校で香害による体調不良を経験)を契機に、家庭・学校・社会が協力し、香害に苦しむ子どもを守る環境づくりを進めていくことが大切です。