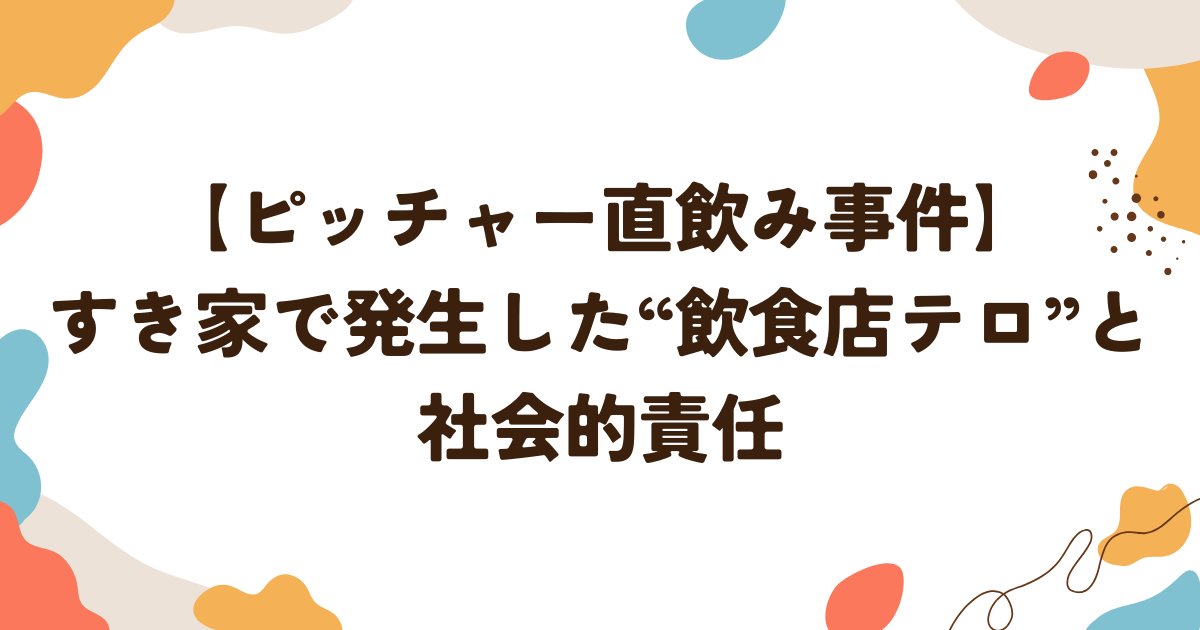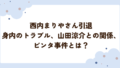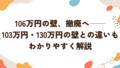2025年2月、大阪市中央区の牛丼チェーン「すき家」で、16歳の少女2人が店舗の卓上ピッチャーに直接口をつけてお茶を飲むという迷惑行為を行い、その様子をSNSに投稿したとして、大阪府警は5月、2人を威力業務妨害容疑で書類送検しました。この一件は、飲食店での「迷惑動画投稿」が引き起こす社会的影響を再び浮き彫りにしました。
ピッチャー直飲みという行為が招いたもの
当該動画では、店内の卓上ピッチャー(いわゆる「水差し」)に少女が口を直接付けてお茶を飲んでいる様子が収められていました。撮影された動画はSNSに投稿され、拡散。店側は該当ピッチャーを洗浄・交換し、衛生面や顧客対応などに追われたことで、通常業務に支障が出たと判断され、警察に相談。最終的に書類送検に至りました。
このような行為は、「ふざけてやった」「バズりたかった」などの理由では済まされません。第三者が使う備品に対して衛生を著しく損なう行為であり、実害をもたらす“犯罪”です。
威力業務妨害罪とは?
本件で適用された「威力業務妨害罪」とは、刑法234条に基づくもので、他人の業務を妨害する目的で威力(身体的・心理的な強制や圧力)を用いた場合に成立します。
SNSでの動画拡散は、店の信用を損ない、顧客離れを招くなど、物理的な暴力を使わずとも結果的に“威力”を伴った妨害とみなされます。このような判断は、2023年に発生した「回転寿司テロ」でも前例があり、実際に数名が逮捕・起訴されています。
飲食店で続発する「迷惑行為」──類似事件との比較
| 年度 | 店舗業態 | 行為内容 | 法的対応 | 社会反響 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 回転寿司 | 醤油差しに口をつけた動画投稿 | 威力業務妨害で逮捕 | “すしテロ”の言葉が流行 |
| 2023 | ラーメン店 | ニンニク容器のスプーンを口に入れて戻す | 逮捕 | 調味料の撤去が加速 |
| 2025 | 牛丼チェーン(本件) | ピッチャーにじか飲み | 書類送検 | 「水差しじか飲み」が問題視 |
どの事例も、“軽はずみな行動”がSNSで拡散され、企業・利用者双方に大きな影響を与えています。
変わり始めた企業対応──毅然とした「被害届」の意義
かつては、このような迷惑行為に対し、飲食チェーン側が“謝罪と再発防止”にとどめるケースもありました。しかし、現在では事情が大きく変わっています。企業は「毅然とした対応」がブランドを守る最大の防御策であると認識し始めています。
すき家も、本件で速やかに被害届を提出し、SNSや公式見解で「厳正に対処する」と表明しました。こうした姿勢は、模倣犯の抑止、顧客への安心感の提供、そして店舗・従業員の士気維持にも繋がります。
テーブル上のアイテムにも変化が…
本事件の影響だけではありませんが、近年、飲食チェーンでは卓上調味料や共用物の“撤去”や“提供制”が進行中です。
- 以前は自由に取れた漬物や調味料は「必要であればスタッフにお声かけください」に変更
- ピッチャーやスプーンも、スタッフ提供式に切り替えるケースが増加
- 一部では、使い捨て容器への変更やフタ付きの備品導入も
これは、飲食店が被る損害が“金銭”だけではないことを示しています。信頼の損失は、売上やブランドに大きく影響するのです。
「バズ狙い」がもたらす現実の代償
SNSが身近なツールとなった今、投稿の再生回数や「いいね」を求めて、過激な行動に出る若年層が増えています。しかし、
「投稿すればバズる」「バレないだろう」という甘い考えは、現実とはかけ離れています。
- SNS上の投稿は削除しても復元・記録されている場合が多い
- 店内の防犯カメラ、目撃者、そして投稿に映った服装・声などから高精度で個人が特定される
- 警察はすでにSNSからの“逆引き”捜査を常態化
このような現実を知らない若者たちが、ニュースを見ない、読まないという「情報断絶」にある可能性も指摘されています。
社会全体で模倣犯を防ぐために
このような事件を防ぐには、飲食店の対策だけでなく、社会全体での意識の共有が不可欠です。
- 学校でのネットリテラシー教育の充実
- 保護者・大人による日常的な注意喚起
- 報道による「逮捕・書類送検」などの具体的事例紹介
また、利用者一人ひとりも「飲食店でのマナーを守る」ことが当たり前だという意識を持つことが重要です。
秩序を守るための「厳正な姿勢」
今回の「ピッチャー直飲み事件」は、単なる迷惑行為にとどまらず、「飲食店テロ」とも言える重大な社会問題です。飲食店が清潔で安全な空間であり続けるためには、
- 法的対応による抑止
- 被害届提出による明確な意思表示
- 客側のモラルとマナーの再認識
これらが三位一体となって機能する必要があります。
何よりも大切なのは、「バズりたい」「目立ちたい」という一時の感情で行動することが、自分の人生を大きく狂わせるリスクをはらんでいるという現実を、すべての世代がしっかり認識することです。