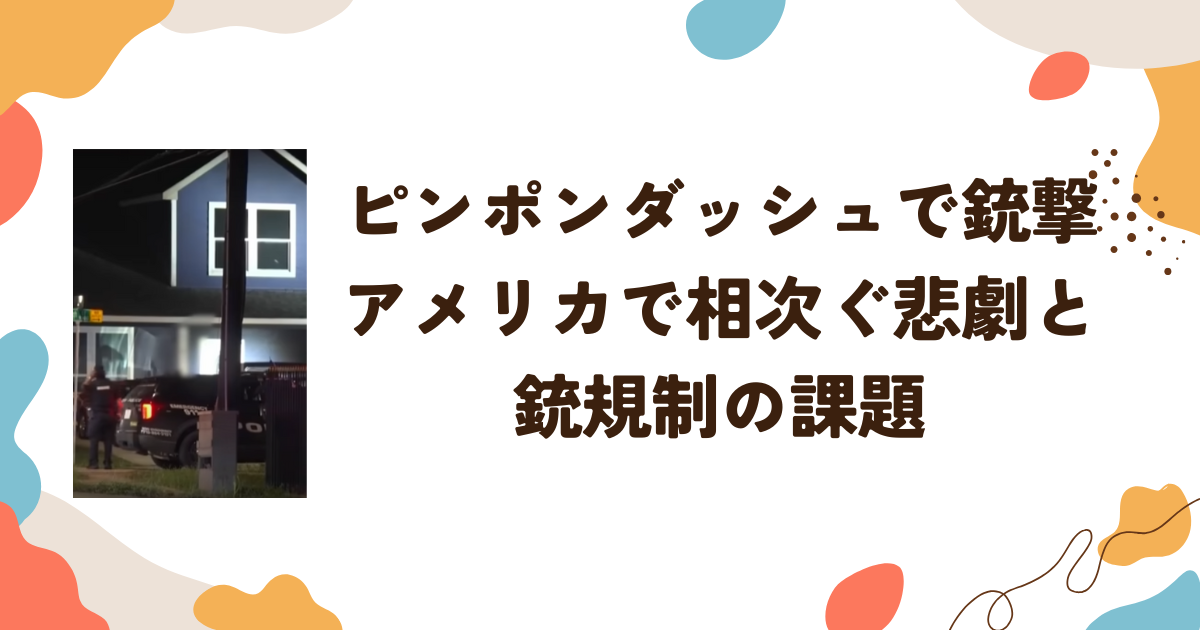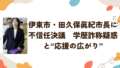テキサス州ヒューストンで、11歳の少年が玄関ベルを鳴らして逃げる「ピンポンダッシュ」の最中に住人に銃撃され、命を落としました。警察は「正当防衛にはあたらない」と説明しており、軽いいたずらが取り返しのつかない悲劇へとつながった形です。
この事件は、銃を持つことが日常化しているアメリカ社会の危険性を改めて示しました。過去には、似たような状況で「正当防衛」が認められ、銃撃した住人が無罪となったケースも存在します。銃と正当防衛をめぐる議論は、いまもアメリカ社会に根深い課題として残されています。
さらに近年は、SNSで拡散される「チャレンジ動画」をきっかけに命を落とす若者も後を絶ちません。銃規制とSNS時代の危険行為という二つの課題が交差する今、私たちは「命をどう守るか」を真剣に考える必要があります。

ピンポンダッシュによる悲劇
2025年夏、アメリカ・テキサス州ヒューストンで、11歳の少年が命を奪われる衝撃的な事件が起きました。
少年は夜遅くに友人たちと遊んでおり、その中で「ピンポンダッシュ(玄関ベルを鳴らして逃げるいたずら)」をしていました。ところが、ある住宅の呼び鈴を鳴らした際、住人が銃を持ち出し発砲。逃げていた少年の背中に弾丸が命中し、少年は病院に搬送されましたが亡くなりました。
検視結果によれば、発砲の瞬間、少年は住宅から約6メートル以上離れており、しかも背を向けて逃げていたため、生命を脅かすような状況ではありませんでした。警察も「正当防衛は成立しない」との見解を示しています。
それでもアメリカの一部の州では、自宅を守る権利を強く認める「キャッスル・ドクトリン」や「スタンド・ユア・グラウンド法」が存在し、住民が「危険を感じた」と証言するだけで正当防衛が成立するケースも少なくありません。この点が銃社会アメリカの大きな特徴であり、今回の事件をめぐる議論の焦点にもなっています。
ハロウィンに起きた日本人留学生の射殺事件
今回の事件は、1990年代に起きた日本人留学生射殺事件を思い起こさせるものでもあります。
当時16歳の高校生だった留学生は、交換留学でルイジアナ州に滞在していました。ハロウィンパーティーに招かれて友人と仮装して出かけたものの、住所を間違えて別の家を訪問してしまいます。呼び鈴を鳴らした際、家主が銃を持ち出して対応。英語を聞き間違えた可能性もあり、留学生は笑顔で近づいたところ、至近距離から発砲され命を落としました。
刑事裁判では家主が「正当防衛」を主張し、無罪となったことが日本でも大きな衝撃を与えました。自宅に不審者が入ってきた場合、命を守るために致死的な武力を使う権利が認められる――これがアメリカ社会に深く根付いている考え方なのです。
日本では到底受け入れがたい判決でしたが、この事件をきっかけに被害者の家族はアメリカでの銃規制活動を始め、180万人以上の署名を集めて当時の大統領に提出しました。その後も「銃のない社会」を目指す活動は続いています。

正当防衛と銃規制 ― どこまで許されるのか
今回のヒューストンの事件も、過去の日本人留学生の事件も共通しているのは、「相手が実際には脅威ではなかった」という点です。
それにもかかわらず、銃が使われ命が奪われてしまった背景には、アメリカ特有の「正当防衛」の広い解釈と、容易に銃を手にできる環境があります。
- 数メートル離れた逃走中の少年に銃を撃つ
- 言葉を聞き間違えただけの留学生に発砲する
これらが「仕方のないこと」と片付けられてしまうなら、誰もが命の危険にさらされることになります。銃規制の議論が繰り返されながら抜本的な改革が進まない現状は、国際社会からも強い懸念を集めています。
SNSが生む危険な「チャレンジ文化」
今回のピンポンダッシュも、単なる悪ふざけではなく、SNS上で「チャレンジ動画」として流行している背景が指摘されています。実際、TikTokなどには玄関のベルを鳴らしたりドアを叩いたりする動画が多数投稿されており、若者が再生数や「いいね」を求めて危険な行動に走る例が増えています。
今年5月、バージニア州でも同様にピンポンダッシュ中に撮影していた18歳が射殺された事件があり、第2級殺人罪で起訴されました。さらに2020年には、別の地域でいたずらの報復として車が突っ込まれ、若者が死亡したケースもあり、加害者に終身刑が言い渡されています。
この構図は銃事件だけでなく、さまざまな事故にもつながっています。たとえば、
- 地下鉄サーフィン:走行中の電車に飛び乗り、屋根の上を移動する行為。毎年のように死亡事故が起きています。
- 激辛ポテチチャレンジ:超激辛スナックを一気に食べる企画で、体調不良や救急搬送が相次ぎ、アメリカでは製造中止に追い込まれた商品もあります。
いずれもSNSの拡散力が「危険行為を面白い挑戦」に変えてしまう典型例です。命を失ってからでは遅いのに、その危険性が十分に理解されないまま広がっているのが現状です。
おわりに ― 命を守る社会に向けて
ヒューストンでの少年射殺事件、そして過去の日本人留学生射殺事件は、アメリカの銃社会の危険性を改めて突きつけました。
銃を「身を守るための道具」と考える文化がある一方で、実際には「無防備な人々の命を奪う凶器」として使われてしまう現実があります。正当防衛が広く認められる社会であるがゆえに、命があまりにも軽く奪われてしまう。この構造を変えない限り、悲劇は繰り返されるでしょう。
さらに、SNS時代の今は、銃だけでなく「チャレンジ文化」による危険も無視できません。地下鉄サーフィンや激辛チャレンジなど、一見すると遊びや挑戦に見える行動が、実際には命を脅かすリスクをはらんでいます。
命を守るために必要なのは、銃規制の強化だけではありません。
社会全体でリスクを理解し、教育を徹底し、若者に「安全こそが本当の勇気」であることを伝えていくことです。
銃社会とSNS社会――二つの課題が交差する現代において、私たち一人ひとりが「命をどう守るか」を考え続けることが、次の悲劇を防ぐ第一歩となるのではないでしょうか。