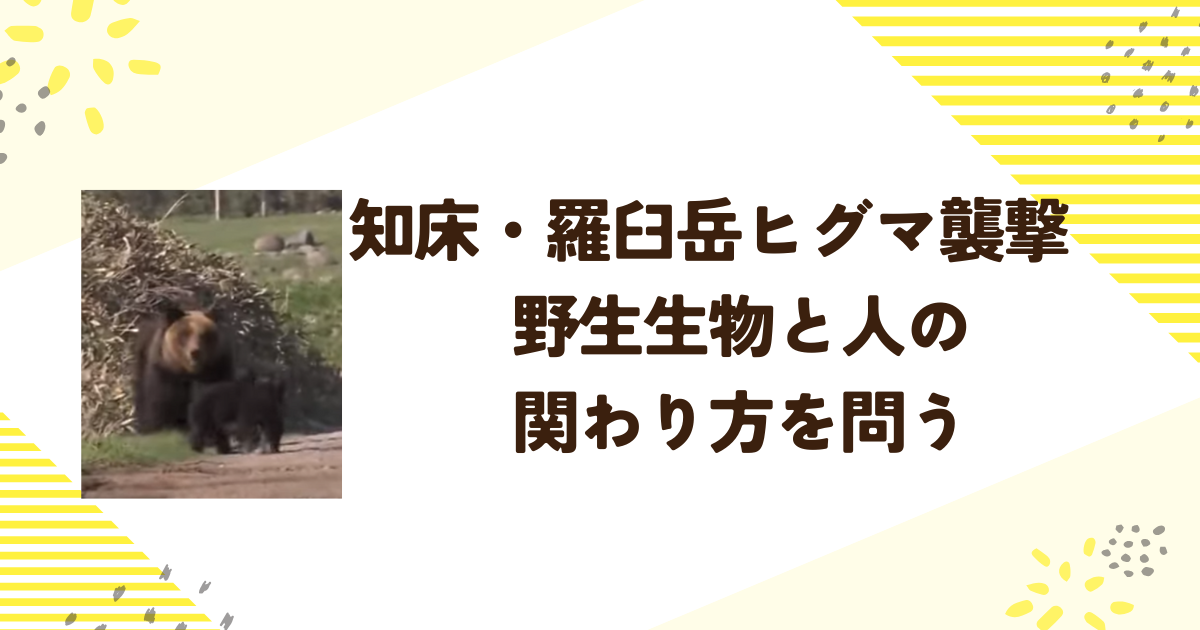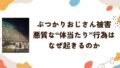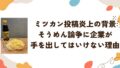2025年8月14日、北海道・知床半島の羅臼岳で登山者がヒグマに襲撃され死亡する事故が発生しました。世界自然遺産として知られる知床では、これまでもヒグマとの遭遇事例が数多く報告されていますが、今回の出来事は改めて安全対策や人と野生動物との距離の取り方を問いかけるものとなりました。本記事では、事故の経緯、事前に報告されていた前兆、そして近年増加するヒグマと人との接触の背景について整理します。
事故の経緯:悲劇の現場と状況
発生から捜索まで
事件が起きたのは2025年8月14日午前11時10分ごろのことです。東京都墨田区在住の会社員・曽田圭亮さん(26歳)は、友人と2人で羅臼岳に登山していました。下山途中、前を歩いていた曽田さんが突然ヒグマに襲われたのです。およそ200メートル後方を歩いていた友人は、曽田さんに名前を呼ばれて異変に気づき駆け寄りました。現場では曽田さんが太もも付近から大量に出血し、ヒグマに組み伏せられていました。
友人は素手でヒグマを殴るなど必死に抵抗しましたが、ヒグマは曽田さんを茂みに引きずり込み、そのまま離さなかったといいます。友人自身に怪我はありませんでした。すぐに110番通報が行われ、警察と消防による捜索が始まります。
翌15日午前中には現場付近で血痕や引きずられた跡が確認され、財布や熊よけスプレー、腕時計、帽子などの遺留品も発見されました。周囲の草木には争った痕跡が残されていたといいます。
15日午後1時頃、捜索隊は現場近くで親グマ1頭と子グマ2頭の計3頭を確認。ハンターにより親グマを駆除した後、約30分ほどして子グマ2頭も合わせて駆除されました。その直後、親グマのすぐそばで曽田さんの遺体が見つかりました。顔や上半身に外傷があり、下半身には激しい損傷が確認され、死因は失血死とみられています。駆除されたクマが実際に襲撃した個体かどうかは、DNA鑑定などを通じて特定が進められています。
登山道の閉鎖・周辺対策
事故後、三つの登山道は全面閉鎖され、知床五湖への道も臨時封鎖。警察や防災ヘリによる救助が続けられ、注意報も発令されました。
前兆:事故前から見られたヒグマとの接近・付きまとい事案
実際に事故が起こる数日前から、羅臼岳周辺では“前兆”とも言えるヒグマとの遭遇事例が報告されていました。
- 8月10日、登山者が親子のヒグマと至近距離(5メートル)で遭遇し、熊撃退スプレーを構えながら慎重に退避したケースがありました。
- 8月12日には、登山者がスプレーを使用したにもかかわらず、数分間にわたりヒグマに付きまとわれた事例が確認されています。
専門家はこれらを「人に付きまとう行動を見せるヒグマ」の典型例と評価し、行動がエスカレートした可能性を指摘しています。
酪農学園大学・佐藤喜和教授も、「付きまといが確認された時点で、積極的な駆除対応が必要だった」と語っており、行政対応のあり方に疑問を投げかけています。

背景:ヒグマと人との接触が増えている理由
個体数の増加と人馴れ化
知床には現在、およそ500頭ほどのヒグマが生息すると推定されており、その高密度ぶりは世界的にも類を見ないレベルとされています。多様なエサを垂直的に活用できる環境が整っており、ヒグマの個体数増に寄与しているのが現状です。
さらに近年では、「人を恐れず接近する“人馴れグマ”」の出現が目立ち、登山者や観光客にとってより危険性が高まっています。
人の側の誘引行動
ゴミの放置、エサやり、観光客によるクマとの写真を撮ろうとする不適切な接近など、人間側の行動がヒグマを学習させ、問題行動を誘発しているケースも増えてきました。
これらは「問題個体」として分類され、積極的な対策が求められている領域です。

管理体制の取り組み
知床では「ヒグマ管理計画」に基づき、電気柵の設置、誘引物の除去、高架木道の活用、フードロッカー等を通じた対策を推進しています。しかし、人とヒグマが混在する地域特有の課題も多く、体制の強化と住民や観光客の理解・協力が不可欠です。
まとめ:自然の中での共存への問い
事故への痛切な教訓
今回の事故は、「自然豊かな場所での人間と野生動物の接点」における安全確保の難しさを示しました。前兆が複数報告されていたにもかかわらず、最悪の事態を避けられなかったのは、対応の遅れや体制の不備によるものです。今後は、早期封鎖や駆除判断など、迅速な対応体制の整備が必要です。
人間の行動にも責任がある
ヒグマとの距離を自然なものとして保ちつつ、人間側が不用意に関わらない姿勢も不可欠。「人馴れを避ける」意識と行動の徹底が、野生動物との軋轢を減少させる第一歩です。
共存への展望
知床のような豊かな自然環境を未来へ継承するためには、地域住民、行政、観光関係者、利用者すべてが、ヒグマの生態や行動について理解を深め、適切な措置を講じていく必要があります。事故をただ悲劇と終わらせず、安全な自然体験とヒグマの保護—そのバランスを追求することが今、何より求められています。