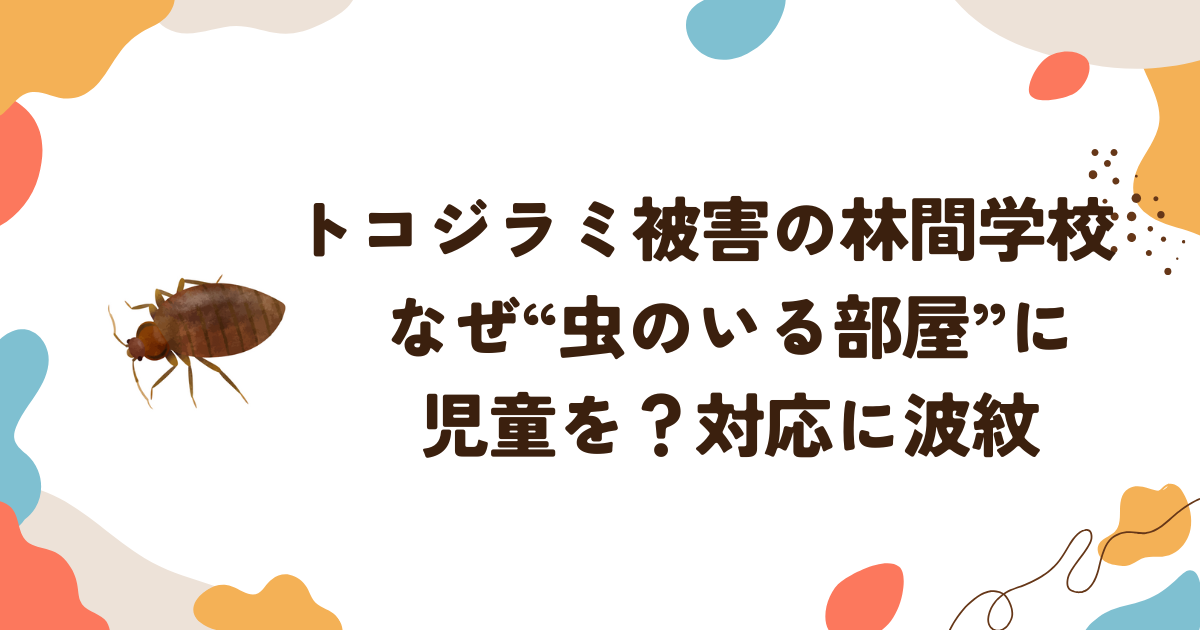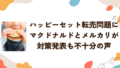2025年8月上旬、東京都品川区の小学校が実施した林間学校で、トコジラミ(南京虫)による被害が発生しました。舞台となったのは栃木県日光市にある区立の保養施設。この施設に宿泊した児童の一部が、「部屋に大量の虫がいた」と訴え、結果として虫だらけの部屋”で寝かされたことへの保護者の抗議が相次ぎ、学校側が謝罪する事態となりました。
この出来事は、教育現場における「安全配慮義務」や「適切な判断力」、そして保護者との信頼関係について、私たちに多くの問いを投げかけています。本記事では、この件の詳細と問題点、そして今後の教訓について丁寧に解説します。
トコジラミとは?林間学校で起きた“見過ごせない虫害”
「トコジラミ(南京虫)」とはどのような虫か。
トコジラミは、人の血を吸う吸血性の害虫で、刺されるとかゆみや腫れを引き起こします。シラミと名前に付きますが、分類学的にはカメムシの仲間です。
近年、海外からの旅行者の増加や、殺虫剤への抵抗性を持つ個体の増加により、日本国内でも急速に拡大しており、厚生労働省も注意喚起を行うレベルの厄介な虫です。
しかも、トコジラミは光を嫌う性質があり、通常は暗くなると活動を始め、寝ている人間に近づいて血を吸います。そのため、「電気をつけて寝る」というのは一応の応急策として理にかなっていますが、根本的な対処とは言えません。
特徴
- 見た目: 成虫は体長5~8mmで、茶褐色で扁平な楕円形をしています。血を吸うと丸く膨らみます。幼虫は小さく、色が薄いです。
- 生息場所: 暗くて狭い場所を好み、ベッドやマットレスの縫い目、家具の隙間、畳の裏側、壁紙の剥がれた部分などに潜んでいます。
- 生態: 昼間は隠れていて、夜間に活動します。人が寝静まった頃に、二酸化炭素を感知して出てきて吸血します。オス・メス、幼虫・成虫のすべてが吸血します。
- 移動: 翅(はね)がなく飛ぶことはできませんが、素早く移動します。衣類や荷物、家具などに付着して運ばれることが多いです。
駆除の難しさ
トコジラミの駆除は非常に難しいとされています。自分で駆除を試みる場合は、掃除機で吸引したり、高温の熱(スチームクリーナーや乾燥機)で処理する方法がありますが、完全に駆除するのは困難なため、専門の業者に依頼することが推奨されます。
- 殺虫剤への抵抗性: 一般的な殺虫剤に耐性を持つ「スーパートコジラミ」と呼ばれる個体が増えています。
- 潜伏場所: 狭い隙間に潜んでいるため、殺虫剤が届きにくいです。
- 繁殖力: メスは1日に数個の卵を産み、繁殖力が高いです。卵は殺虫剤が効きにくいとされています。

品川区の小学校が体験した“林間学校トラブル”の詳細
林間学校でトコジラミのトラブルが発生したのは、日光にある品川区の保養所です。
2025年8月上旬、小学校の児童たちが施設に宿泊中、部屋に大量の虫を発見。教員に報告したところ、なんと「他の部屋が空いていない」との理由で、その部屋で寝るように指示されたのです。
さらに驚くべきはその後の対応です。
- 校長は、児童に対して「虫のいない方に避け、明かりをつけて寝なさい」と指示
- しかし、見回りに来た別の教員が「なぜ電気をつけているのか」と怒って電気を消す
- 教員が部屋の入り口で子どもたちを“監視”しながら寝かせるという異様な状況に
この一連のやりとりから見えてくるのは、現場の混乱と、対応の一貫性のなさです。明かりをつけて寝るべきなのか、消すべきなのか、そもそも「虫が確認されている部屋で寝かせるべきだったのか」という根本的な問題が見過ごされています。
トコジラミを家に持ち帰ったケースも 保護者の迅速な対応とは
この件を最初に公表したのは、児童の保護者です。
保護者は帰宅した娘から詳しく話を聞き、「あの虫はおそらくトコジラミだ」と判断。すぐに衣類を乾燥機にかけ、リュックや持ち物を徹底的にチェックしたそうです。娘からは虫は見つかりませんでしたが、他の児童のリュックからトコジラミが発見されるという事態に。
保護者の言葉には怒りと不信感がにじみます。
「数人の先生が目視で虫を確認しているのに、なぜその部屋に寝かせたのでしょうか。明かりをつけて寝なさいという指示が出ていたなら、最初からトコジラミの可能性を疑っていたのでは?」
この保護者の発言からは、「子どもたちを守る立場の大人が、果たして正しい判断をしたのか?」という疑念が生まれて当然です。
“空き部屋なし”は本当だったのか?教育委員会の見解
この件について、品川区教育委員会は8月6日、報道陣の取材に次のように回答しています。
- トコジラミが確認されたのは全42部屋中2部屋のみ
- 「空き部屋がなかった」という学校側の説明は確認できていない
- 同じ施設を使った他の学校からも同日にトコジラミ被害の報告
- お盆前の8月8日までの利用は全面中止
つまり、教育委員会側からすれば、「本当に空き部屋がなかったのかは不明」というのが現時点での見解です。
この発言が事実であれば、「他に部屋がないからここで寝て」とした教員や校長の判断は、保護者に対して事実とは異なる説明をしていた可能性も出てきます。
トコジラミ対策の甘さが招いた問題 学校現場に求められる危機管理
今回の事例から浮かび上がるのは、教育現場における危機管理能力の課題です。
子どもたちを守るはずの教員が、明確に異常があるとわかっている環境に児童をとどめた。そのうえで意思疎通の不備が起き、対応が場当たり的だったことで、児童たちは朝まで眠れず、精神的な不安を抱えることになったのです。
もちろん、当日の状況にはさまざまな制約や判断の難しさがあったことでしょう。しかし、「安全を最優先すべき場面で、十分な対応が取れなかった」ことは、事実として受け止める必要があります。
保護者としてできる対策は?
このような事態が他人事ではないと感じた方も多いのではないでしょうか。今後、学校行事などでお子さんが宿泊を伴うイベントに参加する場合、以下の点をチェックしておくと安心です。
- 宿泊施設の衛生状態や管理体制
- 子どもからの報告をきちんと聞く習慣
- 衣類や持ち物を帰宅後すぐにチェック・洗浄
- トコジラミの予防や駆除方法の基本的知識
教育現場の危機意識の甘さ
子どもたちの安全と健康を最優先に考えるべき学校が、今回のような対応をしてしまった背景には、情報共有の不足、危機感の薄さ、そして想定外の事態への準備不足があったのではないでしょうか。
今後、教育現場にはより高い危機管理意識が求められます。そして私たち大人もまた、子どもたちを守るために、学校や自治体にしっかりと声を届けていく必要があります。