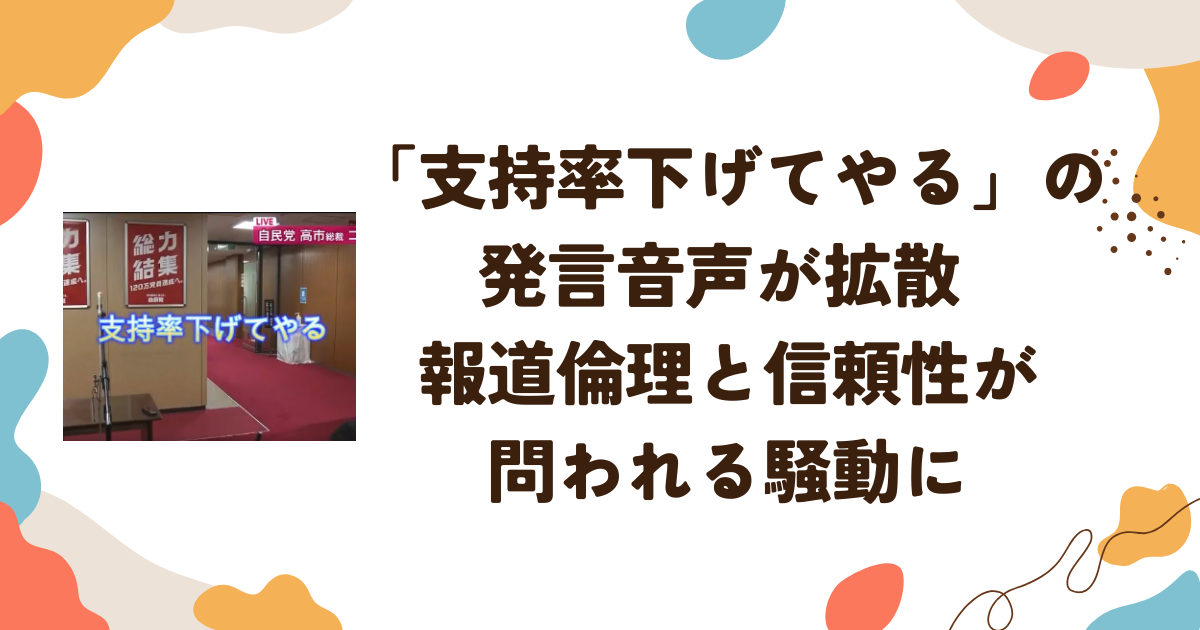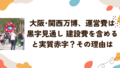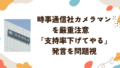2025年10月7日、日本テレビのYouTubeライブで配信された自民党・高市早苗氏の取材現場で、報道関係者とみられる人物から「支持率下げてやる」「支持率が下がるような写真しか出さねーぞ」といった発言が生中継に入り込み、ネット上で大きな話題になりました。
その後、公開済みの映像から問題の音声部分が削除されたこともあり、マスコミ批判や「編集操作・証拠隠滅ではないか」との疑問が相次いでいます。日テレは「弊社の関係者による発言ではない」と否定していますが、報道機関・視聴者双方から説明責任を求める声が高まっています。
本記事では、どのように発言が拡散したのか、日テレの対応、世間の反応・批判について整理し、わかりやすく解説します。
「支持率下げてやる」発言が生中継で拾われた経緯
会見前の配信中に音声が混入
2025年10月7日、高市早苗氏は公明党関係者との会合を終えて自民党本部で報道陣に取材に応じる予定でした。その際に日本テレビ系列が YouTubeライブ中継 を実施。会見開始前からカメラ準備・待機状態で配信が始まっていたところ、画面には映らない位置から「支持率下げてやる」「支持率が下がるような写真しか出さねーぞ」といった声がマイクに入り込みました。
こうした発言がそのまま全国配信されてしまったことがまず火種となりました。
映像の切り取り・編集後公開
その後、YouTubeやニュースサイトで公開されている配信アーカイブには、問題の発言が入っていた冒頭部分が削除された状態で公開されるようになりました。これを見た視聴者から「編集で証拠隠滅を行ったのではないか」という批判が沸き起こりました。
日テレ側は、これを「ライブ収録した本編以外の部分は、見逃し配信用アーカイブ化の過程でカットしている。通常の作業だ」と説明し、編集を認めつつも「関係者の発言ではない」と自社関与を強く否定しています。
日テレ 編集・削除の説明と問題点
日テレの説明とその限界
日テレが公式に述べた主な内容は以下の通りです。
- 問題の音声があった部分はライブ配信時の「本編以外」の領域と見なし、アーカイブ化の際に編集で除外した
- 当該発言は弊社の関係者によるものではない
この説明だけでは「本編以外」とは具体的にどの範囲か(準備中、カメラチェック、マイクチェック時点など)、編集判断を誰がしたのか、元の無編集データ(ログ)を保管しているか、外部からの検証が可能か、という点が明らかになりません。視聴者からすれば「通常の作業」という言葉だけでは納得し難いのが実情です。
証拠隠滅・編集の透明性に関する疑問
編集後に公開されたアーカイブをもって「証拠が残らなければなかったことにできる」という疑念は、マスメディアへの信頼を揺るがす重大な問いになります。
特に、生中継での発言を元に議論が起きた後にその部分を削除する動きは、編集操作や都合の良い情報統制につながる恐れがあります。透明性を保つためには、編集前映像(あるいは編集ログ)を関係機関に公開する制度や説明責任を設定するべきとの指摘が出ています。
「支持率下げてやる」発言は誰か?
発言者の特定はされていない
現時点では、「発言したのはどこの記者か」「所属はどこか」といった情報は公式には確認されていません。複数の報道機関は「把握していない」とコメントしています。
SNSでは憶測が飛び交い、「カメラマン」「報道陣」「会見準備者」などさまざまな候補が挙げられていますが、それらは未確定情報です。
冗談説・雑談説の可能性
一部の音声解析ユーザーは、発言が本気ではなく雑談や冗談の範囲だった可能性を指摘しています。例えば、会見直前の緊張や待機中の雑談の中で軽口が交わされた場面をマイクが拾った、という見方です。
ただし、たとえ冗談であったとしても、「記者」という立場で「支持率を下げる」という表現を軽々しく使うこと自体が、公平性への疑いを招くという批判もあります。
SNS/世論の反応:マスコミ批判と擁護の声
批判・疑問を呈する声
SNS上では、以下のような意見が目立ちます:
- 「メディアは政権批判ありきでやっているのではないか」
- 「報道機関が支持率を操作する意図を持っていると受け取られても仕方ない」
- 「編集して削除するのは証拠隠滅だ」「視聴者を欺く行為だ」
こうした批判は、マスコミ不信や偏向報道への根強い懸念と直結しています。
擁護・慎重な見方も
一方で、以下のように慎重な立場をとる声もあります:
- 「カットされた映像が元どおり存在するかもしれない」
- 「文脈や前後のやりとりを見なければ判断できない」
- 「炎上拡散の速さが議論を先行させている」
つまり、SNSでは「批判」か「懐疑」かで二分されやすいですが、双方ともに一定の根拠を持った意見として交錯しています。
なぜこの騒動が特に注目されたか
タイミング:高市早苗氏の総裁就任直後
高市早苗氏は自民党の新総裁に就任したばかり。就任当初は世論の注目度が高く、報道のトーンひとつで支持率は大きく揺れ動く可能性があります。
そうした節目の時期に、「支持率を下げるような発言」が報道の現場から出たというインパクトは非常に強く、敏感な時期だからこそ炎上が激しくなった側面があります。
メディアと政治の関係への不信感
近年、報道と政治の関係性、偏向報道への不信感、情報操作への懸念は日本でも根強く存在します。
本件は、まさにその懸念が“目に見えるかたち”で表面化した事例といえます。
SNS時代の拡散力
昔ならローカルな出来事で終わったかもしれない音声が、今はXやYouTubeで瞬時に全国に拡散します。一つのショートクリップがトレンド入りし、世論を動かす力を持つ時代。それがこの事件にも強く作用しました。
報道倫理・信頼性の観点から考えるべきこと
公平性・中立性の担保
報道機関は、政治的に中立な姿勢を示すことが最も基本的な使命です。記者個人の感情的発言や、取材者としての立ち位置を逸脱しかねない表現は避けるべきです。
ましてや「支持率を下げてやる」という言葉が公の電波に乗れば、政治的な立ち位置を示す行為とみなされ、視聴者の信頼を損ねます。
編集と削除のルール・説明責任
ライブ配信・録画番組の編集は不可避な作業ですが、どの範囲を編集対象とするか、判断基準や責任所在、元データの保存と第三者検証可否などを明確にする制度設計が必須です。
編集後の映像だけで判断が進むと、「都合のいいものだけを残す」リスクが高まります。
視聴者との信頼関係
視聴者は「映像が事実だ」と信じて番組を視聴します。メディア側は、その信頼を前提にして報道を行うべきです。
信頼を裏切るような印象(編集操作、音声削除、説明不十分な対応など)は、視聴者離れや不信感の深刻化を招きます。
今後の焦点・注目ポイント
以下の点に今後注目しておきたいです:
- 元データやログ公開の可否
日テレが生中継原版(無編集)や音声ログを保管・公開できるか、あるいは第三者機関の検証に応じられるか。 - 社内調査の実施と公表
発言者が社内または現場関係者であれば、調査・処分方針を明らかにする必要があります。 - 報道機関の編集ガイドライン強化
ライブ中継・録画配信の運用ルール、マイク音声管理、編集責任者の明記などの制度化。 - 視聴者からの苦情・第三者機関の審査
放送倫理・番組向上機構(BPO)や放送局への苦情申立てがどう扱われるか。 - メディアと政治の「距離感」の再検討
報道と政治が過度に近くならない構造、メディア自主性の維持、報道機関のチェック機構のあり方。
まとめ
高市早苗氏の生中継で「支持率下げてやる」という発言が流れた事件は、単なる取材現場の騒動を超えて、報道倫理・信頼性を巡る重大な論点を照らし出しました。
重要なのは、憶測や感情だけで論じるのではなく、編集前の元データ、説明責任、検証可能性を求めながら、冷静に事実と論点を整理していくことです。
読者の皆さまも、「報道をそのまま信じる/疑う」という二択ではなく、情報源、編集背景、透明性を意識しながらニュースを見ていただきたいと思います。今後、日テレ・他局・第三者機関からの説明が出た際には、改めて検証記事を更新していく予定です。