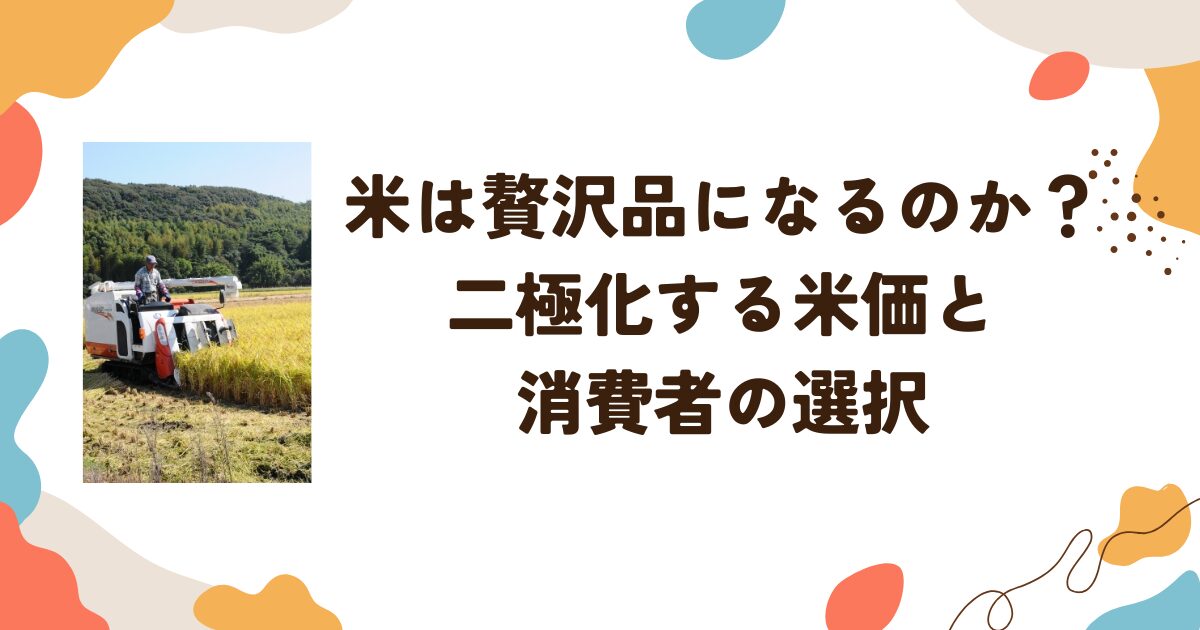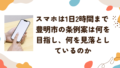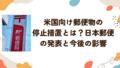夏の終わりから秋にかけて、日本の食卓を豊かに彩る「新米」の季節が訪れました。炊き立てのご飯から立ち上る香りや甘みは、この時期ならではの楽しみです。
しかし今年の新米は、例年以上に高値で売り出されており、多くの消費者がその価格に驚きを隠せません。あるスーパーでは、早生品種の5キロが4,600円前後と、昨年に比べて1.6倍の水準に達しました。
なぜ新米は高くなったのか
今年の新米価格高騰には、複数の要因が絡んでいます。
- JAが引き上げた「概算金」
生産コスト上昇を背景に、JAは農家への前払い金である「概算金」を大幅に引き上げました。これにより卸売価格が高まり、店頭価格も押し上げられました。 - 集荷競争の激化
JAだけでなく、民間の卸売業者も農家に対して高額提示で集荷競争を繰り広げています。そのため、市場全体の仕入れ価格が吊り上がり、店頭価格も上昇せざるを得ない構図になっています。 - 天候不順による収穫不安
少雨や高温などの気候条件が全国的に続き、収穫量や品質に懸念が生じたことも価格を下支えする要因となっています。 - 備蓄米施策の限界
政府は備蓄米の放出を進めていますが、販売期限の延長が決まったとはいえ、新米の価格には大きな影響を与えないという見方も報じられています。
こうした背景から、今年の新米は全国的に「高止まり」が予想されています。
概算金とは?
農家が収穫した米をJAに出荷する際、JAはすぐに代金の全額を支払うわけではありません。米は流通や販売に時間がかかるため、まず「見込みの販売価格」をもとに 前払い金 を支払います。これが「概算金」です。
秋に収穫したばかりの時期でも農家の収入が途切れないようにするための仕組みで、農業経営の安定には欠かせません。
しかし、この概算金が高く設定されると、JAや流通業者はそれを上回る価格で販売しなければならず、結果的に消費者が購入する米の店頭価格が上昇します。
つまり「農家を守るための制度」が、消費者にとっては「米の高値」につながる一因となっているのです。
新米高騰の裏で広がる外国産米
一方、消費者の選択肢として広がりを見せているのが「外国産米」です。タイ米やカリフォルニア米など、海外から輸入される米は、5キロあたり2,000円台から販売されることもあり、国産新米との価格差は倍近くに達します。
また、国産と外国産を混ぜ合わせたブレンド米もスーパーの売り場で存在感を増しています。こうした動きは、家計を重視する消費者にとって現実的な選択肢となりつつあります。
米価は二極化していくのか
新米価格の高騰と外国産米の流通拡大。この2つの動きが進むことで、米価は次第に「二極化」していく可能性があります。
- 高価格帯(国産ブランド米・新米)
有名産地や銘柄米など、品質や安全性、そして「新米ならではの美味しさ」を求める層が支える。特別な食卓や贈答用の需要も根強い。 - 低価格帯(外国産米・ブレンド米)
日常消費用として、家計の負担を抑えたい層に選ばれる。外食産業や加工食品業界でも需要が増加。
この構造が進めば、中間価格帯の米は縮小し、消費者は「ブランドを取るか、価格を取るか」という選択を迫られることになります。
消費者と生産者の認識のギャップ
この「二極化」の背景には、消費者と生産者の間にある認識のギャップが浮き彫りになっています。
- 生産者にとって
資材費、肥料や燃料代の高騰で経営が厳しくなる中、ようやく「適正価格」での販売が見え始めたことに安堵しています。 - 消費者にとって
「米は主食だから安価であるべき」という意識が根強く、高額化に不満を募らせています。高齢世代を中心に「新米を楽しみたいけど財布が追いつかない」といった声も多く聞かれます。
双方の立場は理解できるものの、このギャップをどう埋めるかが課題となっています。

外食産業や家庭への影響
家庭だけでなく、外食産業でも米の高騰は大きな課題です。牛丼チェーンやお弁当業界など、米を主原料とする業態ではコスト増が避けられず、価格転嫁が進めば消費者の負担はさらに広がります。
一方で、安価な外国産米の利用を進める外食チェーンも増えており、ここでも「国産志向」と「価格重視」の二極化が進行しています。
おわりに
今年の新米高騰は、単なる物価上昇にとどまらず、米価の二極化を加速させる可能性を示しています。
「新米の美味しさを味わいたい」という願いと、「家計を守らなければならない」という現実。その間で揺れる消費者の選択は、日本の米市場の姿を大きく変えていくかもしれません。
新米を前に私たちが下す小さな選択が、これからの日本の農業や食文化を形づくる一歩となるのです。