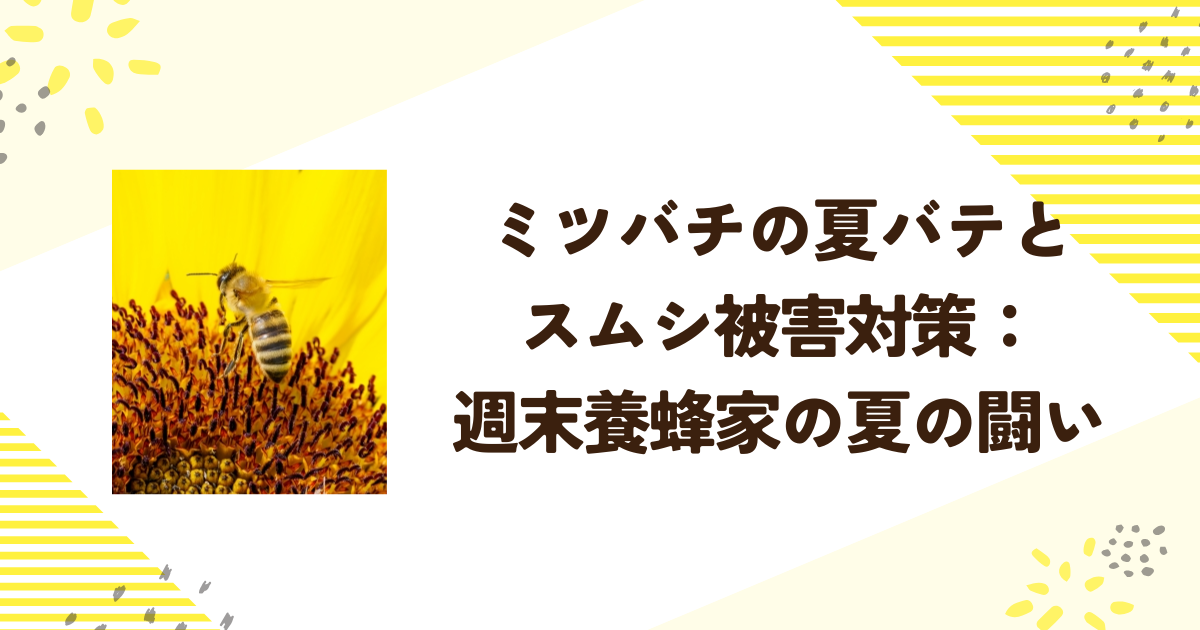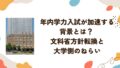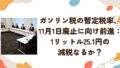自然とふれあいながらミツバチの飼育を楽しむ「週末養蜂家」が近年、全国で増加しています。都市部や郊外に暮らす人々が、自宅の庭や借地などを利用して週末にミツバチの世話を行うライフスタイルは、「自然回帰」や「自家製ハチミツ」への憧れとも相まって、注目を集めています。
しかし、夏の暑さはミツバチにとっても、養蜂家にとっても厳しい試練の季節です。特に夏バテとスムシ被害は、初心者が見落としがちな深刻な問題として養蜂界でも警戒されています。この記事では、週末養蜂家が知っておくべき「夏の蜂対策」をわかりやすく解説します。
週末養蜂家が増えている理由
・手軽な副業や趣味としての魅力
・自然志向の高まりと「自家製ハチミツ」ブーム
・都市型養蜂(都市の屋上や庭など)への関心
・地方移住者による里山利用
実際には「1群から始める」「養蜂教室で学ぶ」「採蜜体験から入る」といったステップを踏む人も多く、特に30〜50代の男性や、夫婦で取り組む人も増えています。
ただし、夏場の管理が最大の関門。週に1~2回しか巣箱を見られないというスタイルでは、急激な環境変化への対応が遅れがちです。

暑さとミツバチの“夏バテ”
ミツバチは元来、高温多湿には弱い昆虫です。巣内の最適温度は32~35℃ほど。これを超えると、働きバチが羽を震わせて風を送ることで巣を冷やします。また、水を運び、巣に撒いて気化熱で冷やす方法も使います。
しかし、近年の猛暑ではその努力も追いつかず、以下のような“夏バテ”症状が見られるようになります:
- 女王バチが産卵しなくなる
- 働き蜂の動きが鈍くなる
- 巣内で死亡する蜂が増える
- 巣が過密になり換気が追いつかない
さらに、日中の急激な気温上昇や雨の減少による水不足も、蜂群にとって命取りです。

夏バテ対策:暑さから巣箱を守る方法
1. 日陰を確保する
・木陰や人工的なすだれ、寒冷紗(遮光ネット)を活用
・巣箱の上に断熱シートをかぶせる
・風通しの良い場所を選ぶ(斜面、林縁など)
2. 巣箱の構造を工夫する
・底を金網にして通気性を上げる(網底式巣箱)
・巣門(出入口)を広くして風の出入りを良くする
・熱がこもりやすいプラスチック巣箱より、木製の通気性の良いものを使用
3. 水を切らさない
・近くに浅い水場を用意(ビーキーパー用水飲み器など)
・スポンジや石に水を含ませて、蜂が安全に止まれるようにする
スムシ被害とは?──「共存できる虫」が脅威に変わるとき
「スムシ被害」とは、ミツバチの巣箱や巣板がガの幼虫(スムシ)によって食い荒らされることを指します。特に問題となるのは、ハチノスツヅリガやウスグロツヅリガといったガの仲間の幼虫です。
これらの幼虫は、ミツバチの巣に入り込み、蜜蝋(みつろう)や花粉、さらには幼虫や蛹までも餌として成長していきます。
本来は共存できる存在
実は、スムシは自然界において完全な「害虫」ではありません。たとえば在来種のウスグロツヅリガは、ミツバチの巣の中で不要になった巣クズや死骸などを片付ける、いわば「清掃屋」としての側面も持っています。
元気なミツバチの群れ(強群)であれば、スムシが侵入しても、ミツバチたちがその幼虫を捕らえ、巣の外へ運び出したり、噛み殺して処理することができます。自然環境下では、こうしたバランスがある程度保たれており、スムシも“共存可能な生物”のひとつでした。
なぜ「被害」になるのか?
問題は、養蜂という人為的な環境でこのバランスが崩れてしまうことです。
▸ 群れが弱っていると…
病気、農薬の影響、蜜源不足などで蜂の数が減っている巣箱(弱群)は、スムシの侵入を防ぐ防衛力が低下します。ミツバチが巣板全体を覆えないため、スムシは自由に移動しながら巣を食い荒らすことが可能になります。
▸ 逃げられない養蜂環境
自然界のミツバチであれば、スムシが大量発生した巣を放棄して逃げる(逃去)という選択肢があります。しかし、養蜂場の巣箱では「逃去」は難しいため、スムシが蔓延しやすく、被害も拡大しやすいという側面があります。
スムシの種類にも注意
特に注意すべきは、ハチノスツヅリガと呼ばれるガの一種です。これは西洋ミツバチとともに日本に持ち込まれたとされ、在来種のスムシよりも大型で繁殖力が高く、被害が大きくなる傾向があります。
そのため、外来スムシが原因の被害は、特に都市部や温暖な地域で深刻化しつつあります。

温暖化とスムシ──「気温上昇」がもたらす新たな脅威
スムシ(ハチノスツヅリガ)の成長と気温の関係
スムシ(ハチノスツヅリガ)の成長速度は、気温に大きく左右されることが知られています。特に気温が高くなる夏場には、その活動が著しく活発になり、養蜂場における被害も深刻化する傾向があります。
一般に、気温が20℃を超えるとスムシの活動が本格化し、25℃を超えると爆発的に繁殖速度が上がるとされています。中でも28℃前後は最も活性が高く、次々と新たな幼虫が現れるような状態になります。逆に、発育が停止するとされる温度(発育ゼロ点)は約5℃であり、寒冷な季節には成長が極端に鈍化します。
驚異的な成長スピード
ハチノスツヅリガの成長サイクルは、高温下では非常に短期間で進行します。たとえば、25℃の環境下では卵から孵化するまでに約4~5日、成虫になるまでには約50~60日とされています。
この期間の中でも特に注意が必要なのが「幼虫期」です。スムシの幼虫は、孵化後およそ2週間も経てば、ミツバチの成虫よりも体格が大きくなることがあり、その時点でミツバチたちが物理的に排除するのが難しくなるケースもあります。このように、幼虫は蜜蝋や花粉、巣内のクズや死骸を大量に摂取し、急速に成長します。
成長のプロセスと被害の拡大
具体的な成長の流れは以下のとおりです(気温25~30℃の最適環境下の場合):
- 卵(数日間):巣板の隙間などに産み付けられます。
- 幼虫(約3週間~1ヶ月半):蜜蝋、花粉、ミツバチの幼虫や死骸などを食べながら急速に成長。終齢幼虫になると体長数cmに達し、巣板の構造に深刻なダメージを与えます。
- 蛹(10~20日程度):巣板や巣箱の木材内部に穴を掘って繭を作り、その中で蛹化します。
- 成虫(数日後):羽化してすぐに交尾し、再び産卵を始めます。
このサイクルが、短期間で繰り返されるため、ひとたび侵入を許すと巣箱内が瞬く間にスムシだらけになってしまうリスクがあります。
夏場のスムシ対策が重要な理由
特に夏場は、気温の上昇に伴ってスムシの繁殖が加速しやすくなります。そのため、養蜂家にとってこの時期は、スムシによる巣板の食害や糸の発生、巣箱の構造破壊といったリスクへの対処が欠かせません。
孵化からわずか2週間程度で、巣の中を支配するほどの大きさに成長するスムシの幼虫は、まさに“見えない脅威”です。ミツバチの数が少ない弱った群れでは、これに対応することができず、最悪の場合には群れが崩壊することもあります。
こうした背景から、夏季におけるスムシ対策は、養蜂を営むうえでの最優先課題の一つとなっています。
スムシ被害の特徴と痕跡
スムシによる被害は、見た目にも分かりやすい兆候がいくつかあります。
- 巣板や蜜蝋の穴・トンネル状の食害
- 白い糸状の繭(糸を吐いて移動・巣作り)
- 幼虫のフン、繭のカス、死骸の残骸
- ミツバチの活動鈍化、逃去、群れの全滅
また、スムシの幼虫は、巣箱の木材をかじって傷をつけるため、巣箱自体にも深刻なダメージを与えることがあります。
スムシ対策:日々の管理が被害を防ぐカギ
スムシ被害は、養蜂家にとって見過ごせない大きな問題ですが、日頃の予防と早期発見によって、大きな被害を防ぐことが可能です。
まずは予防が第一
スムシは一度増えると駆除が難しいため、「繁殖させない」ことが最大の防御策です。
- 強群の維持:元気な群れは、スムシの侵入を自力で排除できます。ミツバチの数を保ち、病気やダニの管理、必要に応じた給餌も忘れずに。
- 巣箱の衛生管理:底板の巣くずや死骸、カビた花粉はスムシの餌になります。週1回を目安に掃除し、清潔な環境を保ちましょう。
- 通気と湿気対策:巣箱の設置場所は風通しのよいところを選び、底板に通気口を設けるなどして湿気をこもらせないようにします。
- 夜間の巣門調整:スムシは夜に活動するため、夜は巣門を狭くして侵入を防ぐ工夫も有効です。
スムシを見つけたら即対応
- 巣箱の点検時には、白い糸を吐いたトンネル状の巣板やスムシ幼虫の姿がないかチェック。
- 見つけたら除去し、被害を受けた巣板は取り外すようにしましょう。
巣板の安全な保管方法
空になった巣板はスムシにとって最高の繁殖場所。使用しない巣板は保管方法が重要です。
- 冷凍保存(-20℃で4時間以上):卵〜蛹までを完全に死滅させる確実な方法。
- 酢酸燻蒸:密閉容器で酢酸を使って殺虫する方法。ただし、取り扱いには十分注意が必要です。
- 二硫化炭素は過去に使われていましたが、安全性の問題から現在は推奨されていません。
微生物資材や薬剤の活用
- BT剤(スムシっ子カード、セルタンB401など):スムシの幼虫にだけ作用する生物農薬で、予防や初期段階の駆除に効果的です。
- えひめAI:納豆菌や酵母などから作られる自家製微生物資材。小さなスムシ幼虫の増殖を抑える効果が期待されていますが、3mm以上の幼虫には効きません。
巣箱の工夫で防ぐ
一部の養蜂家は、掃除しやすくスムシが住みにくい巣箱の構造を採用しています。たとえば、底板を網状にして通気を良くし、巣くずが自然に落ちるような設計が有効です。
捕虫器をDIYする方法もSNSで紹介されていますので補助的に利用するのも良いかもしれません。
自然と共に、夏を乗り越えるために
週末養蜂は、自然との対話であり、命を育む営みです。しかし夏は、暑さと虫害という“二重苦”の季節。だからこそ、ミツバチの視点で環境を整えることが何より大切です。
- 巣箱の暑さ対策(通気性・日陰・水)
- スムシの予防と徹底した衛生管理
- 定期的な点検と蜂群の健康維持
これらを押さえれば、初心者の週末養蜂家でも、健康な蜂群と美味しいハチミツを手に入れることができるでしょう。ミツバチと共に、今年の夏も元気に乗り越えていきたいですね。