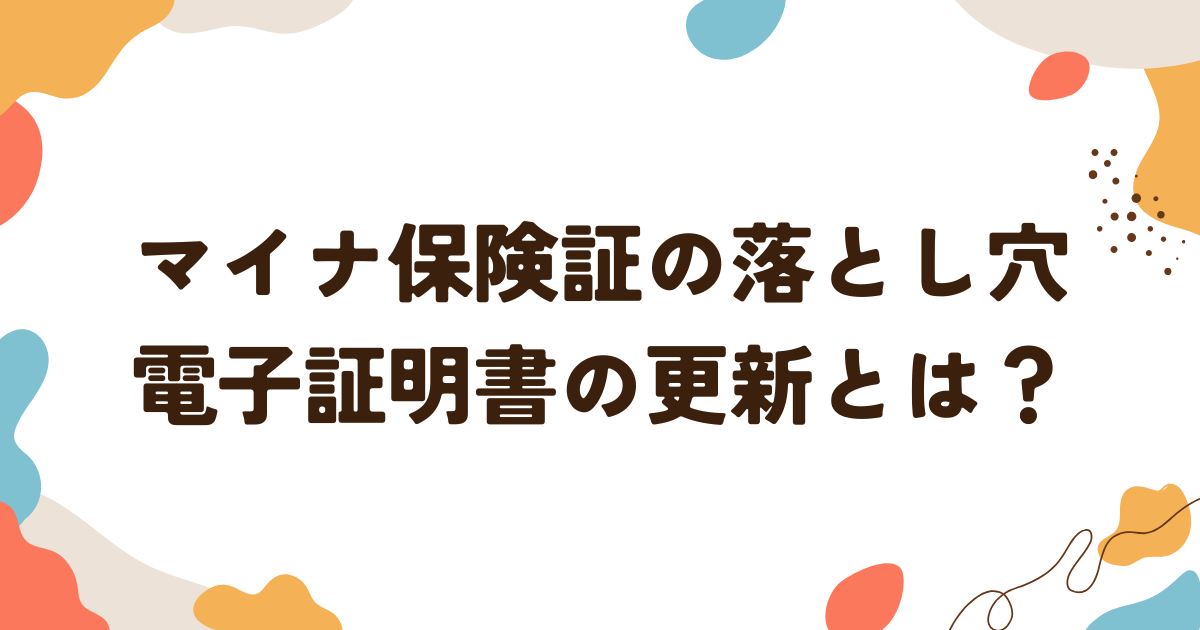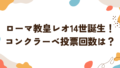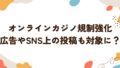2024年12月から、従来の健康保険証の新規発行が終了し、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」への移行が進められています。
マイナ保険証は、医療情報の一元管理や手続きの簡素化など、多くのメリットがあるとされています。しかし、その一方で、特に「更新手続き」に関する課題が浮き彫りになっています。
今回は、マイナ保険証の仕組みや更新手続きの実態、そしてその課題について解説します。
見落とされがちな「期限切れ」
マイナ保険証は、医療の効率化や利便性向上を目的とした仕組みとしてスタートしました。薬の履歴が共有できる、医療費控除が簡素化される、保険証を持ち歩く必要がなくなる――そうしたメリットが強調されがちですが、その裏で多くの人がつまずいているのが「更新手続きの複雑さ」です。
従来の健康保険証は、有効期限が近づくと自動で新しいものが郵送され、特別な手続きは不要でした。しかし、マイナ保険証は違います。カード自体の有効期限は10年(18歳以上)ですが、内蔵された電子証明書は5年で期限切れとなります。しかも、その事実や更新時期が分かりづらく、うっかり期限が切れていたことで「マイナ保険証が使えなかった」という事例が、いま全国の医療機関で増加しているのです。
更新手続きが「不便さ」の原因に
さらに問題なのは、その更新手続きがとても不便であるという点です。電子証明書の更新は、基本的に自治体の窓口での対面手続きが必須。忙しいビジネスパーソンや子育て世代、高齢者にとっては、わざわざ市役所へ出向く手間が大きな負担になります。オンラインやコンビニでの対応が進んでいない現状では、「便利なはずのマイナ保険証」がかえって“使いづらい存在”になってしまっているのです。
2026年には、マイナンバーカードの新バージョンが導入され、電子証明書とカード本体の有効期限が10年で統一される予定ですが、現在すでにカードを持っている利用者にとっては、今がもっともトラブルが起こりやすいタイミングとも言えます。前倒しで新カードの申請ができるようにする制度改正や、高齢者・交通弱者への出張更新対応など、もっと柔軟な仕組みが求められています。
マイナ保険証とは?
マイナ保険証とは、マイナンバーカードに健康保険証の機能を持たせたものです。これにより、医療機関での受付がスムーズになり、薬剤情報や特定健診情報の共有が可能になるなど、医療の質の向上が期待されています。
また、確定申告時の医療費控除の手続きが簡素化されるなど、生活面でも利便性が向上します。
従来の健康保険証は使えないのか?
2024年12月以降、従来の健康保険証の新規発行は停止されましたが、現在手元にある有効な保険証は、最長で2025年12月まで使用可能です。その後は、マイナ保険証または「資格確認書」を利用することになります。
資格確認書は、マイナンバーカードを持たない方や、マイナ保険証を利用しない方に対して、保険者から発行される書類で、医療機関での受診時に提示することで、保険診療を受けることができます。
マイナンバーカードを持っていない場合
マイナンバーカードを持っていない方は、引き続き従来の健康保険証(2025年12月まで)や資格確認書を利用して医療機関を受診することができます。
申請は、原則として住まいの自治体の窓口またはオンラインで手続きを行います。窓口では、交付申請書に必要事項を記入し、顔写真を貼付して提出します。オンライン申請は、マイナンバーカード総合サイトから手続きを進めます。
マイナ保険証の登録方法
マイナ保険証を利用するには、以下の手続きが必要です。
- 自治体の窓口またはオンラインで手続きを行い、マイナンバーカードを取得する。
- マイナポータルや対応する医療機関・薬局の窓口で、健康保険証としての利用登録を行う。
登録後は、医療機関や薬局でマイナンバーカードを提示することで、健康保険証として利用できます。
厚生労働省:マイナンバーカードの健康保険証利用について
マイナポータル:マイナンバーカードの健康保険証利用
更新手続きの実態と課題
マイナンバーカードには、カード自体の有効期限(10年)と、電子証明書の有効期限(5年)が設定されています。電子証明書が失効しても3か月間は利用できますが、それを過ぎると保険証としての機能を失い、マイナ保険証としての機能が停止します。

更新手続きは、原則として市区町村の窓口で行う必要があり、オンラインでの手続きは限定的です。また、更新の通知は有効期限の2〜3か月前に送付されますが、見落としや手続きの遅れにより、電子証明書が失効してしまうケースが増加しています。
特に高齢者や多忙な方にとって、窓口での手続きは大きな負担となっており、更新手続きの簡素化やオンライン対応の拡充が求められています。
今後の展望と対応策
政府は、2026年からマイナンバーカードと電子証明書の有効期限を10年に統一する方針を示しています。これにより、更新手続きの頻度が減少し、利用者の負担が軽減されることが期待されています。
また、コンビニエンスストアでの更新手続きや、オンラインでの手続きの拡充など、利便性向上のための施策も検討されています。
しかし、現時点では、更新手続きの煩雑さや情報の周知不足など、課題が残されています。利用者自身が有効期限を把握し、適切なタイミングで更新手続きを行うことが重要です。
まとめ
マイナ保険証は、医療の質の向上や手続きの簡素化など、多くのメリットを提供する制度です。しかし、その利便性を最大限に活用するためには、更新手続きの課題を理解し、適切に対応することが求められます。
今後、制度の改善や手続きの簡素化が進むことが期待されますが、現時点では、利用者自身が情報を収集し、適切な対応を行うことが重要です。
マイナ保険証の利用を検討している方は、早めにマイナンバーカードの取得と健康保険証としての登録を行い、更新手続きのスケジュールを把握しておくことをおすすめします。