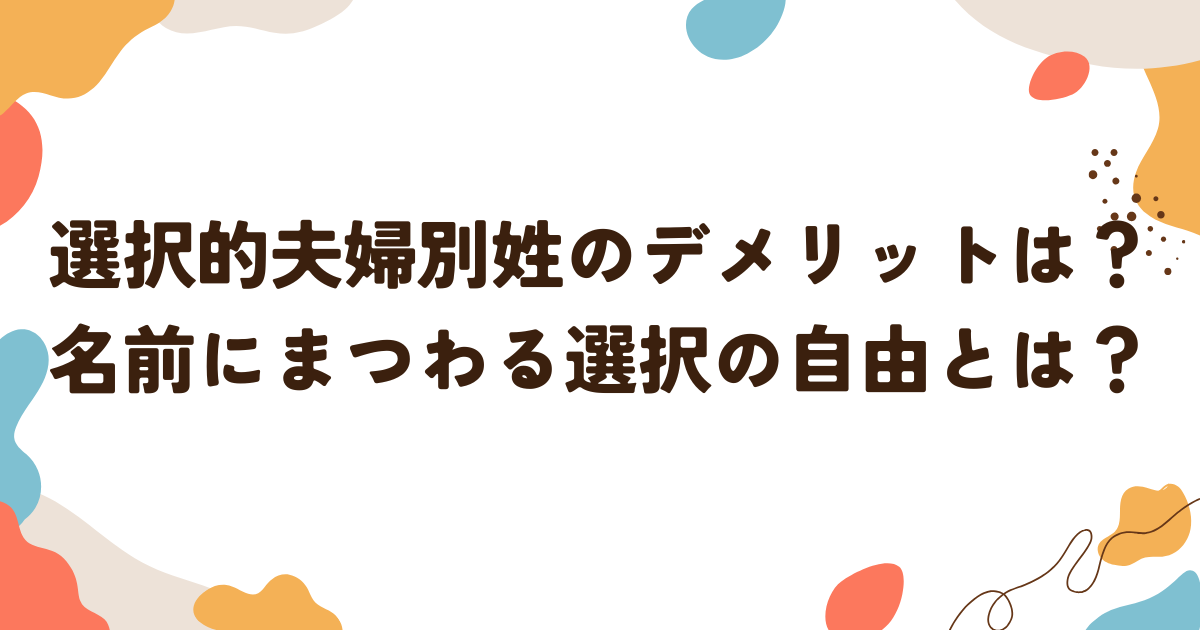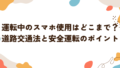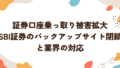2025年4月30日、立憲民主党が「選択的夫婦別姓制度」の導入を目指す民法改正案を衆議院に提出しました。今回の法案は、自民党内の一部や日本維新の会などが慎重な姿勢を見せる中、どこまで他党の理解を得られるかが焦点となっています。
このニュースを受けて、SNSなどでは「姓なんてどうでもいいのでは?」「なぜそこまでこだわる必要があるの?」といった素朴な疑問から、「変えたくない人の権利を守ってほしい」といった切実な声まで、様々な反応が広がっています。
では、選択的夫婦別姓の議論はいつから始まり、今どのような状況にあるのでしょうか? そして海外ではどのような制度が採用されているのでしょうか? 歴史的背景や比較を通して、制度の意味をあらためて考えてみましょう。
世界各国の夫婦別姓制度はどうなっている?
日本では、現在でも夫婦は同じ姓を名乗ることが法律で義務づけられています(現行民法750条)。世界的に見ると、これはむしろ少数派です。
以下は、代表的な国々の制度の概要です:
- アメリカ:姓の選択は完全に自由。夫婦別姓、夫が妻の姓を選ぶことも可能。
- イギリス:法的制限はなく、姓は自由に決められます。
- ドイツ:1994年の改正で選択的夫婦別姓が可能に。
- フランス:婚姻後も原則として出生時の姓(法的には「名」)を保持。
- スウェーデン:個々の自由に任されており、制度として柔軟。
- 韓国:伝統的に夫婦別姓が根付いており、法的にも定着しています。
- 中国:1950年の婚姻法以来、夫婦別姓が法律で保障。
このように、多くの国では、夫婦がどの姓を名乗るかを自由に決定できる仕組みが整っています。
なぜ中国では「夫婦別姓」が当たり前なのか?
中国では、結婚しても姓を変えない「夫婦別姓」が長く慣習となっています。この背景には、古代から続く儒教的な家族観があります。
中国では古代から夫婦別姓が一般的でした。これは、儒教思想に基づく父系家族制度の中で、女性が結婚後も自らの姓を保持することが自然とされていたためです。女性は「夫の家に入る」存在でありながらも、個人としての姓を持ち続けることが当たり前とされてきました。
近代以降もその流れは変わりません。中華人民共和国が成立した直後、1950年に施行された「婚姻法」によって、正式に夫婦の姓を変更しない権利が保障されました。これは男女平等の理念に基づいた法律であり、その後の民法典にも引き継がれています。
このように、中国では「姓を変える必要がない」という考えが自然に社会に根付いているのです。
日本の「選択的夫婦別姓」議論の歴史
夫婦別姓をめぐる議論が本格化したのは、1990年代に入ってからです。
1996年、法制審議会は「選択的夫婦別姓制度」の導入を含む民法改正案を答申。しかし、自民党保守派の強い反発により、法案は国会に提出されることはありませんでした。
その後も、市民運動や訴訟、地方議会での意見書提出などを通じて議論は継続。2015年には最高裁で「夫婦同姓は合憲」との判断が出されたものの、同時に「立法による検討の余地がある」とも付記され、社会の関心は根強く続いています。
近年では、女性の社会進出や再婚・国際結婚の増加、職場での旧姓使用の広まりを背景に、「姓を選ぶ自由」に対する関心が高まり続けています。
賛否両論とこれからの課題
選択的夫婦別姓の導入については、賛否が分かれます。
賛成意見
- 結婚によって姓を変える手続きが煩雑で、特に女性に負担が偏っている。
- キャリアや学術上の実績が旧姓に紐づいているケースが多く、姓の変更が障害になる。
- 憲法が保障する「個人の尊厳」や「両性の本質的平等」との整合性。
反対意見
- 伝統的な家族観が崩れる恐れがある。
- 戸籍制度の維持が困難になるのでは、という懸念。
- 「同じ家族で名字が違うと子どもが混乱する」といった声。
中には「そんな制度、どうでもいいのでは」といった意見もありますが、重要なのは、誰かが「変えたい」と願ったときにその選択肢があるかどうかです。「こだわる」ことが問題なのではなく、「選べない」ことが問題なのです。
選択的夫婦別姓に懸念される点とは?
選択的夫婦別姓の導入に慎重な意見があることも事実です。その多くは「家族の一体感」や「戸籍制度の維持」に関する懸念に根ざしています。
例えば、「夫婦や子どもが異なる姓を名乗ることになれば、外見上“家族”と分かりにくくなり、社会的な不便が生じるのでは」という声があります。とくに子どもに関しては、「兄弟姉妹で姓が異なると、学校や地域社会で混乱を招くのでは」と心配する保護者も少なくありません。
また、現在の戸籍制度は「家単位」で管理されているため、別姓を認めることで制度の根幹が揺らぐという指摘もあります。これまで「氏=家族の単位」とされてきた法制度との整合性をどう取るかは、法案設計上の重要な課題です。
さらに、「姓が異なることによる遺産相続や扶養の取り扱い、銀行口座などの名義管理が複雑になるのでは」といった、実務的な問題を指摘する声もあります。こうした細かい制度設計への不安が、議論の足かせになっている側面も否めません。
とはいえ、これらの懸念は制度設計や運用ルールを丁寧に整えることで対応可能であるという意見も多く、国会や市民レベルでの議論が求められています。
おわりに
夫婦別姓制度に対する関心が再び高まりつつある今、「いつからこの議論が続いているのか?」という点に立ち返ることも大切です。すでに30年近くにわたって続いている議論の根底には、多様な家族のあり方を認める社会への模索があります。
姓は単なる記号ではなく、個人の人生やアイデンティティと密接に結びついたもの。今後の国会審議を通じて、「選べる社会」の実現に一歩近づけるのか──私たち一人ひとりが注目していく必要がありそうです。