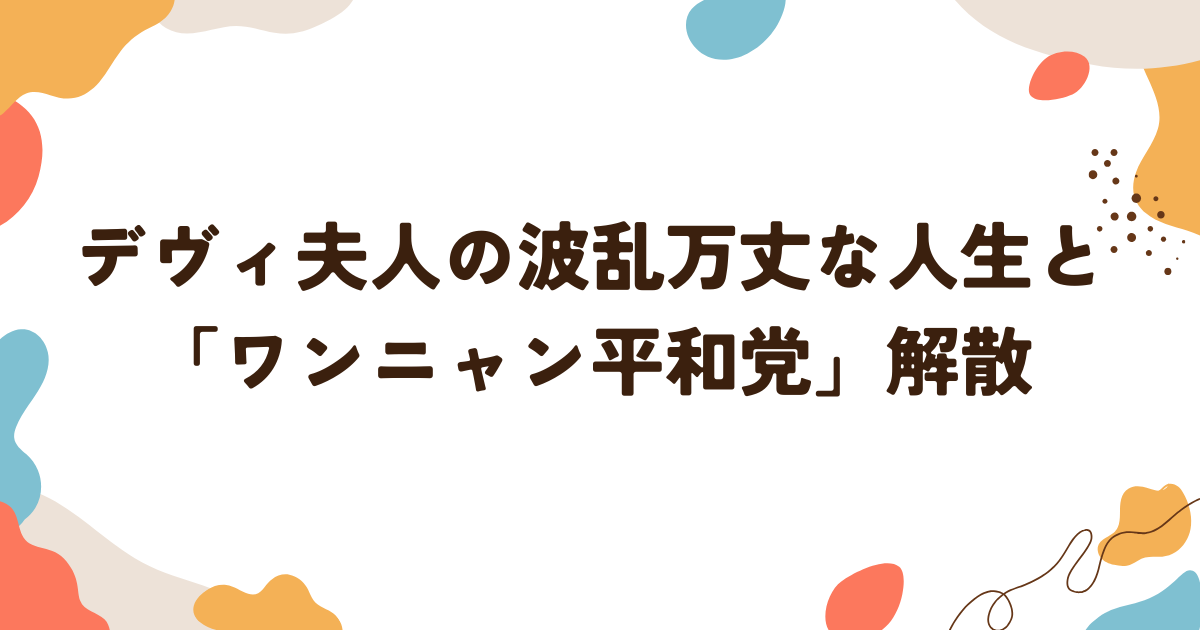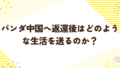2025年4月25日、タレントであり動物愛護活動家として知られるデヴィ・スカルノさん(通称:デヴィ夫人)が代表を務める政治団体「12(ワンニャン)平和党」の解散が発表されました。公式ホームページの動画で、デヴィ夫人は参議院選挙に向けた準備を進めていたものの、やむを得ない事情から活動を終了する決断に至ったと話しています。
「選挙プランナーだった藤川晋之助さんの突然のご逝去、そして私自身の日本国籍への帰化承認が未解決のままであることが理由です」とデヴィ夫人は説明。また、「支えてくださった皆様に心からおわび申し上げます」と、支援者への感謝と謝罪の気持ちも表しました。
デヴィ夫人の本名、若い頃は?
デヴィ夫人は1940年、東京生まれ。本名はラトナ・サリ・デヴィ・スカルノ(旧姓:根本七保子)さんです。
父親は大工の棟梁だったそうです。
太平洋戦争中は福島県に疎開し、戦後は家庭の事情から早くに働き始めました。中学卒業後は千代田生命に入社し、昼は会社勤め、夜は定時制高校に通いながらアルバイトを掛け持ちし、女優も目指すという非常に多忙な生活を送っていました。
その後、赤坂の高級クラブでのアルバイトを通じて英語力を身につけ、1959年、インドネシアのスカルノ大統領と出会います。スカルノ大統領に見初められ、彼の招きでインドネシアへ渡り、19歳で結婚。スカルノ大統領から「ラトナ・サリ・デヴィ(宝石の妖精)」という名前を贈られました。
デヴィ夫人の波乱万丈の人生
しかし1965年、インドネシアでクーデターが発生し、スカルノ大統領は失脚。デヴィ夫人は安全のために日本を経てパリへと渡り、そこで社交界の華として活躍。「東洋の真珠」とも呼ばれました。娘のカリナさんはフランスで誕生し、現在はアメリカで暮らしています。
1979年には、娘を迎える準備のために一人でインドネシア・ジャカルタへ戻り、スハルト政権下での厳しい環境の中、自ら「馬車馬のように働いた」と語るほどの努力を重ねました。ヨーロッパの5つの大手企業のエージェントとして石油関連ビジネスで成功を収め、自らの力でジャカルタの高級住宅地・メンテン地区に家を建てたといいます。
その後もデヴィ夫人は事業家・文化人・タレントとして活動の幅を広げ、日本を拠点に慈善活動やテレビ出演など多方面で存在感を示し続けています。
ワンニャン平和党とは?
「12(ワンニャン)平和党」は、動物愛護をテーマに立ち上げられた政党で、デヴィ夫人と「世界愛犬連盟」の堀池宏さんが共同代表を務めていました。
掲げていた主な政策は次の通りです:
- 犬や猫の食用を禁止する法律の制定
- 動物虐待への罰則強化
- アニマルポリスの設置
こうしたテーマを掲げ、全国比例区や大都市圏で10〜30人の候補者を擁立する方針でした。過去にも特定のテーマに絞った「ワンイシュー政党」が議席を獲得した実績があることから、同党にも可能性があると見られていました。
デヴィ夫人の暴行疑惑と世間の反応
ところが、2025年4月16日、デヴィ夫人が都内の飲食店で女性にグラスを投げたとされる事件で書類送検されたというニュースが報じられました。被害女性は顔を37針縫う怪我を負ったとの報道もあり、「シャンパン事件」としてネット上でも話題になりました。
この事件を受けて、「動物には優しいけれど、人間にはどうなのか?」という疑問の声が広がっています。暴力的な一面が報道されることで、動物愛護の主張そのものの説得力も揺らいでしまうリスクがあります。
解散の背景と現実的な判断
今回の解散にはいくつかの要因が重なっていたようです。デヴィ夫人自身の帰化手続きの遅れによって立候補が難しくなったことや、選挙プランナーである藤川氏の死去は、政党運営にとって大きな痛手でした。また、暴行疑惑の影響で世論の支持を得ることも難しくなり、選挙戦に入るだけの体制づくりが進みませんでした。
こうした状況を受けての解散は、現実的で妥当な判断だったのではないかと考えられます。
テーマ特化型政党の意味
ワンニャン平和党のように、特定の社会課題にフォーカスした政党の存在は、政治の多様性を示すものです。動物福祉は軽視されがちな分野ですが、そこに特化して政策を打ち出す姿勢は評価に値します。
ただし、政治活動には「誰が語るのか」がとても重要です。政策の中身だけでなく、その発信者の言動や過去の行動も問われます。人々が求めるのは、信頼できるリーダーです。
また、若い世代の政治参加を促す声や、議員報酬の見直しなど制度改革を求める意見も根強くあります。私たちが政治を見る目を養うには、「誰が、何を、どう実現しようとしているのか」を見極めることが大切です。
今回のワンニャン平和党の解散は残念ではありますが、動物福祉や政治参加のあり方について改めて考えるきっかけとなりました。今後もこうしたテーマに関心を持ち、前向きな議論が広がっていくことを期待したいと思います。