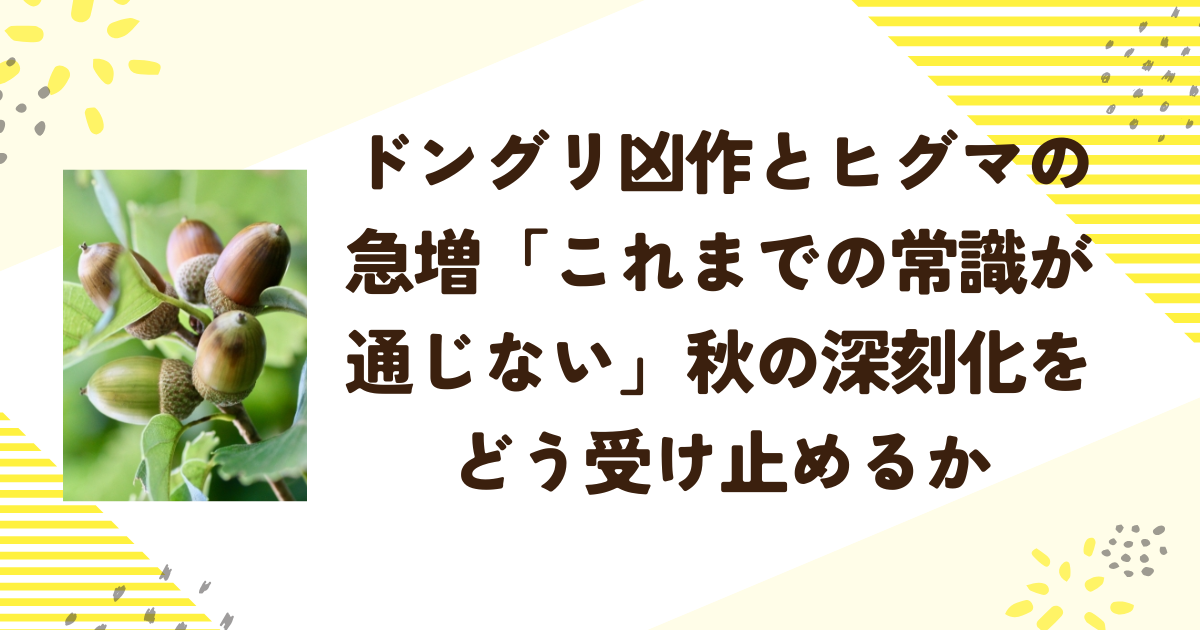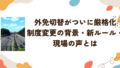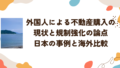2025年、北海道の調査によるとミズナラやブナなどのドングリ類が広範囲で凶作となりました。札幌市では「今までの常識が通じない」と関係者が語るほどヒグマの出没件数が増え、注意特別期間も11月末まで延長されています。
では、なぜ今年はここまでヒグマが人里に現れるのか。背景には気象条件の変化、森の環境、狩猟者の減少、生態系のゆがみなど複数の要因が重なっています。ここでは、最新の情報をもとに原因と対策をわかりやすく解説します。
今年はなぜドングリが不作なのか
2025年の北海道では、ヒグマの主要な秋の食料となる木の実類が広範囲で凶作・不作となっており、人里への出没増加が懸念されます。
北海道が2005年から実施している秋の木の実の豊凶調査によると、2025年は特に以下の点が顕著でした。
- ミズナラ(ドングリ): 9管内で凶作。
- ブナ: 道南を中心に不作〜凶作。
- ヤマブドウやコクワ(サルナシ): 並作〜不作が多い。
ヒグマはこれらのドングリ類、ヤマブドウ、コクワといった堅果・液果を秋の主要食料としていますが、実りが悪い背景には気象の不安定さがあります。

凶作の背景にある気象要因
ドングリ類をはじめとする木の実の凶作は、主に以下の気象条件が影響しています。
- 開花・受粉期の不順:
- 開花期に低温や長雨が重なると、受粉がうまくいかず、実を結ぶ量が減少します。
- 夏の気象ストレス:
- 夏場の高温や乾燥は、成長途中の実を落とす原因となります。
- 気候変動による変動の増大:
- 近年の気候変動により、これらの気象条件が極端になりやすく、年ごとの豊凶の変動幅が大きくなっています。
山で十分な実りが得られない場合、ヒグマは冬眠前に必要な栄養(脂肪)を蓄えることができません。その結果、餌を求めて人里へ降りてくるケースが急増するため、警戒が必要です。
ドングリの不作だけではない、ヒグマ出没が増える要因
① ドングリなどの食料不足
ヒグマは冬眠前に大量の脂肪を蓄える必要があり、秋は最も重要な時期です。木の実が少ない年は、行動範囲を広げて人間の生活圏に侵入しやすくなります。生ごみ、果樹、家庭菜園、ペットフードなども餌として狙われます。
② ハンターの不足と高齢化
北海道に限らず、狩猟者の数は減少傾向にあります。
- 1980年代:約19万人
- 現在(全国):約4万人
- 60代以上が7割近く
若手のハンターが少ないことで、有害駆除や出没対応に間に合わない地域が増えています。また、山奥での駆除や追跡には体力と人員が必要ですが、それを支える体制も弱まっています。
③ 暖冬で子グマの生存率が上昇
本来、子グマの多くは冬眠中に命を落とすことがあります。しかし近年は暖冬傾向が続き、餓死・凍死が減少。結果として個体数が増え、人との接触機会も高まっています。さらに、冬眠をせずに活動するヒグマも出始めています。

森林環境も影響 人工林と原生林の問題
かつてヒグマは、原生林を中心に生活していました。しかし戦後の林業拡大などによりスギやカラマツなどの人工林が増え、本来の生態系が変化しました。
- ミズナラやブナなどの広葉樹林が減少
- ドングリが安定的に実りにくい環境
- 昆虫や小動物など他の餌も減少
専門家からは「人工林を減らし、広葉樹中心の森に戻すべき」との声が上がっています。ただし、森林再生は数十年規模の時間が必要で、短期的な解決策にはなりません。
「人間の味を覚えたヒグマ」は本当か?
「人間を襲うクマは、人肉や血の味を覚えたのでは?」という声もあります。実際、人身事故後に再び人間に近づいた例も報告されていますが、専門家の見解は次のように整理されます。
- 味を覚えるというより「人を恐れなくなる」ことが問題
- 生ごみや残飯を食べた経験が学習につながる
- ペットや家畜を襲う例も、人と結びつける要因になる
重要なのは、クマに「人間由来の食べ物を与えない・近づけない」環境を作ることです。
私たちにできるヒグマ対策
出没が続く現在は、地域や個人でも対策が求められています。
人里での注意点
- 生ごみ・コンポストは放置しない
- 外にペットフードを置かない
- 果樹や畑は収穫を早める
- 飼育中の家畜は柵や電気柵を活用
外出時の行動
- 早朝・夕方・暗い時間を避ける
- 鈴やラジオなどで存在を知らせる
- 複数人で行動する
- フンや足跡、爪痕を見つけたら近づかない
被害を避けるポイント
- 熊鈴・スプレー・ライトの携帯
- 子どもや高齢者への情報共有
- 通学路や公園での啓発
「国が主体となるべきか?」という議論
現在、ヒグマ対策は都道府県や自治体、猟友会が中心です。しかし被害が拡大するにつれて「国がもっと主導すべき」という意見も増えています。
一方で、以下の課題も指摘されています。
- 生息数の把握やモニタリング体制の不足
- 人的・財政的負担の大きさ
- 駆除と保護のバランス
- ハンター育成や免許制度の見直し
駆除強化か、共存策重視か、地域による判断か──今後も議論が続くと考えられます。
まとめ:これまでの常識が通じない時代に
2025年の北海道で起きているヒグマ出没の増加は、単なる一時的現象ではありません。
- 木の実の凶作
- 気候変動
- 森林環境の変化
- 個体数の増加
- ハンター不足
これらの要因が複合的に影響し、人の生活圏とヒグマの距離は確実に縮まっています。札幌市や道内各地で「過去とは違う状況」が続いている今、行政の対策だけでなく、住民一人ひとりの警戒も欠かせません。
今後も木の実の豊凶や個体数の推移、対策の進捗によって状況は変化します。命を守るためには「自分の地域でも起こりうること」として意識を高めていくことが重要です。