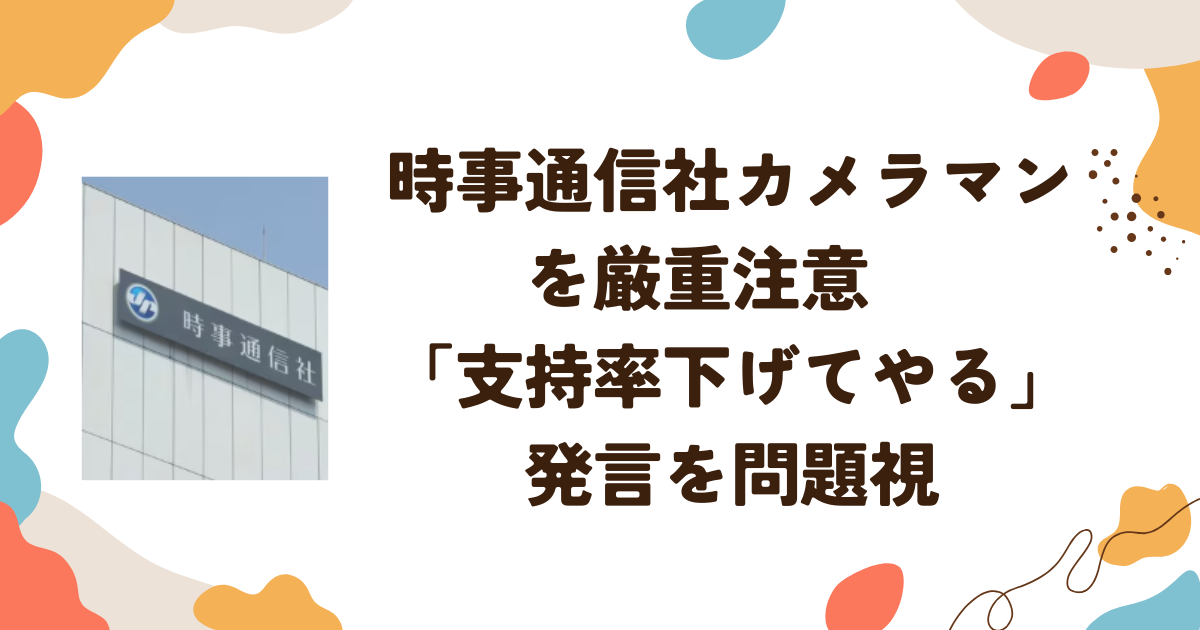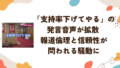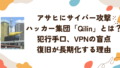2025年10月7日、自民党本部での取材中に「支持率下げてやる」という音声が生配信に入り込み、SNSで拡散。報道の在り方やメディアの信頼性が大きく問われる事態となりました。
発言の主は、時事通信社の男性カメラマンであることが確認され、9日に同社が「厳重注意処分」と発表しました。
この記事では、事件の概要、時事通信社という会社の特徴、メディア業界全体に広がる課題、そして今回の騒動の本質について詳しく解説します。
事件の経緯:「支持率下げてやる」発言が生中継に
問題の発言があったのは、10月7日、自民党本部での高市早苗総裁の取材時。
報道陣が待機していた際に、時事通信社のカメラマンが他社の記者と雑談する中で、「支持率下げてやる」「支持率が下がるような写真しか出さねえぞ」といった発言をしました。
この音声が、民放テレビ局のYouTube生配信マイクに拾われてしまい、瞬く間にSNSで拡散。
「報道が政治的に偏っているのでは?」と疑う声が相次ぎ、時事通信社に批判が集中しました。
時事通信社とは? 新聞を持たない「通信社」という存在
「時事通信社」という名前はよく耳にしますが、実際にどんな会社なのかを知る人は少ないかもしれません。
時事通信社は、日本の二大通信社のひとつ(もう一方は共同通信社)です。1945年の終戦に伴い、戦時下の国策通信社であった同盟通信社が解散し、その業務が2つの新しい組織に分割・継承されました。
通信社とは、自社で新聞を発行するのではなく、取材で得たニュース記事や写真を全国の新聞社・テレビ局・ネットメディア・企業・官公庁などに配信する組織です。
つまり、私たちがテレビや新聞で目にする多くのニュースは、こうした通信社の配信をもとに作られているのです。
時事通信社は特に、
- 行政や経済の専門ニュース
- 海外の政治・国際情報
に強みを持っています。
また、一般向けのニュース配信だけでなく、官公庁や企業向けに専門的なデータベースも提供しています。たとえば「インターネット行政情報モニター(iJAMP)」などが代表例です。
宗教・政党との関係性は?
時事通信社は、特定の宗教団体や政党の機関紙ではありません。
基本的には「中立・公正な報道姿勢」を掲げています。
しかし、過去には内部の不適切な言動が問題になったこともあります。
たとえば2015年には、記者が沖縄県議会関連の質問中に「もう、そんな連中は放っておいてもいい」と発言し、異動処分を受けました。
また、旧統一教会(現・世界平和統一家庭連合)との関係についても、社内で注意喚起が行われた時期があると報じられています。
今回の「支持率下げてやる」発言も、そうした「中立性への信頼」を揺るがす出来事として、重く受け止められています。

オールドメディアへの批判が再燃 「奈良公園シカ報道炎上」なども
今回の件をきっかけに、SNSでは「オールドメディア(伝統的メディア)」への批判が再燃しました。
近年、テレビや新聞による偏向報道がSNSで指摘されるケースは少なくありません。
特に2025年総裁選前の高市氏の”外国人シカ暴行発言”に対する、日本テレビの「奈良公園のシカ」報道が炎上。番組内で「観光客のマナー問題」を強調しすぎた編集が批判され、「メディアの切り取り報道」として議論を呼びました。
こうした一連の出来事により、国民の中で「報道機関は信用できるのか?」という疑念が広がっているのです。
自民党鈴木広報本部長:「非常に残念な発言だ」と問題視
今回の「支持率下げてやる」発言をめぐっては、自民党内でも「報道のあり方そのものが問われている」との声が上がっています。
鈴木貴子広報本部長は、「非常に残念な発言だ」としつつも、発言者の特定には踏み込まず、あくまで「報道機関としての姿勢」が問題の核心だと示唆しました。
自民党内では、高市総裁への批判や揶揄ではなく、報道全体の信頼性を揺るがす行為として受け止める向きが強いと考えられます。
騒動の本質は「報道の信頼」と「情報空間の変化」
今回の騒動の本質は、単なる一人のカメラマンの失言ではありません。
報道の中立性と国民の信頼がどこまで維持されるのか、その根本的な問題が問われているのです。
SNS時代、情報は瞬時に拡散し、視聴者自身が“監視者”のような立場になっています。
一方で、報道側には「伝える責任」と同時に「信頼を守る責任」が求められます。
報道の自由は民主主義の根幹ですが、それは中立性と誠実さの上に成り立つもの。
たとえ雑談でも「報道する側の姿勢」が軽んじられれば、メディア全体への信頼が崩れていく危険があります。
まとめ:信頼を取り戻せるか、時事通信社と日本の報道
時事通信社は今回の件を受け、「関係者の皆様に不快感を与えた」と謝罪し、社員教育の徹底を約束しました。
しかし、いま求められているのは再発防止だけではなく、“報道の透明性”の回復です。
「誰が」「どんな目的で」「どのように」ニュースを伝えているのか。
視聴者がそれを知る権利を持ち、メディアが説明責任を果たす時代に入っています。
一人の発言が生んだ今回の騒動は、報道業界全体にとっても、信頼と中立性を見直す転機になるかもしれません。